参加者の声
-
話し合いで得た気づきを吸収し 明日への活力としていく
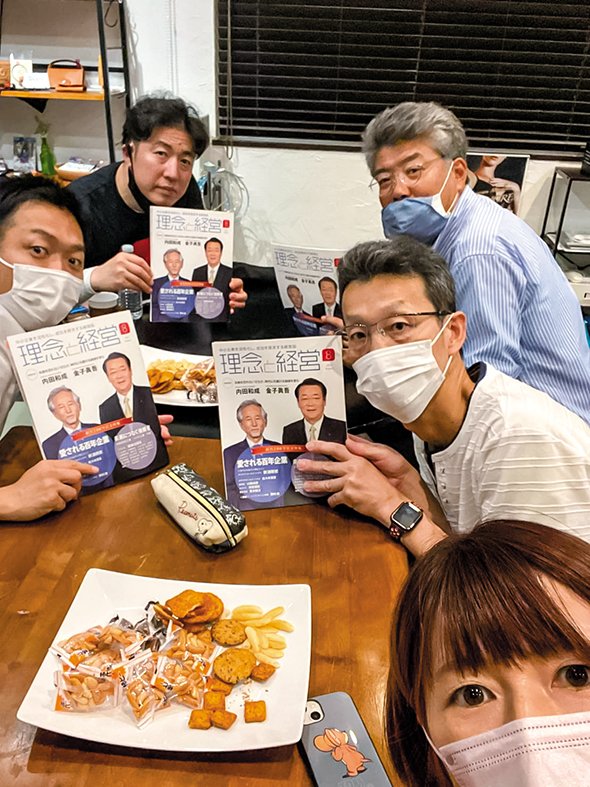
茂原支部(千葉県)
海保 宏之弊支部は、茂原市内で経営者仲間が集い、一〇年以上にわたって和気あいあいと楽しく活動してまいりました。三年ほど前からは、場所を大網白里市に移し、六~八名で活動しています。
コロナ禍に突入したばかりの頃は、勉強会をZoomでの開催に変更することで何とか月一回集まれるようにし、学びを継続するための努力を重ねました。現在は、「できるだけリアルで集まろう」という総意の下、前向きに学び続けています。
勉強会では参加者が各自の経営課題を持ち寄り、話し合いから多くの気づきを吸収することで、明日への活力にしています。異業種の経営者が集まっており、さまざまな角度から意見を出し合うので、毎回多くのことを考えさせられます。また、初めて参加されたゲスト経営者も、学びの多さに感心し、気づきの大切さを実感して帰られています。
これからも「学びの深掘り」をテーマに掲げ、皆で楽しく活動してまいります。
-
〝出会いと縁で道は開ける〟と 実感させてくれる勉強会

恵比寿支部(東京都)
栗駒 和訓〝人生で起こることにはすべて深い意味があり、人生で出会う人すべてに深い縁があります。〟―田坂広志さんの言葉です。「経営者の会」は、この教えを実感させてくれる場です。
約三年前から続くコロナ禍は世界に大きな波紋を呼び、多くの変化をもたらしました。また、今年二月、ロシアのウクライナ侵攻によって平和が脅かされました。戦争の影響で燃料や穀物の輸入が困難となり、資源や物流のコストが上昇。世界全体が新たな困難に直面しています。
そんな中、今月は「渋沢栄一に学ぶ仕事道」から、〝譲れない信念は何か〟というテーマについて討議しました。「顧客中心主義」「事業の永続」「従業員の誇りと尊厳」「諦めず挑戦し続けること」など、さまざまな考えに触れることができました。
事業を取り巻く環境は、日々変化していきます。その変化に意味を見出し、たった一つの出会いと縁を手繰ることで道は開けます。私たちの支部は「出会いと縁を大切にする」勉強会です。
-
勉強会の前の話し合いから 仲間の“ペインポイント”を引き出す

増田支部(福井県)
増田秀勝二〇一七年一月に支部登録をして以来、毎月勉強会を開催しています。当初は仲間の考えを引き出すことに苦戦したり、会員拡大が思うように進まないことに悩んだりしていました。尾崎支部の皆さんも同じ悩みを抱えていたことから、今では尾崎&増田支部として合同で開催をしています。
コロナ禍では、感染が拡大していくにつれ、定刻になっても人が集まらないことが増えました。誰もが必死で業績を回復させようと奮闘していたためだと思います。そこで、開催前に仲間同士で自社の悩みや業績回復の見込みなどについて話し合うようにしたところ、徐々に定刻に集まってもらえるようになりました。社内ではなかなか言えないことでも、勉強会の仲間への信頼が厚いからこそ打ち明けられるのだと思います。
今では、勉強会の三〇分~一時間を、仲間の“ペインポイント”を引き出す時間に充てています。これからも楽しい雰囲気のなか、気持ちを整理できる集まりにしてまいります。 -
“経営の真の目的”を知るために 欠かせない貴重な集い

志命塾(石川県)
竹野一茂志命塾は、『理念と経営』経営者の会・梶谷晋弘前会長の梶谷支部が前身となっている勉強会です。現在、会員は約四〇名。普段は中崎支部、黒田支部、中濃支部、竹野支部に分かれて活動をしていますが、勉強会は五支部合同で開催しております。オンライン開催の時期もありましたが、現在はリアルで開催しています。
毎月の勉強会は約二時間で、会の前半では地元の経営者の方などに講演をしていただき、それに対する質疑応答を行っております。後半では支部ごとのグループに分かれ、『理念と経営』と設問表を題材にディスカッションし、最後にグループの代表が参加者全員の前でディスカッション内容の共有を行っています。
志命塾には、「1.自らの使命を知り、経営の真の目的(理念)を知る」、「2.経営者自身の人間力を高める」、「3.縁ある人々の物心両面の幸福と持続可能な経営の実現」という目的があります。会員一同、これらの目的を常に意識し、学び続けています。
-
参加者への手厚いサポートで 誰もが安心して参加できる場に
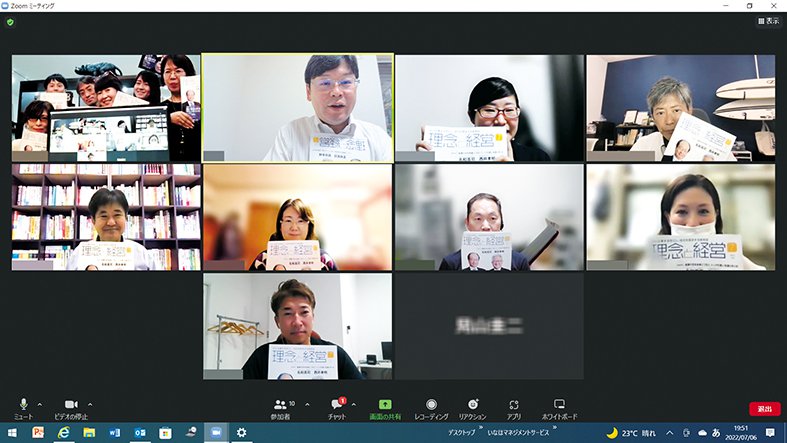
浜松支部(静岡県)
稲穂充月一回の浜松支部の勉強会は、今年度から経営研究会の副会長や委員長が持ち回りで運営を担当するようになりました。
七月の勉強会は、担当委員長の会社会議室をお借りし、会場参加六名、リモート参加九名で開催しました。入会検討中の方や新入会員の方が見学する中、参加者は実践報告や失敗談などを発表していきました。
一連の取り組み発表からは、初参加の方も学ぶ意欲を高めておられました。進行役の担当副会長がお一人お一人の発表に承認や質問を交えつつ丁寧に進めてくださるほか、庄田会長や高橋前会長がアドバイスをくださるのも大きな魅力です。経営実践のヒントがたくさん得られる場として、多くの方がリピート参加してくださっています。
また、会場では、会の後に本音で話し合う懇親会を実施し、参加者に会場参加の魅力を感じてもらうことで次回参加をモチベートしています。会員のサポートが手厚いため、どなたでも安心して参加いただける勉強会です。
-
経営へのヒントに富む勉強会は あっという間に過ぎていく時間

鈴鹿神戸支部(三重県)
松田卓弥鈴鹿神戸支部は、五年前に阿部支部長が立ち上げました。最初は四名程度での開催でしたが、支部長が地元の経営者をお誘いくださり、今では一〇名程度の会になりました。
勉強会は設問表を中心に進めておりますが、自社の経営相談に発展することも多々あります。各自が自身の経営に対する考え方や自社の事例などを発表する中で、参加者が相互にさまざまなヒントを得られるため、自社の改善に繋げることのできる貴重な機会となっています。また、『理念と経営』の記事に関するそれぞれの発表を聞くことで、自社の課題や問題点に気づかされることもあります。支部には異業種の経営者が集まっているので、勉強会に参加すると自社の事業の外にあるさまざまな情報を得られ、世の中の変化に気づくきっかけにもなります。
勉強会は月一回、二時間行っていますが、あっという間に時間が過ぎていきます。これからも勉強会に参加して楽しく学び、自社を良くしていきたいと思います。
-
経営者にとっての勉強会は 学びと情報収集の得難い場

井上支部(京都府)
桃井 康行約五年前は、経営の勉強に必要性を感じつつも、活字への苦手意識から『理念と経営』を活用し切れていませんでした。そんな折に勉強会へのお誘いを受け、今日まで継続して学んでいます。
コロナ禍の当初は、勉強会をリモートで開催していました。現在は、遠方の方や会場参加できない方のため、リモートとリアルのハイブリッドで開催しています。先行きが不透明な中で勉強会に参加される経営者の方は、学びの場を欲しているように感じます。毎回、初参加のゲストがいらっしゃるのも、その表れのような気がします。
勉強会には、多様な業種の経営者、社員、時には現役の大学生が参加しています。そのため、いろいろな角度からの意見が飛び交い、多くの気づきと学びを得られます。さらに、設問表に沿った勉強会だけでなく、日々の学びを共有する勉強会を別で開催し、マンネリ化を防いでいます。経営者にとって、学びと情報収集の機会となる良い勉強会となっています。
-
勉強会は、学びを共有し、 仲間と共に成長する機会
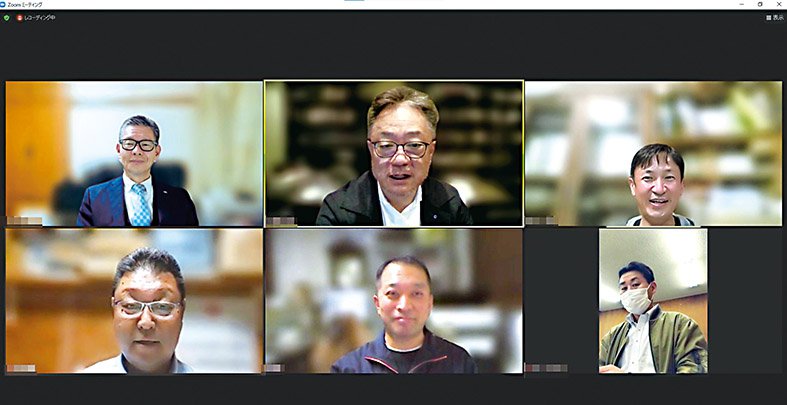
湖東支部(滋賀県)
佐野正一郎湖東支部は、昔から関わりがある経営者仲間を中心に、「会社や地域を良くしたい」と思う一一人で活動をしています。
勉強会では、適度な緊張感の中、一人ひとりが設問表を基に発表されますが、一つの設問で二時間を使い切ってしまうほど議論が白熱することもあります。これは、仲間が互いに理解し合っており、信頼関係ができているからだと感じています。
また、メンバーの多くは、人財育成、社内のコミュニケーション、社風、戦略など、たくさんの経営課題を抱えています。そうした課題を持つメンバーにとって、経験に基づく仲間からのアドバイスは、解決に繋がる糸口です。同時に、議論の中で得たヒントや気づきは、自社の成長に大きく役に立っています。
そして、私たちは「何のために経営をしているのか」を自問自答しながら、激変する時流に対応できる強くて良い会社づくりを目指しています。これからも理念を基に、目標に向かって挑戦し、前向きに学び続けます。
-
多彩な業種の仲間たちと 親睦を深めながら高め合う

城東支部(徳島県)
伊丹慎治城東支部は、中央支部が大きくなり過ぎて分封をしていただいたばかりの新米支部です。開催も中央支部と同場所です。
城東支部の親元・中央支部は、『理念と経営』発刊から間もない頃、徳島経営研究会の学びと親睦を深める趣旨で開設されました。現在、城東支部のメンバーは一三名です。メンバーの業種は製造業、税理士法人、テニススクール、建築業、飲食業、製薬業、広告印刷業、学習支援事業と多彩です。皆さん開催を楽しみにしていただいているようで、『理念と経営』の感想発表はもちろん、情報交換をしたり、お互いの悩みを相談し合ったりする有意義な会になっています。
また、三名のメンバーがこの会から経営研究会に入会してくださいました。会の内容が素晴らしく、先輩の面倒見も良いことが要因だと思います。今後とも、経営の成功を目指す仲間たちと高め合いつつ、親睦を深めていける会でありたいと思っております。
-
勉強会の運営方法を工夫し 「学び」を深めていく

新家谷支部(香川県)
新家谷剛志新家谷支部は、香川経営研究会のリーダーシップ委員会のメンバーを中心に毎月開催しています。六、七人で集まり、新家谷支部長を中心に和気あいあいと開催しています。
私たちの勉強会の大きな特徴は、リーダーを毎月変えていることです。月ごとのリーダーが、各々のやり方で勉強会の運営をしています。狙いは、リーダーを持ち回りにすることでマンネリ化を防ぐことと、その月のリーダーにリーダーシップを学んでいただくことです。
また、ある時には、あえて設問表を使用せず、メンバーの問題にフォーカスしてディスカッションを行いました。結果として、問題を抱えていたメンバーが大きなヒントを得られた効果的な勉強会になりました。設問表を用いて勉強会を開催するのは基本ですが、勉強会での学び方は様々な応用が利くとも感じています。今後は、この勉強会に定期的に新しい仲間を連れて来ることで、学びの仲間を増やしていきたいです。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






