導入企業の声
-
お客様の喜びを 共に創る

有限会社 フードショップふじむら
藤村昌弘徳島県で「感動ある人生を共に創る」という経営理念の下、スーパーマーケットを経営しております。スタッフが増えたことによるコミュニケーション不足を解消し、意識をすり合わせるため、勉強会を導入しました。
その結果、仲間の考えを知ることができ、部門を超えての交流も活発になりました。お客様への貢献度も、明らかに高くなったと感じております。
全スタッフが参加できるよう、毎月二日に分けて開催し、開催時には勉強会の目的も共有しています。交代制で決められた司会者は、開催前は勉強会の目的と司会者の役割を共有し、開催後は良かった点と改善点を幹部も交えて話し合っています。
参加したスタッフも、最初は難しく感じていたようですが、徐々に理解が深まり、最近は読みながら自分が同じ立場ならどう振る舞うか考え、仕事に活かしているようです。今後も共感し合える場として勉強会を継続していきます。 -
意見を発信し 共に成長する場
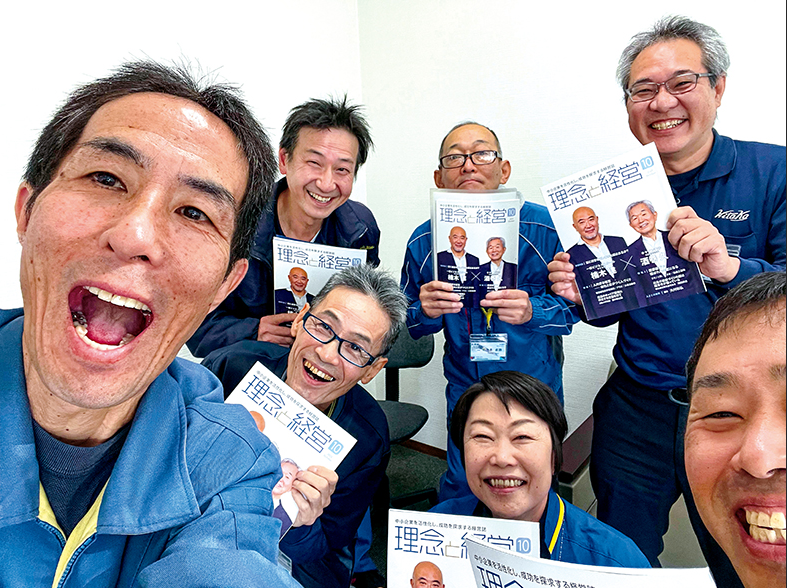
日隆産業株式会社
林剛志弊社は自社のみならず、お客様、協力会社と共に成長を目指す「相利共生」を経営理念に掲げ、大阪市に本社を置き、運送業を営んでおります。
毎月一回、摂津営業所において「共に学ぶ会」を実施しております。各セクションの責任者が設問表の内容を発表し、それに対して全員でディスカッションを行います。
二〇二二(令和4)年四月にスタートした頃は、受け身で感想を述べるだけでしたが、回を追うごとに自らの意見や考えを積極的に発信し、議論し合う場に変わっていっています。
設問表の内容に関するもので始まりますが、議論が白熱して「そもそも内容は何でしたっけ?」と脱線してしまうなんてこともしばしばあります。それだけ各々が自分の意見を持ち、人間力が向上している証しだと感じます。
今後も自社に関わるすべての人たちと共に成長することを目指して、「共に学ぶ会」で得たものを発信し、共有していきます。 -
愛ある社風で 魅力度日本一へ

芦葉工藝舎
芦葉武尊私たちは埼玉県幸手市にて工務店を経営しております。今や、お客様から直接受注する工務店は本当に少なくなりました。工務店とは大工棟梁を中心とした技術者集団です。棟梁がいて、研修中の大工がいます。日本の家造りを担ってきた地域工務店の今後の「あるべき姿」を追求しております。
挨拶、元気、掃除の徹底、助け合うこと、学ぶこと、感謝すること……まさに毎日凡事徹底です。みんなの好きな言葉は「愛ある社風」です。目標は「魅力度日本一の工務店」。売り上げよりも、まずは付加価値と魅力度を高めることを目指しています。
当社では五つの委員会活動を行っています。新人研修の「社長塾」、知の共有を目指した「大工塾」、そして月末は会社の羅針盤として「みんなの会議」を開催します。その際に勉強をするのが理念と経営委員会主催の「共に学ぶ会」です。
みなさん、信はチカラなりです。学び続けましょう。ぜひ、お立ち寄りください。 -
視野を広げ、 思いを共有する時間

淀川中央動物病院
菅木佑始こんにちは、淀川中央動物病院です。当院は新大阪駅近くに二〇一一(平成23)年開業いたしました。開業以来、右肩上がりに急成長してきましたが、一〇年が経過したとき、理念が存在しないこととチームとしての学びを深めていないことが致命傷となり、大きな後退を余儀なくされました。その時に共に学ぶことの大切さを痛感し、『理念と経営』の勉強会と「13の德目」朝礼を同時に導入しました。
本誌を読むことで、さまざまな業種の方々の仕事に対する考え方や価値観、人生観を学ぶことができるので、社員さんと共に視野が広がっていくことを感じています。
また、日頃伝えられない事業に対する私の思いを設問表の回答を通して伝えることができるとともに、社員さんの深い考えを知ることもでき、貴重な時間になっています。
今はまだインプットで精いっぱいですが、いずれ得た知識を自社に落とし込み、動物たちや飼い主様がより喜んでいただける取り組みを、社員さんと共に話し合い実践する喜びを感じていきたいです。 -
お客様の喜びが 私たちの喜びに

ダイトー工業株式会社
真渕幸治徳島県を拠点に、産業用設備の設計から部品加工・組立・制御・据え付けまで、自社で一貫して行っています。より良い設備提供を行うことでお客様の喜びを創造しております。
われわれの仕事の醍醐味は、全く何もない状態から作り上げるところにありますが、毎回ゼロからの挑戦のため、幾度も失敗や紆余曲折があり、社員の気持ちがバラバラになりかけていたその時『理念と経営』の勉強会を知り、導入しました。
部署を越えたコミュニケーションや他者受容力を「共に学ぶ会」を通じて少しずつ養い、失敗に対する思いを共有し行動に繋げた結果、「DAITOチーム力」が上がり、ワークエンゲージメントとパフォーマンスの向上に繋がりました。今では、お客様により良い設備提供を行うことでお客様の喜びが生まれ、それが私たちの喜びに繋がっています。
今後も変化し続ける不確実な社会情勢にも「DAITOチーム力」で立ち向かえると信じています。 -
現場の様子が聞ける 貴重な機会

小笠原建設株式会社
馬場雅代わが社は、愛知県新城市で土木工事を主に行っている建設会社です。
経営理念である「地域の安全と環境(まち)づくりに貢献し、社会に役立つ人財を育てます」を基に、自己成長と人間力向上を目指して勉強会が始まりました。当初は幹部のみの参加でしたが、二〇一三(平成25)年頃からは、職種や年齢に関係なく、全社員が数名ずつのグループに分かれて、現在も毎月実施しています。
司会進行役は交代制で行うので、コミュニケーションの取り方や対応力を養えているのではないかと思います。
私の所属する総務では、現場の監督や作業員の方々と時間をかけてお話しする機会がほとんどないため、勉強会の場では、現場での様子や設問表の答え、ちょっとした雑談等を聞くことにより勉強になると感じます。
今後も継続していき、円滑な業務に繋げていけたらと思います。 -
競争ではなく協調、 考え方を整える

株式会社名友産商
ジンジン ピョン愛知県小牧市にあります株式会社名友産商です。弊社は、創業四八年目を迎え、自動車部品及び機械部品の製造をしております。共に学ぶ会は、毎月違うメンバーで約一時間程度開催し、一人ひとり発言する場として大切にしています。
次世代のリーダー候補をグループリーダー、ベテラン社員さんを書記として、技能実習生も交えて開催しています。社員さんのモチベーションアップ、インターンシップの採用に役立っているほか、実習生の日本語力向上や日本での働き方の理解を深めることにも一役買っています。
競争ではなく協調、コミュニケーションを密に取ることで、全体のレベルアップにもなり、実習生も外国人社員も、日本人社員も全員参加することで、考え方を整える機会になっていると思います。それぞれが自分の意見や、思いを語りあいチームワークにつながり始めています。
この勉強会を通じて、みんながさらに能動的な人材になれるよう、私自身も頑張っていきます。 -
総合的な能力が 向上しています
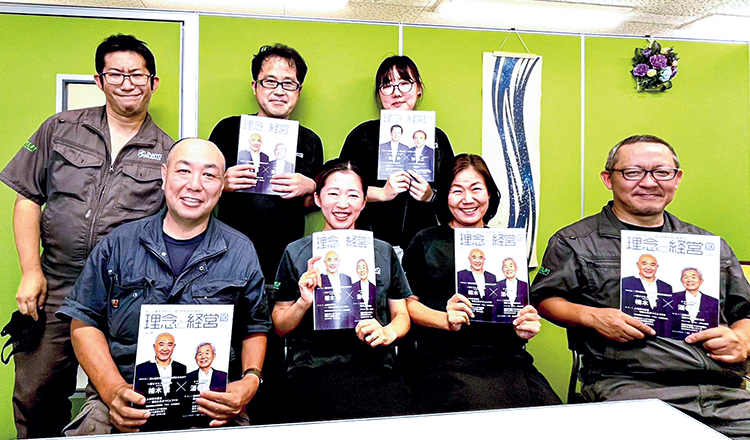
山陽製紙株式会社
竹下浩一弊社は大阪の空の玄関口である「関西国際空港」に近く、自然に恵まれた大阪府泉南市に本社を構え、まもなく創業一〇〇周年を迎えます。「環境に配慮した循環型社会に貢献する」という理念のもと、「紙創りを通してお客様と喜びを共有する」ことを目指して製紙業を展開しています。
私たちは単なる技術力向上だけでなく、本誌を活用した勉強会を通じて、部署を超えたコミュニケーションを促進しました。その結果、多くの社員さんたちが傾聴力、考える力、感謝力、プレゼン力など、総合的な能力を向上させることができたと感じています。
現在、毎月、社員さんが提案した「オリジナル設問表」を使用しており、さらなる成長を支えています。これからも、共に成長し、充実した人生を送るために、全社一丸となって学びを深めていきたいと思います。 -
新たな気づきに 繋がっています

株式会社花田工務店
古澤悠弊社は、愛知県内を中心に建設業を営んでおり、今年で創業九五周年を迎えました。「不動産オーナーの問題解決屋」を目指し、グループ会社全体で設計施工の建設を中心に、リノベーション、不動産仲介・賃貸管理、資産形成サポート等、総合的に事業を設けています。
弊社では、人間力・チーム力の向上のために、部門・性別・年代が混合のグループに分かれ、月一回「理念と経営」を全員で読んだ後に設問表の内容に沿ってディスカッションを行っています。自身の意見をいかに伝えるかを学びつつ、日常業務だけでは話すことの少ない社員の考えを知ったり、アドバイスを得たりすることで新たな気づきに繋がっています。また、ディスカッションの進行をグループ内で毎回交代することで、ファシリテーションスキルの向上にも役立っています。
今後もより多くのお客様に喜んでいただけるように人間力・チーム力を高める取り組みを継続していきます。 -
部門の垣根を越えて 学び合う組織へ

株式会社ネオランドリー
皆川幸太郎神奈川県横浜市を中心とし、「衣類のクリーニングを通して、お客様の嬉しい! 便利! 助かった! という喜びと安心感を提供し思い出豊かな人生の創造に貢献する」よう、五二店舗のクリーニング店の運営を行っています。
「共に学ぶ会」を導入した目的は、部門の垣根を越えて学び合う組織を創ることと、他社の事例からより多くのお客様に喜んでもらう考え方や、在り方を学ぶことです。現在は「徳目委員会」という委員会活動の一環として、毎週進行役を代えながら、設問の回答に対し感想や意見などを伝えあっています。
コロナ禍により、いま一度自社の在り方を見直す上で、学ぶ会を通じ社員さんの思いに触れることができ、新たなビジョンを描くことができました。現在はリモートで開催することが多いですが、懇親会を兼ね一堂に会し楽しく学ぶ企画を考えています。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






