導入企業の声
-
「会社」の枠組みを越えた学びが 社内改善に役立っている

株式会社丸通地建
近藤希美弊社は、岡山県瀬戸内市で不動産業を行っております。地域密着型で経営させていただいているため、対応エリアを会社から三〇分以内で移動できる場所に限定しており、お客様の呼び出しにすぐに駆け付けて対応できるようにしています。また、分譲も地域のことを考えて行っております。
月一回の勉強会は、弊社の全社員に加え、協力業者や地元の会社の社員さんたちを集めて行っております。そのため、同業・異業を問わず、多様な人々と関わりが持てる場となっています。勉強会でメンバー各々の捉え方や考え方、想いを伝え合うことは、改めて弊社の理念や社風を捉え直し、社員共通の価値観を形成するための貴重な機会です。
また、経営上の悩みを相談し合い、アドバイスや改善案、実例を互いに共有することもあります。意欲の高いメンバーから得る知見は、社内改善に役立っています。これからも勉強会を続け、そこで得た学びを弊社の価値観教育や改善活動に繋げていきます。 -
社員同士で認め合い お客様のためにより良い選択を
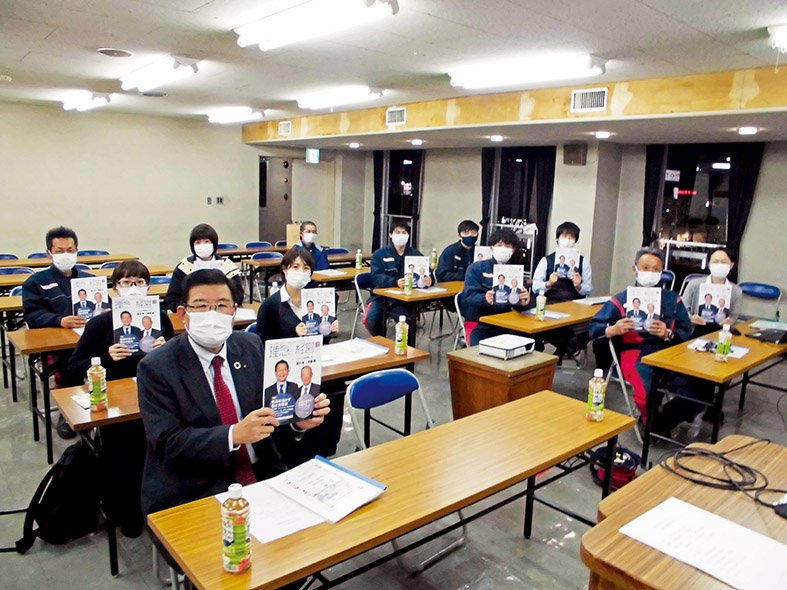
株式会社神戸ダイハツ
阿部雅登弊社は、一九六三(昭和38)年創業の自動車販売店です。「カーライフサポートで一人一人のしあわせづくり」を経営理念とし、「お客様のお役に立ちたい」という創業時からの純粋で誠実な思いで地元のお客様と向き合ってまいりました。おかげさまで今年の五月で創業五九年を迎えます。
勉強会は二〇〇八(平成20)年からスタートしました。現在も、毎月一回行っております。勉強会には発表者の意見を認め合う雰囲気があり、新入社員でも意見や考えを率直に発表できています。また、普段なかなか交流することのない他部門の社員同士が、和気あいあいとコミュニケーションを取れる時間でもあります。
普段の業務でも、人の意見を一旦受け入れ、それからお客様のためにより良い選択を社員同士で話し合って見つけるという姿勢に変わってきています。これからも社員同士の大切なコミュニケーションの機会として勉強会を続けていきます。
-
勉強会を重ねるごとに 経営理念の浸透度が深まる

株式会社オアシス
山岡友紀当社は「ライフプランコンシェルジュ」として茨城県つくば市に本社を置き、神奈川・兵庫・福岡でライフプランを基にしたサービスを提供する、保険と住宅ローンの代理店を運営しております。
以前は、グループに分かれ別日で勉強会を開催していました。他グループの考え方も共有したほうが良いという意見があり、現在はオンラインを活用し開催。数名のグループに分かれ八〇分のディスカッション、一〇分のグループ発表の時間を取り、全員がどんな考えを持ったのか、共有をしています。
自社の方向性や新しい事業のアイデア、お客様に対する想いなどが、回数を重ねるごとにブラッシュアップされていき、「私たちは『ライフプラン』を通じて全ての人たちと幸せを追求し続けます」という経営理念の浸透度が深まっていることを強く感じます。
最近では内定者が参加して入社前のコミュニケーションをはかる場としても活用しています。今後も価値観を共有し「幸せの追求」を目指して日々成長し続けていきます。
-
「人こそ我が宝」の念いで 仲間と価値観を共有し合う

グリーンウッドタクミ協同組合
浦田将成私たちは三重県松阪市で東海地区最大級の木材製造工場として、住宅や公共施設などで使用する木材を製造、販売しています。毎日の幹部ミーティングに加え、月一度の全体会議で情報共有を行い、その後に仲間全員で『理念と経営』を用いて勉強会を実施しています。
勉強会は、理念委員会が独自で考えた質問に対し、五~六名のグループに分かれて各リーダーを決め、それぞれが発表を行います。理念委員会の添削に理事長の一言を加え、仲間へ返却する体制を作っています。
工場では最新鋭AIの無人機械化が進む中、やはり仲間の考え方の相互理解や信頼関係を築くことが大切です。そういう意味で、勉強会は仲間と価値観を共有し、コミュニケーション能力を高める場となっています。また、全体会議の後に行うことで情報共有の落とし込みへとつながっています。
弊社の社訓である「人こそ我が宝」の念いを大切にし、働く仲間と一緒に成長、会社発展、業界発展を目指していきます。
-
勉強会で社内環境だけでなく お客様への対応も変化した

株式会社クボタ贈商
窪田幸雄弊社は、北海道旭川市でカレンダーやタオルの企業用名入れ商品を中心とした贈答品販売店を営んでおります。
勉強会は社員とのコミュニケーションツールとしてとても役に立っています。『理念と経営』を読んで感想を言い合い、意見交換することで価値観が共有されています。月に一度、自己開示ができたり承認し合ったりする場があることで、社内に統一感が出てきました。また、それぞれの行動基準も明確になってきました。『13の徳目』と合わせて行うことで当月のテーマと設問が絡み合い、とても前向きな考え方でチャレンジ精神が湧いてきているように感じます。
勉強会を始めてから電話対応なども明らかに違ってきています。お客様のために、という意識が伝わる対応になってきました。職人さんにとっては慣れないこともありますが、難しい言葉も覚えていくことでより共通言語が広がっているようにも感じます。
今後も勉強会を続け、コミュニケーションを円滑にし、明るく楽しい環境を作っていきます。
-
学びを通して未来を語り、 ビジョン共有の場をつくる

株式会社トムコ
田村純也私たちは岡山県倉敷市、広島県福山市を拠点とし、産業発展支援業を行っています。我が社の強みは対応力です。取り扱い困難な無機化学薬品(毒劇物)にもノウハウを有した人財と特殊車両で、安全な対応をしています。
勉強会は理念の浸透と人財育成を目的とし、月一回のペースで開催しています。近年では私たちを取り巻く経営環境が目まぐるしく変化していることからビジョン実現に向け、今後の我が社は「どう在るべきか」、そして「どうするべきか」を具体的に語り合うことが増えています。特に若手の社員さんには、経営者の考えを直接聞けることや管理者とのディスカッションが新事業・新市場へのチャレンジの動機づけとなっており、勉強会の価値が一層高まっています。会の最後では毎回感想を一人ずつ発表するようにしていますが、新人の社員さんも「次回も参加したい」と笑顔で答えてくれます。
これからも素晴らしい同志と共に学び続け、我が社の経営理念を追究し、必ずビジョンを実現します。
-
勉強会が部門を超えた情報共有と 問題解決に役立っている

株式会社ちむら
千村大輔私たちは、「美味しさづくり・幸せづくり」の経営理念のもと、慶応元年創業以来、鳥取市で代表商品「とうふちくわ」を中心とした、練り製品の製造・販売を行っております。
二〇〇八(平成20)年にスタートした『理念と経営』の勉強会は、現在すべての社員で取り組んでおり、毎月設問表へ解答することを通して、自分自身の意見を明確にし、各企業の取り組みを自社に置き換えて、活かす機会となっています。
月に一回、終業後に勉強会を開催し社員が集まることで、『理念と経営』を活用した大切なコミュニケーションの場となっています。普段なかなか顔を合わせることのできない店舗の社員から生のお客様の声を製造現場の社員に届けたり、新商品開発の意見交換をしたりするなど、部門を超えた情報共有、問題解決に役立っています。
この勉強会は、自身の成長と社員間のコミュニケーションを円滑にするためにも欠かせない取り組みとなっています。
-
「全部正解」で取り組むうち、 社内の空気が大きく変わった

株式会社上々
竹村陽子当社は愛知県瀬戸市で「素敵なお母さんづくり」を理念に、整体、エステティック、ハンモックを使ったヨガ、パーソナルトレーニングで健康な心と体づくりを提供しています。お母さんのコンプレックスやストレスの解消で心の余裕を生むことが、子どもたちの可能性を広げる未来をつくるという想いでそのお手伝いをしています。
独立志向の業種ゆえ学びに対する意欲は高いのですが、離職率が高いことが当社の大きな課題でした。それを相談した愛知経営研究会の仲間に「質のいいアウトプットは質のいいインプットから」と勉強会を推奨され導入しました。
学ぶ会では、普段、自分では絶対に取りに行かない難しい情報を解釈することでさまざまな意見がでます。そんな相手の意見を絶対に否定しないというルールの中、「全部正解」でそれぞれの考えを認め合うことを繰り返しているうちに、社内の空気が大きく変わりました。「お客様のために」「仲間のために」「会社のために」という言葉が飛び交うようになり、チームで仕事をするようになったことが大きな成長です。
-
“学ばざる者食うべからず!” 勉強会で相互理解を深める
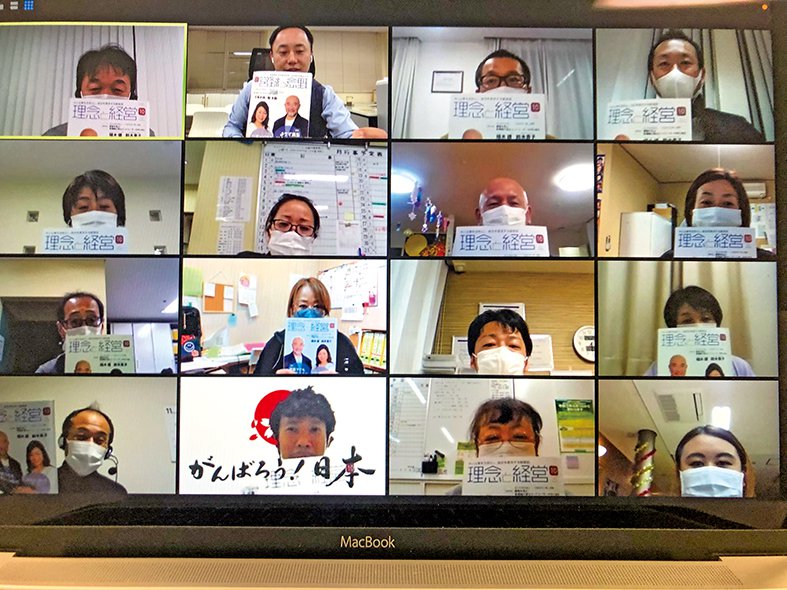
社会福祉法人 平成福祉会
中村昌史山梨県の東部、大月市、上野原市、都留市、道志村にて特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、グループホーム、居宅介護支援事業所、放課後等デイサービスを運営しております。
「しあわせを共に〜みんなを“しあわせ”にできる会社にしよう!〜」という経営理念のもと、仲間と共に学び成長するため、二〇一五年より『理念と経営』を用いた勉強会をスタートしました。
当初は月に一度、法人本部に集まり幹部会議の後に幹部社員のみが五~六名のグループに分かれて行っていました。次第に参加を希望する社員が加わったり、事業所単位で開催したりと、徐々に学びの輪が広がっていきました。現在はオンラインに切り替えて行っています。
勉強会を行うことで、社員同士の相互理解が深まり、これまで以上の絆が生まれています。また、異業種の経営者の方の話や考え方に触れ、視野や思考の幅が広がっているように感じています。
平成福祉会では「学び=仕事」です。“学ばざる者食うべからず!”の気持ちでこれからも学び続けます。
-
考えを承認するスタンスで コミュニケーション力を高める
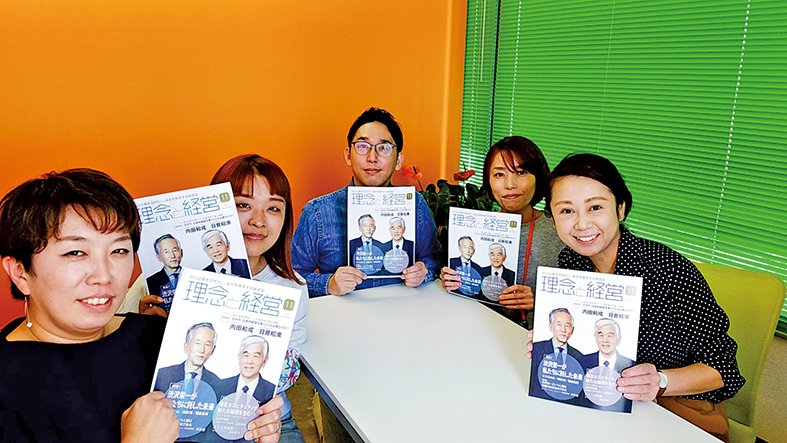
株式会社ミンナのシゴト
川田有子私たち「ミンナのミカタぐるーぷ」は、栃木県鹿沼市で「日本から障がいという言葉と概念を無くす」というビジョンを掲げ、就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所・就労支援事業所特化型お仕事マッチング業を展開しております。
共に学ぶ会は、社員さん一四名を二グループに分け、それぞれの発表に共感し、考えを承認するスタンスでコミュニケーションを図っています。
会を導入した頃は、自分の考えを発表するのが苦手だった社員さんや、自分の考えを押し通す社員さんもいました。しかし今では「そういう考えもあるよね」「私はこう思うけど、皆はどう思う?」というように固定概念にとらわれず、さまざまな考えを承認できるようになり、発想と視野も広がりました。
毎月司会進行を交代制にすることにより、聞き出す力や要約力もつき、実際の現場でもコミュニケーション力を発揮しています。
今後も共に学ぶ会を通して成長していきたいと思っております。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






