『理念と経営』WEB記事
巻頭対談
2025年4月号
蔦屋重三郎に経営を学ぶ
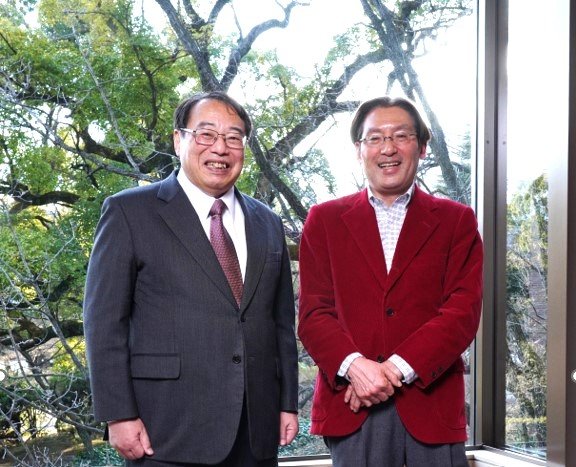
歴史小説家 高橋直樹 氏(右) ✕ 歴史家・作家 加来耕三 氏
世襲や身分制度によって、すべての物事が決まっていた江戸後期―。遊郭街「吉原」で頭角を現し、斬新なヒット作を次々に生み出して、硬直した社会に風穴をあけてきた「江戸のメディア王」こと蔦屋重三郎。その類いまれな発想力と行動力は、現代の中小企業経営者にも多くの示唆を与えてくれる。
史料が乏しいからこそ、
想像の翼を広げて描いた
―〝蔦重〞こと蔦屋重三郎を主人公にした、今年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』によって、「蔦重ブーム」が起きています。蔦重は、江戸後期に版元(出版社)兼書店の「耕書堂」を経営して、本や浮世絵などの大ヒットを連発した「江戸のメディア王」でした。彼の生涯には、現代の中小企業経営者が学ぶべき点も多いと思います。
そこで、小誌で「蔦屋重三郎と江戸文化」を連載中の加来先生と、蔦重を主人公にした小説を先ごろ刊行された髙橋先生に語っていただこうと、この対談を企画いたしました。
加来 髙橋先生の『蔦屋重三郎 浮世を穿つ「眼」をもつ男』、大変面白く読ませていただきました。
髙橋 ありがとうございます。執筆にあたっては蔦重について深く調べましたが、史料がほとんど残っていないのですね。江戸時代の有名人だったはずなのに、意外でした。
加来 そうですね。蔦重の菩提寺は東京・浅草の「正法寺」ですが、そこにある2つの碑に書かれた文章が、数少ない史料と言えるでしょう。1つは蔦重本人が亡くなったあと、友人の石川雅望(「宿屋の飯盛」の筆名で狂歌師として活躍)が書いた墓碣銘。もう1つは蔦重の母親の顕彰碑で、こちらは大田南畝(文人・狂歌師)が文を書いています。2つ合わせてもA4用紙1枚に収まる程度の短い文章ですが、蔦重の生涯が簡潔にたどられた貴重な史料です。
髙橋 ただ、墓碣銘も顕彰碑も、文章は蔦重を褒めたたえる内容ですね。功成り名遂げた蔦重が、友人の著名文化人に書いてもらったものでしょうから、内容をそのまま史実として捉えてよいか、ちょっと疑問です。
加来 確かに、褒め言葉については話半分で受け止める必要があるでしょう。ただ、蔦重の生没年とか、父親が尾張(名古屋)から江戸に来たとか、母親は元々江戸の人だとか、そういった伝記的事実は偽っても意味がないわけですから、信用してよいと思います。
いずれにせよ、蔦重の史料がほとんどないのは事実で、だからこそ、彼を主人公にドラマや小説を創る場合、かなりの部分を想像で埋めるしかありません。
髙橋 私の小説もしかりで、想像力を駆使して私なりの蔦重像を創り上げました。歴史学者なら主張には厳しく根拠が求められますが、小説家には自由に想像して史料の隙間を埋めてよいという特権がありますから(笑)。
加来 私も歴史家なので、自由に想像の翼を広げられる点は、ある意味うらやましいです。一例を挙げれば、髙橋先生の小説では、蔦重が極端な偏食家で、白米に塩をかけて食べながら清酒を飲むのが日々の食生活だったと書かれています。野菜などはまったく食べようとしなかった、と……。そんなことが記録された史料はないので、先生の創作ですよね。
髙橋 ええ。蔦重が「江戸わずらい」(脚気)によって、数え年48歳の若さで亡くなったことは史実なので、そこから想像を広げてそんな設定にしてみました。
加来 読者の皆さんのために注釈します。当時、「江戸わずらい」と名がつくほど脚気がはやったのは、それまで主に玄米を食べていた江戸の庶民層に白米食が広がり、脚気の原因となるビタミンB1不足を招いたからですね。蔦重もそれで命を落としたわけです。
吉原と一般世間を結ぶ仲介役を担った蔦重の「知識と人脈」
加来 中小企業経営者が多い『理念と経営』の読者にとって、いちばん関心があるのは「蔦重はなぜ大ヒット作を連発できたのか?」という点でしょう。つまり、経営に生かせる知恵をそこに見いだしたい、と思っているはずです。そこで、蔦重が出版プロデューサーとして成功した理由を考えてみたいのですが、髙橋先生はその点をどうお考えですか?
髙橋 私がまず思うのは、蔦重は人の懐に入り込む達人だったのだろうということです。いわゆる「人たらし」だったのだと思います。それはどこで培われた資質かといえば、やはり、彼が吉原で生まれ育ったことが大きな要因だったのでしょう。
加来 その点は、私も同感です。
髙橋 現代ではとかく、「吉原には文化的な香りもあった」と、プラス面が強調して語られがちですね。確かにそういう面もあったとは思います。吉原は、江戸の一流文化人が集う知的サロンとしての役割も担っていました。また、「粋」の美意識も、吉原が一つの源流になっていた面があります。
しかし、そうした面ばかりを強調すると、吉原の闇の部分を見落としてしまうでしょう。吉原は幕府公認の遊里として売買春が行われていた「悪所」であり、働く女性たちにとって「苦界」であったのには違いないのですから……。そこで生まれ育った蔦重は、文化の香りも存分に吸収したでしょうが、吉原の暗い面からも多くのことを学んだはずです。
吉原には、遊女に夢中の男たちが江戸中から集まってきて、たくさん金を落としていきました。何よりもまず「金儲けができる場所」だったわけです。生き馬の目を抜くような連中が金儲けの腕を競う〝戦場〞でもあった。蔦重はそこでのやりとりをずっと観察し、自分も商売に関わることで、「人の心を動かし、金を使わせるテクニック」を磨き上げたのでしょう。それが彼をのちにヒットメーカーたらしめた要因だったと、私は思います。
加来 蔦重が面白いのは、吉原にどっぷり浸かるのではなく、さりとて吉原から出ていくのでもなく、その真ん中でとどまったという点です。「耕書堂」を最初に開店した場所も、吉原大門(吉原への入り口)の並びでしたしね。
吉原に首まで浸かっていたら、「忘八者」(「仁義礼智忠信孝悌の8つの徳を忘れた無法者」の意。遊女を仕切る側の人間がこう呼ばれた)のやくざな世界で生きたでしょう。しかし、蔦重はそうはならず、吉原にとどまりながらも、出版というまっとうな世界で生きた。その点に、彼がヒットメーカーとなった一因があると思います。つまり、吉原と一般世間を結ぶ仲介者だったことこそ、彼の強みだったのです。
髙橋 そうですね。蔦重が放った最初のベストセラーが、『吉原細見』(吉原のガイドブック)であったことは象徴的です。吉原で生まれ育ったことで身につけてきた知識と人脈を、すべて出版の世界で生かしました。それは彼にしかできないことだったのだと私は思います。
チャンスは準備していた者にしかつかめない
加来 私は、蔦重という人は時代に恵まれた面があると思っています。江戸の泰平が長く続き、町人文化が花開いた時代に生まれましたし、元々江戸の町人の識字率は高かったので、出版界が発展する土壌ができていました。
構成 本誌編集長 前原政之
撮影 鷹野 晃
本記事は、月刊『理念と経営』2025年4月号「巻頭対談」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






