『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第119回/『クリティカル・ビジネス・パラダイム――社会運動とビジネスの交わるところ』
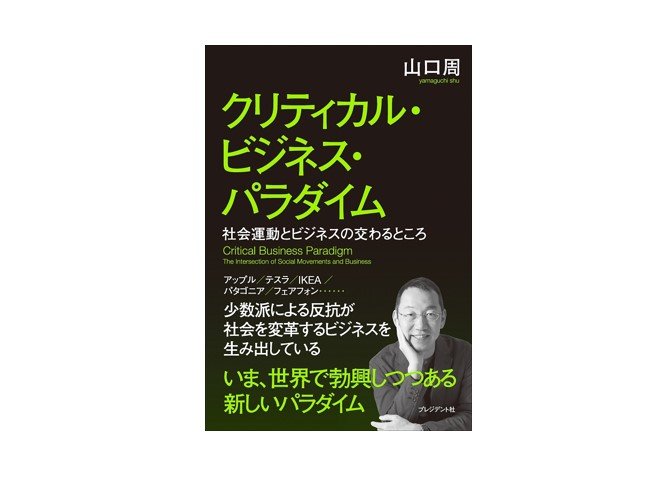
経営を「思想・哲学」として捉える論客
山口周氏といえば、経営・ビジネスに関する先鋭的な著作を数多くものしている人気著者です。
氏の数多い著作のうち、最もよく知られたものは、累計26万部突破(電子書籍版と併せて)のロングセラーになっている『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?――経営における「アート」と「サイエンス」』(光文社新書/2017年刊)でしょうか。
同書は、ビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)に輝くなど、その内容も高く評価されました。
山口氏には『理念と経営』でも、2019年8月号の特集《いま求められる未来を見通す力――リーダーの「教養」》にご登場いただいたことがあります。そのときは私が取材・構成を担当しました。
私はかねてより、山口氏の著作の大ファンでもあります。
氏はメディアに登場する際、「独立研究者・著作家・パブリックスピーカー」という肩書を主に用いていますが、私にとって氏のイメージは何よりも「経営思想家」です。経営を、単なる戦略や金儲けの次元ではなく、「思想・哲学」として捉える論客――。そのような立ち位置から生み出された著作は、実に斬新で卓抜、魅力的です。
今回紹介する近著『クリティカル・ビジネス・パラダイム』もしかり。
ビジネスの最前線で起きている一大画期を鮮やかに鳥瞰した1冊であり、新たな経営思想を提示する書でもあります。
「クリティカル・ビジネス」とは何か?
書名の「クリティカル・ビジネス」とは聞き慣れない言葉ですが、これは《社会運動・社会批判としての側面を強く持つビジネス》を意味します。
英語の「クリティカル(critical)」には「批判的な」「危機的・致命的な」などの意味がありますが、ここでは「批判的な」というニュアンスで用いられているわけです。
つまり、「クリティカル・ビジネス」とは、従来のビジネスのありようとは根本的に異なる新たな潮流を指します。では、どのように異なるのでしょう?
本書は従来の「ビジネス」について、《顧客のニーズを満たす商品やサービスを提供し、収益を得る目的で行われる経済的な取引や活動のこと》と定義しています。
一方、「社会運動」については、《社会の変革や改善を目指し、一定の目標や価値観を共有する人々が組織的に行う活動や運動のこと》と定義されています。
そして、「ビジネス」の定義に当てはまらず、むしろ「社会運動」の定義に当てはまる企業が、近年になって世界的に脚光を浴びていることが指摘されます。
《今日の社会において、大きな存在感を放ち、優秀な人材を惹きつけ、顧客と長期的なエンゲージメントを形成するのに成功している企業の多くが、単に利益を追求するだけでなく、何らかの社会運動・社会批評としての側面を強く持っていることにも気づかされます》
そのような大企業の例として挙げられるのが、フェアフォン、テスラ、Google、Patagonia、アップル、Airbnbなど……。それらの企業はいずれも、従来のマーケティング理論では説明不可能な発展をしてきたことが指摘されます。
マーケティング理論では、ターゲット顧客の満たされていないウォンツやニーズを新たな方法で満たすことで、企業は市場に受け入れられ、発展していくものと考えられてきました。
ところが、例に挙げられた大企業はいずれも、市場にある顧客の不満・不安・不便を解消して成長したのではありません。むしろ、誰もが「そういうものだ」と受け入れていたシステムに対して、異なるあり方を示すことで、そこに新たな市場を作って成長したのです。
そのわかりやすい例として、テスラの成功が挙げられています。
テスラは2003年の創業時から、「化石燃料に依存する文明のあり方に終止符を打つ」という壮大なビジョンを掲げていた電気自動車メーカーです。
しかし創業当時、「環境に負荷をかけるガソリンエンジンの自動車には、もう乗りたくない」というニーズやウォンツがあったかといえば、ノーでしょう。ごく一部の人はそう思っていたかもしれませんが、大多数の人は「ガソリンエンジンを使い続ける未来」を、「そういうものだ」と受け入れていました。
テスラはそうした社会に向けてクリティカルな(批判的な)あり方を示し、そこに新たな市場(=新たな問題)を生み出して成功したのです。
そして、そのような《古典的な経営学やマーケティングのパラダイムでは説明のつかない成功事例の頻出は、いま、私たちの社会において大きなパラダイムシフトが進行している証左と考えることができます》と、山口氏は指摘します。
その「パラダイムシフト」(=考え方や価値観の劇的な転換)こそ、本書が1冊を費やして解説している「クリティカル・ビジネス・パラダイム」なのです。
「ソーシャル・ビジネス」との相違点
ここまでを読んで、「クリティカル・ビジネスって、従来のソーシャル・ビジネス(社会問題の解決を目的としたビジネス)と何が違うの?」と首をかしげた人もいるでしょう。
もっともな疑問です。山口氏も、本書で一項を割いて両者の違いを説明しています。
《ソーシャル・ビジネスもクリティカル・ビジネスも、何らかの社会的課題をアジェンダとして取り上げ、その解決を目指すという点では同じです。では何が違うのでしょう?
従来のソーシャル・ビジネスが、すでに多数派のコンセンサスが取れたアジェンダに対して取り組むのとは対照的に、クリティカル・ビジネスでは、運動を開始する時点では必ずしも多数派のコンセンサスが取れていないアジェンダについて取り組む、というのが大きな違いです》
典型例として、「SDGs」に設定された17個のアジェンダが挙げられます。それらは「人類の未来のために取り組むべきもの」として世界的コンセンサスが得られたものであり、企業としても参入しやすく、しかも参入することで称賛されます。
それに対して、クリティカル・ビジネスとは、参入時点ではごく少数の人にしか認識されておらず、市場すら存在しない課題に先駆的に取り組むものなのです。
先に挙げたテスラ、Patagonia、Airbnbなどの企業が世界的成功を収めたのは、その取り組みがクリティカル・ビジネスであったからこそと言えます。
なぜなら、いわゆる「SDGsビジネス」のような、すでにコンセンサスが得られた課題への取り組みは、世界中の企業がしのぎを削るレッドオーシャンに後発で参入することに他ならないから。
市場すら存在しないクリティカル・ビジネスに、高い参入障壁を越えて挑んでこそ、そこにはブルーオーシャンが広がり、巨大な先行者利益を得ることができるのです。
“経営の未来への羅針盤”として
《本書は「社会運動・社会批判としての側面を強く持つビジネス=クリティカル・ビジネス」を理解・実践する上でのガイドブックということになります》
「はじめに」にそうある通り、本書はクリティカル・ビジネスをさまざまな角度から解説する内容です。
「クリティカル・ビジネス・パラダイムとは何か?」という詳細な解説から始まり、クリティカル・ビジネスが勃興しつつある背景の分析あり、代表的事例の紹介あり……。
また、第6章《アクティビストのための10の弾丸》は、山口氏自身が行った国内外のクリティカル・ビジネスのアクティビスト(実践者)へのインタビューを踏まえた内容です。そこでは、彼らが共通して持っている独特の思考様式を浮き彫りにしています。
「社会変革の担い手は、昔もいまもこういう人たちなのだな」と、深い感慨を持って読みました。
そして、最後の第7章《今後のチャレンジ》では、経営者側のみならず、我々1人ひとりがクリティカル・ビジネスとどう向き合っていくべきかが論じられています。
社会をよい方向に変えていこうとするクリティカル・ビジネスは、ごく少数の賛同者から出発するだけに、大きな広がりを持つか否かは、受け入れる我々(一般消費者)の姿勢しだいです。
だからこそ、共感できるクリティカル・ビジネスに出合ったら、さまざまな面で応援していくことが大切だと、山口氏は言います。応援の7つの形が、この章で解説される《7つのチャレンジ》なのです。
何よりも大切な応援が、《クリティカル・ビジネスの製品やサービスの利用》であることは言うまでもありません。
《ビジネスには社会を変革する大きな力がありますが、その力が、社会を啓発して明るい方向に導くか、逆に愚民化して暗い方向に導くかは、ひとえに顧客である私たち市民の一人一人が、どのような見識・倫理観・美意識を持って、製品やサービスを選択するかにかかっています。
(中略)
この点で日本社会は大きく遅れをとっています。社会的・環境的・政治的な変化を起こすことを意図的に目指す消費行動を「消費アクティヴィズム」と言いますが、この消費アクティヴィズムの土壌が日本では非常に脆弱なのです》
消費行動も、ある意味では選挙で好ましい候補者に投票するのと同じで、“自らが望む社会のあり方を選択する行為”なのです。
本書は、経営観が変わるほどの心地よい衝撃を味わえる1冊ですが、同時に、消費行動についても深く考えさせられる内容と言えます。
これは、中小企業経営者が読んで、即「経営に役立つ」というたぐいの本ではありません。それでも、いわば“経営の未来への羅針盤”として、一読をおすすめします。
山口周著/プレジデント社/2024年4月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






