『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第118回/『小説 土佐堀川――広岡浅子の生涯』
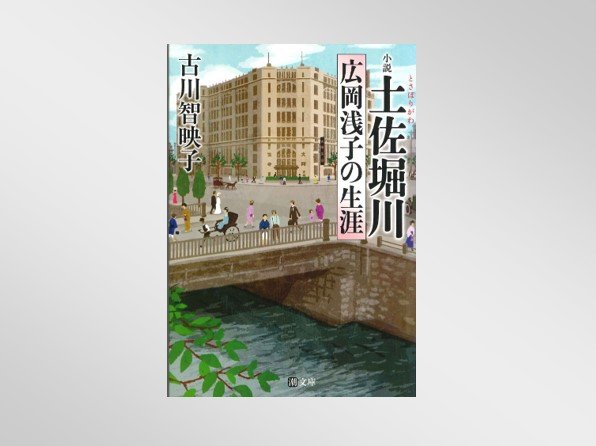
広岡浅子を知らしめる原動力になった作品
この連載は経営書・ビジネス書を主に扱いますが、時には歴史小説や経済小説も取り上げます。小説から経営が学べることも多いからです。
たとえば、直近では第86回で、門井慶喜氏の『文豪、社長になる』を取り上げました。文藝春秋の創業者でもある作家・菊池寛の伝記小説であり、経営者としても先見の明に満ちていたその生涯から、中小企業経営者が学ぶべき点も多いのです。
今回は、歴史小説家・古川智映子氏の代表作『小説 土佐堀川――広岡浅子の生涯』を取り上げます。「近代日本初の女性実業家」として知られる広岡浅子(1849~1919)の一代記です。
大阪の豪商・加島屋を切り盛りして維新後の難局を乗り越え、銀行を創立し、鉱山も経営し、晩年には大同生命を興し、日本女子大学の創立にも関わった……その生涯で浅子が成し遂げたことは、当時(幕末~大正期)の女性たちが置かれた社会的立場を考えれば、奇跡のような偉業と言えます。
しかし、古川氏が1988年に本作を上梓するまで、浅子は知る人ぞ知る存在でした。共通点も多い渋沢栄一などと比べ、知名度が低かったのです。
本作は刊行後、ラジオドラマ化・舞台化されるなど、一部で注目を浴びました。それでも、浅子の名が広く知れ渡るには、それから27年を経た2015年の朝ドラ(NHK「連続テレビ小説」)化を待たねばならなかったのです。
15年下半期の朝ドラ『あさが来た』は本作を原案としており、ヒロインは広岡浅子をモデルとした「白岡あさ」(演・波瑠)でした。『あさが来た』は平均視聴率23.5%と、21世紀の朝ドラでは最高の人気作に。また、ドラマ化に合わせて刊行された本作の文庫版も、55万部突破のベストセラーとなりました。
まさに、広岡浅子の名を日本中に知らしめる原動力となったのが、この『小説 土佐堀川』なのです。
ちなみに、タイトルの「土佐堀川」とは、大阪市北区中之島を流れる川。浅子が切り盛りした加島屋も、その河畔にありました。そこは彼女が長年暮らした場所でもあります。
手探りで進められた地道な取材・調査
『あさが来た』による広岡浅子ブームを経て、いまでは彼女を扱った一般書もたくさんあります。しかし、古川智映子氏が本作のための調査を始めたころ、浅子についての一般書は皆無に等しかったのです。
古川氏は、高群逸枝著『大日本女性人名辞書』(復刻版)の中にあった、浅子についてのたった14行の記述に心惹かれ、彼女の生涯を小説化したいと考えました。当時、その記述以外に資料らしい資料はなく、調査は手探りでした。
《大阪と京都に通い、加島屋本家の子孫や浅子のお孫さんの生存が分かり、聞き書きをすることができた。西宮市雲井町の広岡家にも伺い、写真を見せてもらったり、お話をうかがったりして小説の肉付けをふくらませて行った》(『小説 土佐堀川』文庫版あとがき)
小説というより、大部のノンフィクションをものすような地道で綿密な調査を経て、本作は完成したのです。
経営的観点からも学びが多い
浅子は、のちに三井財閥を形成する「三井十一家」の1つ「京都油小路三井家」(出水家)の令嬢として生まれました。江戸期を通じて日本有数の豪商であった三井家に流れる「商人の血」を、色濃く受け継いだのです。
17歳で大阪の両替商・加島屋に嫁ぎますが、夫・広岡信五郎は商売より茶の湯や芝居見物に明け暮れる趣味人でした。いきおい、加島屋の経営は少しずつ嫁の浅子頼りになっていったのです。
幕末から明治維新へと向かう激動の中で、加島屋は経営危機を迎えます。巨額の「大名貸し」(諸藩への融資)が維新で焦げ付き、幕府に「御用金」として供出した大金もほとんど戻らなかったからです。
そのとき、まだ20歳だった浅子が夫に代わって奮闘し、金策に駆け回るなどして危機を脱しました。大阪の両替商の多くが維新期に廃業の憂き目を見たなか、加島屋は生き残ったのです。そこから、浅子の経営者としての才覚が花開いていきます。
浅子による加島屋再興の道筋を辿ると、そこには、現代でも通用する優れた経営感覚が随所に見られます。そのことが示すように、この小説は経営的観点からも学びが多いのです。
たとえば、浅子は義兄・三井高喜から受けた次のようなアドバイスを、肝に銘じました。
「世の中の変わり目いうのは、商人にとっては恰好の舞台になるもんや。必ず新しい商いが出てくるわ。先への判断がつくかどうか、何というても情報集めが先決や」
そのアドバイスに従って、浅子は鉱山を買い、当時としてはきわめて先進的な炭鉱ビジネスにチャレンジしたのです。
しかも、福岡県飯塚市のその炭鉱を成功させるため、浅子は単身現場に乗り込み、荒くれ者揃いの坑夫たちの中に分け入り、真っ黒になって指揮を執りました。そうすることで、坑夫たちから信頼を勝ち取ったのです。
そのとき、彼女が護身用のピストルを懐中に忍ばせていたというエピソードは有名で、本作でも印象的に描かれています。
炭鉱ビジネス成功までのいきさつだけでも、いくつもの学びがあるでしょう。いち早く情報をつかみ、まだブルーオーシャンであるうちに新しいビジネスに打って出ること、経営者自らが現場に立つことなど……。それらの大切さは、現代の中小企業経営においても変わりません。
広岡浅子が語る「経営と商売の勘所」
その多くは作者の創作ではあるでしょうが、本作の要所要所で浅子が語る言葉は、経営と商売の勘所が見事に表現されたものです。いくつか例を挙げてみましょう。
「石炭掘るのは確かに加島屋のためや。けど、もっと大きく国益のためでもあるんや。日本の国の発展が皆の腕にかかってる」
――これは、炭鉱で坑夫たちに語りかける言葉。
「お金がお金を連れてくるのやない。人がお金を運んでくるのや。つまりお金連れてくる人間様に真心を尽くすしかない」
――これは、自ら創立した「加島銀行」の行員たちに言い聞かせる言葉。
「うちは商人やから、多少は損得も考える。金の損得やないで。得にも大きい利と小さな利があるのや(中略)
女子大学創立に走り回って、利益にならんと思うてる人も多い。しかし日本の国動かしてるような人にぎょうさん会うて、知り合いになることがでけた。大きな得したことになる。金では買えん財産や」
――これは、「日本女子大学」の創立に邁進していたころ、浅子が娘の亀子と井上秀(のちに日本女子大学初の女性校長になる)に熱く語る言葉。
「これからは自分が大きゅうなろう思て努めます。自分の幅広げた分だけ商いも大きゅうなりますのや」
――これは、浅子が渋沢栄一と面会し、アドバイスを受けたあとに語った結論。ただし、2人にはさまざまな接点があったものの、直接会見したことを示す史料はなく、この場面のやりとりは作者の創作です。
このような、経営に生かせる普遍的な金言がちりばめられた作品でもあり、浅子から経営の要諦を学ぶ思いで読むのも一興でしょう。
「九転十起」の精神で闘い抜いた
浅子の座右の銘は「九転十起」――「九転び十起き」でした。ことわざの「七転び八起き」より2回ずつ多いのは、彼女がそれほど多くの逆境を乗り越えてきたからにほかなりません。
浅子は若き日に、当時は恐るべき死病であった肺結核を病み、克服しています。また、のちには乳がんにもなり、末期に近かったものの、手術によって乗り越えました。
そうした病魔との闘いに加え、事業上の逆境は枚挙にいとまがありませんでした。一例として、経営する鉱山で爆発事故が起き、大きな危機を迎えたことがあります。
本作でも、そのときの場面が印象的に描かれています。そこで、浅子は幼い娘の亀子に次のように語りかけるのでした。
「亀子、加島屋の山は、事故に遭うてしもた。七転び八起きいう言葉があるけど、お母はんはな、九転び十起きやと思うて負けまへんで」
「社会のため」を忘れない経営者
そのように不屈の経営者であったことに加え、浅子は経営を通じて社会に貢献しようとする姿勢が一貫していました。
たとえば、浅子は晩年に女子教育にも力を入れます。日本で初めての女子大学となった日本女子大学の創立者・成瀬仁蔵を助け、創立に深く関わったのです。
浅子自身は、「女子に学問は不要」という三井家の古いしきたりのため、勉学の道をあきらめざるを得ませんでした。そして、結婚後に独学でさまざまなことを学び、経営者として必要な見識を得たのです。
その経験から、女子にも教育機会を与えることを日本社会の大きな課題と捉え、日本女子大学創立に力を貸したのでした。
また、浅子の実業家としての最後の挑戦は、大同生命の実質的創業者となったことでした。その背景にも、社会貢献への強い意志がありました。浅子は、保険事業こそ社会を救済し、人々の暮らしに安定や安心をもたらすものと考えたのです。
そして、保険事業拡大のため、元々経営していた朝日生命(現在の朝日生命とは別会社)と、護国生命、北海生命の合併を実現させ、大同生命を誕生させたのでした。その社名には、「小異を捨てて大同につく」との思いが込められていました。
いうまでもなく、浅子が創立に深く関わった日本女子大学と大同生命は、21世紀のいまも健在です。
目先の利益のみを追うのではなく、「社会のため」「日本の未来のため」を常に考えて事業に臨んだ浅子は、同時代を生きた渋沢栄一にも通じる、崇高な理想を掲げた経営者でした。
近代日本に輝く、不世出の女性実業家・広岡浅子――。その痛快な生涯を鮮やかに描いた本作は、現代の中小企業経営者にも深い感動をもたらすに違いありません。
古川智映子著/潮出版社/2015年9月刊(文庫版)
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






