『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第112回/『超進化経営――勝ち続ける企業の5つの型』
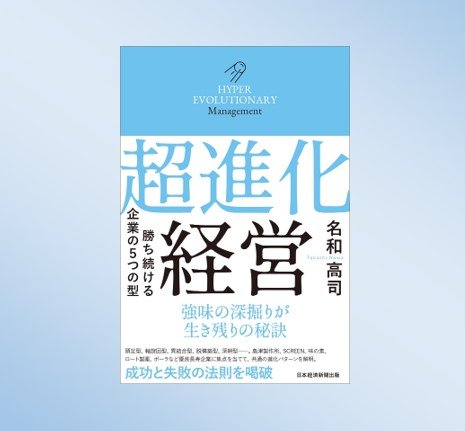
企業も「進化」するからこそ生き残る
いまや日本を代表する経営学者の1人と言ってよい名和高司先生(一橋大学ビジネススクール客員教授、京都先端科学大学教授)には、『理念と経営』の巻頭対談にしばしばご登場いただいています。
名和先生は著作活動も精力的に行っており、2021年刊の大著『パーパス経営――30年先の視点から現在を考える』(東洋経済新報社)は、日本の「パーパス経営」ブームを先導する書となりました。
今年(2024年)に限っても、今回取り上げる『超進化経営――勝ち続ける企業の5つの型』のみならず、新たな大著『エシックス経営――パーパスを経営現場に実装する』(東洋経済新報社)が、もうすぐ(9月18日)刊行されます。
この『超進化経営』については、実は『理念と経営』の巻頭対談の中で刊行が“予告”されていました。
というのも、名和先生とオイシックス・ラ・大地株式会社の高島宏平社長の対談(2023年8月号)の中で、先生はこう言われていたからです。
《私はいま、「進化経営」というテーマで本を書いています。企業は1つの場所にとどまっていてはダメで、進化し続けないといけないという内容です》
この巻頭対談は私が取材・構成したものなので、「その本を早く読みたい」と待ちわびていたのです。
生物が環境に適応して進化していくように、企業もまた、環境変化に応じて進化し続けるからこそ生き残っていけるものです。
生物の進化や絶滅は何万年という長いスパンの中で進みますが、企業の淘汰はもっとケタ違いにスパンが短いでしょう。企業の平均寿命は30年とも言われ、100年以上生き残る企業はまれなのですから……。
だからこそ、企業という「人工生命体」は、10年、20年という短いスパンで進化しなければ、生き残っていけません。先行き不透明で変化が激しい「VUCAの時代」であるいまは、なおさらでしょう。
「現状維持は衰退」とも言われるとおり、いまがうまくいっているからといって1つの場所にとどまっていたら、早晩「茹でガエル」化して淘汰されてしまいます。
日本の「超進化企業」トップ50社を検証
老舗企業は、時代の変化に応じて進化し続けてきたからこそ生き残ってこられたと考えられます。
じっさい、老舗企業の歴史を辿ってみれば、同じ商売を同じやり方でずっと続けてきた会社はごくまれです。老舗は、何らかの進化を遂げたからこそ生き残っているのです。
それゆえ、名和先生は本書で日本の老舗企業に着目しました。しかも、上場企業として高い業績を誇ってきた「強い老舗企業」に焦点を絞ったのです。
具体的には、企業の資産効率の評価指標として注目されている「PBR(Price Book-value Ratio:株価純資産倍率)」を、主な評価基準にしています。
日本にはPBR1倍割れ企業が半数近く存在する一方で、PBR2倍を超える長寿企業も少なくありません。名和先生はそのような優良大企業を、さらに独自のフィルターにかけ、「超進化企業トップ50社」としてランキングしました。
島津製作所、SCREEN、味の素、ロート製薬、ポーラなどが、その中に含まれます。50社中18社は創立100年を超える長寿企業であり、それ以外にも、ポーラ(1929年創業)のような準100年企業が多いのです。
《これらの企業は、「寿命30年」の壁を越えて、進化している。この通説が正しいとすれば、100年以上続く長寿企業は、3回以上、進化を繰り返してきた勘定になる》
本書は、日本を代表する超進化企業50社を俎上に載せ、進化のパターンを5つに類型化。そのうえで、各類型の「失敗と成功の法則」を抽出しています。
超進化企業がどう進化してきたのかを知れば、自社を進化させて長寿企業を目指すための方途も見つかるでしょう。本書は、いわば「企業進化のロールモデル集」なのです。
企業進化の「5つの類型」とは?
本書で取り上げられた企業の、進化の「5つの類型」とは次のようなものです。
(1)頭足(オクト)型――タコに代表される頭足類のイメージであり、多角化した企業を指します。複数の事業(タコ足)の太さを変え、時代に合わせて組み替えていきます。ただし、むやみに多角化すればよいわけではなく、新陳代謝に取り組む姿勢を重んじる類型です。
(2)軸旋回(ピボット)型――バスケットボールの「ピボット」のように、軸足に当たる事業を固定し、もう一方の足を動かしながら多角化を進める類型です。《環境変化と自らの成長に合わせて、本業そのものを巧みにずらしていく》特徴を持っています。
(3)異結合(クロス)型――異質な事業を掛け合わせる(クロス)ことで、新たな価値を創出する類型。《自社の中で異結合を誘発させるイノベーション企業》です。
(4)脱構築(デコン)型――《生命の世界における「突然変異」に近い》、《非連続な進化を目指す》類型です。典型例はリクルートで、創業時の求人広告企業から、広範な人財事業を手がける大企業に進化しました。
(5)深耕(カルト)型――「一意専心」で自社の足元を深掘りし続ける企業で、一見すると同じところにとどまって進化していないようにも見えます。しかし、「深化」を極めることが「進化」につながっていくという類型なのです。
――これらの短い解説だけでは、各類型の違いがピンとこないかもしれません。
しかし、本書は5類型を1~5章の各章でじっくり解説しています。その中では各類型に当たる企業が例として挙げられ、進化の中身が具体的に説明されます。各章を読めば、副題に言う「勝ち続ける企業の5つの型」がよく理解できるでしょう。
日本の長寿企業にこそ進化を学ぶべき
本書の中で、名和先生はくり返し、日本企業が欧米で流行の経営理論を付け焼刃で取り入れる愚かしさを指摘しています。
《欧米流の経営論を後追いするのは、そろそろ終わりにしたいものだ》と言い、欧米の経営理論をありがたがる姿を「舶来病」と呼んで批判しているのです。
「パーパス経営」ブームの火付け役となった名和先生の言葉だからこそ、そうした批判には説得力があります。先生は「パーパス経営」ブームについても、パーパスを表層だけ取り入れて内実が伴わない「額縁パーパス」に陥っている企業が多いと憂えているのです。
《本書では、100年を超えてなお進化を続ける企業に焦点を当てた。これらの企業は、長い歴史のなかで、その企業ならではの「伝統」を蓄積し、継承し続けている。一方で、その伝統の単なる踏襲に終わらず、それを大きく革新させる力をもっている。だからこそ、「企業の寿命30年」という定説を破って、次世代に向けて進化し続けているのである》
周知のとおり、日本は世界に冠たる長寿企業大国です。本書にも次のようなデータが挙げられています。
《・創業100年以上の日本企業は3万3076社で、世界トップ。世界の100年企業全体に占める割合は41・3%。
・創業200年になるとその傾向はさらに高まり、企業数は1340社で日本がトップ。世界の創業200年を超える企業全体に占める割合は65%》
長寿企業の圧倒的な多さは、進化を重ねてきた企業が日本に多いことを示しています。だからこそ、欧米の経営理論に飛びつくよりも、日本の長寿企業にこそ進化の方法論を学ぶべきなのです。
本書に登場するのは名だたる大企業ばかりですが、中小企業にとっても、自社を進化させるヒントがちりばめられています。
ここに詳しく解説された「企業進化の5類型」のうち、自社はどれを目指すべきかをじっくり考えてみるのもよいでしょう。
名和高司著/日本経済新聞出版/2024年3月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






