『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第109回/『努力は仕組み化できる――自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学』
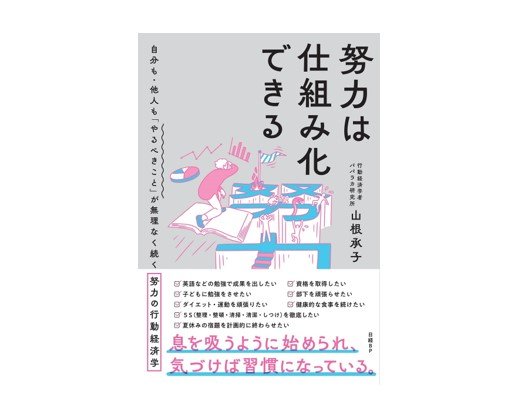
「努力の仕組み化」をずっと考えてきた人
今回取り上げる本は、いつもとは違い、ストレートな「経営書」ではありません。ただし、間違いなく「経営に(も)役立つ」内容です。
タイトルの通り、『努力は仕組み化できる』としたら……。経営者なら、まず社員たちが仕事に向ける努力を「仕組み化」したいと考えるでしょう。
また、自らの生活にも「仕組み化」を取り入れ、楽しく努力できるようになりたいとも思うはずです。
いずれにせよ、経営にも活かせる知恵が満載の1冊と言えます。
著者の山根承子氏は行動経済学の研究者で、近畿大学経済学部准教授などを経て、2020年より「株式会社パパラカ研究所」の代表取締役を務めています。同社は、企業や自治体向けに行動経済学の知見を用いてコンサルティングを行う法人です。
《この仕事では、本当に様々な業種の方からご相談をいただくのですが、実は「このような行動を継続させたいのだが、どうすればいいか」というような相談は非常に多いです。
継続させたい行動は、健康的な食生活だったり、運動だったり、省エネだったり、消費だったり、サービスの利用だったりと様々で、継続させたい対象は従業員、顧客、消費者、場合によっては会社の上層部などと、本当に多種多様です》(本書「はじめに」)
自分や他者に、望ましい行動を継続させる方法――それはまさに「努力の仕組み化」に他なりません。仕事を通じてその仕組み化をずっと考えてきたのが、著者の山根氏なのです。
行動経済学の視点から「努力を科学する」
ではなぜ、行動経済学の研究が「努力の仕組み化」に役立つのでしょう?
行動経済学は、大雑把に言えば、経済学に心理学を取り入れた学問です。それまでの経済学は人間の心理的側面に深く立ち入らず、「人間は常に経済合理性に沿った行動をするはずだ」という前提に立って研究を進めていました。
しかし、人間は本来、それほど単純な存在ではありません。さまざまな感情に揺さぶられて、時には経済的に不合理な行動(=自分にとって損な行動)を取ることもあります。そのような、心理学が探求してきた人間の複雑さを取り入れ、経済学をアップデートしたのが行動経済学なのです。
また、行動経済学と「努力の仕組み化」の関係については、著者の山根氏自身が次のように説明しています。
《「努力」にまつわる様々な葛藤は、どれも理性と衝動のせめぎ合いから生まれているように見えます。(中略)
本書では、そんな「努力」というものを「行動経済学的視点」で分解していきます。なぜ「行動経済学」なのでしょうか?
それは、行動経済学がまさに、理性と衝動を興味深く見つめてきた学問だからです。(中略)「人間が合理的であるならば、どのように振る舞うか(理性)」と「実際の人間がどのように意思決定し、どんな行動を取るのか(衝動)」の両方、そして両者のズレを生むものについて、多くの研究が行われてきているのです》
行動経済学にはそのような特徴があるからこそ、理性と衝動の間で揺れる「努力」をコントロールするための知恵に満ちています。
その知恵を駆使して、根性論・精神論で語られがちだった「努力」に科学のメスを入れたのが、本書なのです。
「ラクに努力できるようになる」ために
本書は行動経済学だけではなく、さまざまな分野における努力の研究も踏まえています。
《「努力」に関連する様々な話題は、行動経済学だけではなく、心理学や教育学、栄養学、建築学など、多種多様な分野で研究されています。(中略)
本書では行動経済学に限らず、これらの関連領域の研究も紹介していくことで、「努力」を広く、かつ深く理解していきます》
それらの研究成果が随所でエビデンスとして紹介されますが、それでも本書はすこぶるわかりやすく書かれています。論文臭は皆無で、科学的な素養がなくても問題なく理解できるのです。
《「努力できるかどうかは才能なのか」。 これは本書を通して考えていく問いですが、答えをここに書いておきましょう。
確かに才能で決まる部分はあります。しかし、仕組みでどうにかなる部分も大いにあります。
この本では、努力の仕組みを知ることで、皆さんが今よりラクに努力できるようになることを目指します》
「はじめに」にそうあるように、本書はあくまでも実用書であり、「ラクに努力できるようになる」ためのノウハウが山盛りなのです。
たくさん紹介されているノウハウの1つを紹介してみましょう。
努力の継続に効果的なのはそれを習慣化することですが、そのためのテクニックとして「実行意図」の活用が挙げられています。
「実行意図」とは《「どこで、いつ、どのように行うか」をあらかじめ決めておくこと》を言い、それがあったほうが努力が習慣化しやすいそうです。
《例えば、「今週の平日5日のうち4日は、会社帰りにジムに行こう」と決めれば、「できるだけジムに行こう」と漠然と思っているよりも、努力を継続できる可能性が上がるということです。より具体的に「火曜日と金曜日の会社帰りはジムに行こう」だと、さらに効果があるでしょう》
このように、生活に取り入れやすいノウハウが多数紹介されています。しかも、それらがなぜ効果的なのかを示すエビデンスも紹介されるため、納得して取り組むことができるのです。
“努力をめぐる面白エピソード集”としても楽しい
本書は「日経BOOKプラス」のウェブサイト連載がベースになっています。連載中、著者は読者から「努力についてこんなに考えてる人、見たことない」と言われたとか(本書「おわりに」)。その言葉の通り、努力について考える視点が一通り網羅されている印象です。
だからこそ、実用書ではありますが、「読み物」としても楽しめます。“努力をめぐる面白エピソード集・努力の雑学集”としても読める内容になっているからです。
面白エピソードの1つを紹介しておきましょう。
《英語圏には、「新しい習慣を身につけるには 21 日かかる」という俗説があるそうです。そして面白いことに、これが本当なのかどうかを確かめた研究があります》
《様々な行動が自動化されるまでの日数を見ていくと、18 日で自動化される行動もあれば254日(約8カ月)かかる行動もありましたが、中央値は 66 日となっていました。つまり、どんなことでも2カ月頑張ることができれば、その努力は意識せずとも自然に行えるようになっている可能性が高いのです》
これなどは、思わず人に教えたくなる“耳よりな話”でしょう。
経営者が肝に銘じるべき言葉も……
本書はとくに経営者向けというわけではないものの、著者が企業へのコンサルティングを幅広く行っていることもあり、経営者にとって有益な知見も随所で紹介されています。
たとえば、第11章では「努力の弊害」が論じられますが、そこではいわゆる「サンクコスト(埋没費用)」がもたらす不毛な努力が、企業経営にからめて語られています。
《サンクコストの「コスト」には、お金だけではなく、時間や労力も含まれます。長い時間をかけて努力したことは「せっかくずっと頑張ってきたしな」という思いを生み、それが最適な行動を邪魔してしまうこともあります。「努力した」という事実が、よくない選択に導いてしまう可能性 があるということです》
《サンクコストはビジネスにも大きな影響を及ぼします。
あなたは会社で、ある新型のスポーツシューズをずっと開発しているとします。ある日突然、ライバルメーカーが同種の、そしてより高機能のシューズを発売して話題になりました。あなたはこのシューズの開発を継続すべきでしょうか。
このような、プロジェクトの継続と撤退を考える場面において、サンクコストは目を曇らせるので非常に危険です》
まさに経営者が肝に銘じるべき言葉でしょう。このように、行動経済学の知見を経営に活かせる事例が、本書にはちりばめられているのです。
山根承子著/日経BP/2024年8月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






