『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第107回/『Think CIVILITY(シンク・シビリティ)――「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である』
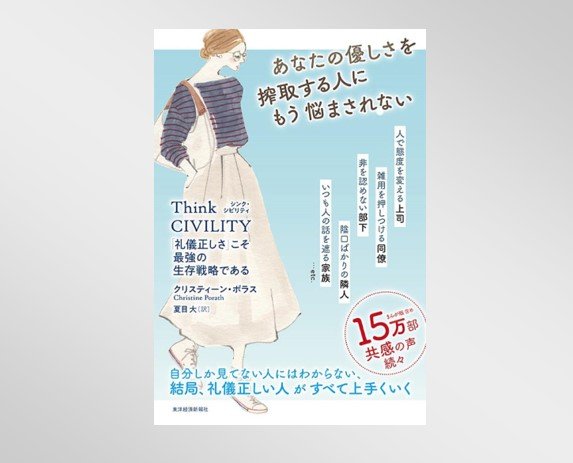
「礼儀正しさ」の価値に科学のメスを入れる
当連載では基本的に新刊・近刊を取り上げていますが、たまに旧著を紹介することもあります。今回取り上げる『Think CIVILITY(シンク・シビリティ)』がそのケースで、邦訳は2019年に刊行されたものです(原著は2016年刊)。
本書は日本でもロングセラーとなっており、マンガ版(2020年刊の『まんがでわかる Think CIVILITY』)と合わせて15万部を突破しています。
昨年(2023年)にはカバーデザインが刷新され、上に掲げたようなフェミニンなイラストカバーになりました。元のシンプルなデザインのカバーで記憶している人も多いでしょう。
本書は「礼儀正しさ」を称揚した本ではあるものの、よくある「マナー本」とは根本的に異なります。内容は、「礼儀正しさ(CIVILITY)の科学」ともいうべきものなのです。
他者に対して礼儀正しくふるまうことが大切なのはあたりまえですが、本書はそこに科学のメスを入れます。“そもそも、礼儀正しさはなぜ大切なのか?”を改めて問い、その価値を科学的に探求した本なのです。
そのような本が日本でロングセラーになっているのは、納得がいきます。日本こそ世界に冠たる「礼節の国」であり、礼儀正しさという価値を重んじる国民性を持っているからです。じっさい、本書には次のような一節もあります。
《日本で地下鉄に乗る時は、プラットフォームで列を作って待ち、列車が来たら、ドアの脇に立って、降りる人がいなくなるまで待つのが礼儀とされている》
我々にはあたりまえのことが、海外から見ると“驚くべき礼儀正しさ”として映るのです。
しかし、「礼節の国」である日本でさえ、無礼な人は少なくないものです。職場や仕事先で、無礼な言動をする上司や同僚、部下、顧客などに悩まされている人は多いでしょう。
本書によれば、過去20年ほどにわたって、世界的に《礼節は悪化し続けて》おり、無礼な人は増加傾向にあるとのことです。
著者はその要因として、グローバル化の進展(=国によって礼節の基準は異なるため、海外の人を無礼と感じやすい)、世代の違い、職場環境とそこでの人間関係の変化などを挙げています。
言い換えれば、無礼な他者に悩まされる人も、世界的に増加傾向にあるわけです。
無礼な人たちにどう対処すべきなのかも、本書には詳述されています。全4部構成の第4部は、丸ごと《無礼な人に狙われた場合の対処法》に充てられているのです。
「職場の無礼」は企業にとって大きな害悪
著者のクリスティーン・ポラス氏は、米ジョージタウン大学マクドノー・スクール・オブ・ビジネスの准教授。
彼女は、《愛する父が長年にわたって、無礼な上司に苦しめられる姿を見たこと》や、自身が会社員時代に無礼な人に悩んだ経験から、《「職場の無礼」を研究することに人生を捧げることを決めた》そうです。
そして、《過去20年にわたって、世界中の何万、何十万という人を対象に調査を実施してきた》という「職場の無礼」研究を踏まえ、長年の成果を一般向けにまとめたのが本書なのです。
職場に無礼な人が1人でもいれば、周囲を嫌な気分にし、仕事に対する意欲を削ぎます。それは誰しも知っているあたりまえの話ですが、本書は“無礼な人が撒き散らす害悪”を、綿密な調査・分析によって、さまざまな角度から数値化・データ化して読者に提示します。
例をいくつか挙げてみましょう。
《無礼な態度は人の健康にも大きな悪影響をおよぼすことが、最近の科学的研究によって明らかになってきた。
まず、無礼な態度は、人の免疫システムを害することがある。そのせいで循環器系の病気、ガン、糖尿病、潰瘍などにかかる恐れがある》
《職場に友好的でない人がいると、死亡リスクが高まることもわかった。たとえば、中年と呼べる年齢の会社員の場合、同僚が友好的でない人は、友好的な人に比べ調査期間だけで約2・4 倍の人数が死亡している》
そのような健康被害は、無礼な人が撒き散らす害悪の一部でしかありません。
《アメリカ心理学会(APA)の試算によれば、職場のストレスによってアメリカ経済にかかるコストは1年に5000億ドルにものぼるという。なんと仕事上のストレスが原因で毎年5500億日もの就業日が失われ、職場で発生する事故の60~80パーセントはストレスが原因で、アメリカ人の通院の約80パーセント以上がストレスに関係しているとも言われる》
無礼な人は会社に有形無形の損害をもたらし、社員たちの集中力や生産性も下げます。また、離職の原因にもしばしばなるでしょう。
さらに、《中の誰かが誰かをひどく叱責するだけで、その企業に対する印象は極端に悪化する。事情はどうであれ、無礼な態度を見てしまうと、顧客はその企業に悪い印象を抱くことになる》とある通り、企業の対外的イメージも大きく毀損します。
《人、企業が無礼な態度によって被る損失は、一般に思われているよりはるかに大きい》ことが、本書で詳細に解説されているのです。
礼儀正しさを高めることは、コストゼロの社内改革
“無礼さのもたらすコスト”を可視化したうえで、著者は次に、礼儀正しさが個人や企業にどれほど多くのメリットをもたらすかを、データを踏まえて解説します。
第3章は《礼節がもたらす5つのメリット》と題され、《礼節ある人が得られる3つのメリット》と《礼節ある企業が得られる2つのメリット》が挙げられていくのです。
無礼さの害悪が想像以上に深刻であるように、礼節がもたらすメリットも想像を超えて大きいことが、この章を読むとよくわかるでしょう。
そして、経営者や社員の礼儀正しさを高めることは、基本的にコストゼロでできます。礼節を教えるプロのコーチを招聘するといったケースを除けば、各自の心構えだけでできる改革なのです。
だからこそ、資金的リソースが乏しい中小企業では、本書を参考に、礼儀正しさを高める改革に取り組むべきでしょう。
そのための方法は、第2部《あなたの礼節を高めるメソッド》や第3部《礼節ある会社になる4つのステップ》で、詳しく解説されています。
経営者は、有能さよりも温かさを印象づけるべき
本書に紹介された「礼節を高める」方法は、どれをとっても難しいことではありません。笑顔を絶やさないこと、感謝の気持ちを言葉にして伝えること、相手の話を傾聴する姿勢を保つことなど、「あたりまえ」のことばかりに見えます。
しかし、凡事徹底であたりまえの努力を積み重ねることが、個人、ひいては企業の印象を大きく変えることが、本書を読むとよくわかるのです。
たとえば、笑顔の大切さを解説した部分には、次のような一節があります。
《ひとつ目の基本動作は、「笑顔」ということだ。簡単だと思うかもしれないが、おそらく読者のほとんどは自分で思っているほど日常生活で微笑んでいない。これは断言できる。
(中略)
子供は平均して、1日に400回くらい笑うとも言われる。
だが、大人になると、その回数は激減する。笑う回数が1日に20回を超える大人は全体の30パーセントほどだ。1日にたった5回も笑わない大人が14パーセントもいる》
私たちは、他者に対してもっと微笑みかけるべきなのです。その心がけは、他者に与える印象をよくするのみならず、自身の心にもよい影響を与えます。
《やり直しのきかないことに挑む前の緊張した状態の時にも、楽しくなることを思い出して笑顔になると、良い結果につながることが多い(たとえば、ステージに上がって何かをする時、大勢の前で話をする時、面接に臨む時、など)》
また、経営者が社員に「温かい人だ」という印象を与えることがどれほど大切かが、データに基づいて指摘されています。
《あなたが会社で管理職やチームリーダーを務めているのなら、部下やメンバーと良好な関係を築くには、まず温かい人になるべきだ。そういう場合、どうしても自分が有能であることを早く証明したいという気持ちに駆られる人が多い。
しかし、一度、温かい人だと感じると、その人に対する評価は上がりやすくなる。温かい人になることは、自分の影響力を高めるための早道ということだ。温かい人は信頼を得やすい。信頼が得られると、自然に周囲から情報やアイデアが多く集まってくる》
「温かい人だという印象を社員に与えるなんて、簡単にできることではないだろう」と思う向きもあるかもしれません。しかし、人が他者を「温かい人」だと判断するのに要する時間は、ほんの一瞬であることが本書で指摘されています。
《プリンストン大学のアレクサンダー・トドロフ教授らは、人が他人の顔を見て相手について瞬時に判断を下す際、その背後で認知機構や神経機構がどのようにはたらいているかを調査した。
その調査でわかったのは、人間が一貫して、まず相手がどれほど有能かより、どのくらい温かいかを知ろうとするということだ。相手が温かいかどうかの判断を下すのに要する時間は、わずか33ミリ秒という短さだ。
相手が温かさに欠ける人だということ、無礼な人だということを人間は本当に一瞬の間に感じ取るし、一度、そういう判断を下すと、その人を簡単には許さない。たとえ、その人が有能であるとすぐあとにわかっても、「温かくない」ということの方を本質だとみなしてしまう》
社員に対する微笑みかけや言葉かけ、その積み重ねがどれほど大切であるかを思い知らされます。《些細なふるまいに気をつけるだけで周囲の反応や評価が変わる》ものなのです。
礼儀正しさを、自社の企業文化にまで高めよう
本書によれば、無礼さも礼儀正しさも、人から人へと伝染して広がりやすいそうです。
《無礼な言動の悪影響は短時間のうちに広がるし、影響はその言動のあとも長く残ることになる。しかし、礼儀正しい言動にも同じことが言える》
《良い態度も悪い態度も、その影響はまったく同じように広がる。つき合いの中にちょっとした優しさ、ちょっとした無礼があると、その人たちが属する組織、集団の中にさざ波のように広がっていく。同じネットワーク内にいる人ならば、その態度を取った人に直接関わらない人たちも影響を受けるということだ》
1人の社員の無礼さ、もしくは礼儀正しさは、他の社員たちも染め上げ、組織全体の雰囲気を変えていくのです。とくに、経営者のふるまいは、一社員よりもはるかに強い影響力を持つでしょう。
だからこそ、中小企業経営者は、言葉や態度、表情の一つひとつに気を配り、自分が礼儀正しく温かい人間であることを印象づける努力をすべきなのです。
その努力の積み重ねは、時には大規模な設備投資以上に、会社をよい方向に変える力となるでしょう。
そして経営者は、自分の会社が礼儀正しさという価値を重んじていることを、社員たちにくり返し伝えていくべきです。そのための工夫についても、本書には挙げられています。
《経営理念として、たとえば「当社の社員は、常に敬意をもって互いに接する」という簡単な文言を入れるだけでも、礼節を重んじるのだという姿勢を示すことができる》
《新しい社員が入ってきたら、オリエンテーションの段階から礼節の重要性を強調して伝える。マントラを唱えるように繰り返し同じことを言い続ける。会議の度に礼節の話をするのもいいだろう。社員全員が当たり前のように礼節を身に付けられるような環境を作るのが理想だ》
そうした地道な積み重ねによって、礼儀正しさを自社の企業文化にまで高めていきましょう。本書の副題に言う通り、それは中小企業にとっても《最強の生存戦略》になり得るのです。
クリスティーン・ポラス著、夏目大訳/東洋経済新報社/2019年6月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






