『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第100回/『こうして顧客は去っていく』
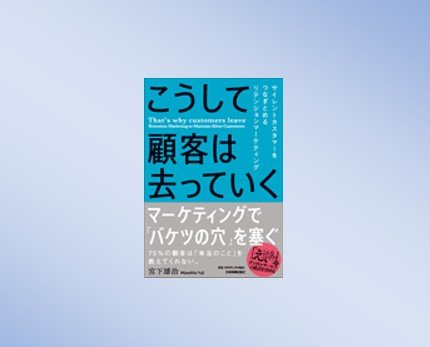
去っていく顧客をつなぎとめるために
経営者はとかく、新規顧客の獲得にばかり目が向きがちです。逆に、「既存顧客をいかにつなぎとめるか」にはあまり目が向かないケースが多いのではないでしょうか?
それはビジネス書・経営書についても言えることで、顧客獲得をテーマにした本が多いのに対し、顧客離脱をテーマにした本は少ない傾向があります。
今回取り上げる『こうして顧客は去っていく』は、タイトルのとおり、顧客離脱を食い止めるための方策についての経営書です。
サブタイトルに「サイレントカスタマーをつなぎとめるリテンションマーケティング」とありますが、「リテンション=retention」とは「維持・保持」の意で、マーケティング分野では「既存顧客の維持」という意味で用いられます。
著者の宮下雄治氏は國學院大學経済学部の教授で、リテンションマーケティングとデジタルを活用したマーケティングを主な研究領域とされている方。まさにその専門分野の知見を、一般向けにブレイクダウンしたのが本書なのです。
なぜいま、新規顧客獲得ではなく、顧客離脱とその防止についての本を世に問うたのでしょうか? その背景にあるのは、新規顧客の獲得が困難な時代にさしかかっているということです。
高度成長期であれば、日本経済そのものが右肩上がりであり、あらゆるモノがよく売れました。人口も多く、新規顧客は陸続と現れたので、既存顧客の維持にあまり注力する必要はなかったのです。
しかしいまや、日本社会そのものが成熟期に入り、平均的な家庭にはもうあらゆるモノが揃っている時代です。加えて、世界一のスピードで進む少子高齢化によって、市場そのものがシュリンクを続けています。
また、SNSの発達などもあり、消費者の目が昔より肥えているため、企業側が広告を打っても、それを鵜呑みにして買ってくれる人は少なくなっています。
そのような変化によって、昔に比べて新規顧客獲得が難しい時代になったのです。
本書にも、次のような一節があります。
《今日の多くの産業は、大きな成長が期待できない成熟期ないしは衰退期の段階に入っています。(中略)
市場の成長期と成熟期のいちばんの違いが、新規顧客獲得のハードルの高さです。事業の拡大において、新規顧客獲得の重要性は成熟期でも変わることはありませんが、成熟期ではそのハードルは一段と高くなります》
そうした時代だからこそ、リテンションマーケティングの重要性が増しています。本書は時宜を得た刊行と言えるでしょう。
既存顧客維持のコストは新規顧客獲得の5分の1
新規顧客獲得が昔より難しくなったことで、「顧客の離脱をいかに最小限に食い止めるか」こそがマーケティングの重点課題となったと、著者は言います。そしてそのことを、《「穴の開いたバケツ」に水を注ぎ続けても、水はたまらない――》という言葉で表現するのです。
本書は、「バケツに開いた穴」(=顧客離脱が多いこと)を最小限にしていく知恵について解説したものと言えます。顧客離脱はゼロにはできませんが、努力と工夫しだいで減らすことはできるのです。
そして、新規顧客獲得と既存顧客維持を比べた場合、後者のほうがはるかに労力が少なくて済むことが、次のように解説されています。
《マーケティングでよく知られた法則の1つに、「1対5の法則」があります。これは、新規顧客を獲得するためのコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるというものです。そのため、同じ価格の商品やサービスを新規顧客へ販売するよりも、既存顧客へ販売する方が企業は多くの利益を獲得することができるのです》
ローコストで利益が得られるという点でも、企業はリテンションマーケティングに力を入れるべきなのです。
顧客離脱の10パターンを詳細に解説
そして本書では、著者の研究の蓄積を踏まえ、顧客が企業から離れていく離脱の要因が詳しく分析されています。
第2章《顧客離脱の実態をつかむ》では、概要が解説されます。また、第4章《解約率(チャーンレート)が上がる10大要因――顧客が離脱する「決め手」とは?》では、顧客離脱の要因が10のパターンに腑分けされ、1つひとつに詳細な解説が加えられていくのです。
それらの章を読むだけで、経営者は目からウロコが落ちるような驚きが味わえるでしょう。
たとえば第2章では、著者が行った調査を踏まえて、離脱する顧客の約半数は「不満がとくにない」という、ある意味で衝撃的な事実が明らかにされています。
私たちは、離脱していく顧客は「何らかの不満を抱えている」と、無意識のうちに想定しています。
もちろん、商品についての不満、スタッフの対応への不満など、具体的な不満が離脱の引き金になることは多いでしょう。しかし、半数程度の顧客は、これといった不満がないのに去っていくというのですから、怖い話です。
著者は、そのような「不満がないのに去っていく」ケースを「消極的離脱理由」と呼び、その内実を5つの類型に腑分けして分析しています。
たとえば、「とくに不満はないが、他社のサービスに魅力を感じたため」「とくに不満はないが、サービスのマンネリ化を感じたため」といった理由で去っていく顧客が一定の割合を占めているとし、それは「顧客の目が肥えて、サービス品質の優劣が見極めやすくなっている」ことの表れだと分析するのです。
また、顧客離脱の10パターンを解説した章を読んでも、いまどきの顧客が昔に比べて目が肥えていて手ごわいことが、総じて感じられます。
リテンションマーケティングのお手本集
本書は、リテンションマーケティングの入門書として読むこともできます。随所に専門用語も飛び出しますが、語り口が平明であるため論文臭はありません。
たとえば、こんな一節があります。
《事前に期待した水準を「期待水準」と呼び、実際に体験して感じた水準を「知覚水準」と呼びます。この期待水準と知覚水準との比較を通じて「顧客満足」は形成されることになります》
何となく「わかったつもり」でいた顧客満足の心理プロセスについて、本書を読むと、マーケティング研究の確かな知見から理解できるようになるでしょう。
また、本書には、有名企業が行っている顧客つなぎとめのための努力と工夫の例が、多数紹介されています。いわば、「リテンションマーケティングのお手本集」でもあるのです。
たとえば、総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を展開する株式会社ドン・キホーテは、同社のオリジナル商品について顧客がダメ出しをする専用サイト「マジボイス(旧・ダメ出しの殿堂)」を展開しており、そのサイトを通じて顧客の声を集めています。そして、その声を商品開発・改善・改良に活かしているのです。
著者はそのことを「サイレントカスタマー」(物言わぬ顧客=不満があっても口にしないまま去っていく顧客)対策の手本として捉え、次のように言います。
《(顧客が)企業に愛想をつかして黙って去っていく前に、満足していない理由を聞き出す機会をつくり出すことが大切です》
《同社が顧客の声を真摯に受けとめ、パッケージから内容物、味にいたるまで商品の改善・改良に反映していることを知っているからこそ(実際にダメ出しから生まれた新商品を同サイトで公開している)、顧客はサイレントカスタマーや、クレーマーにならずにいるのです》
これはほんの一例です。本書で取り上げられている例の多くは大企業ですが、中小企業経営者が読んでも大いに参考になるでしょう。
顧客に寄り添うことこそ、普遍的に重要
本書を読むと、「顧客」のイメージが時代の変化に応じて大きく変わりつつあることを痛感します。
しかし、どんなに時代が変わっても、顧客のことをよく知り、その要望に寄り添うことが、企業にとって何より重要であることは変わりません。
著者も次のように言います。
《顧客が求めていないことを特定することによってはじめて、顧客が本当に求めていること、期待していることをあきらかにすることができる》
《リテンションマーケティングとは、顧客を知らないことには始まらないということです。顧客1人ひとりへの理解を深め、それに応じたカスタマーサクセスをつくることがリテンションマーケティングの目指すところです》
顧客の離脱防止をテーマにしていることで、一見ユニークな内容に思えますが、じつは顧客満足の追求という経営の王道を追求した本なのです。
宮下雄治著/日本実業出版社/2024年2月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






