『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第99回/『世界の学術研究から読み解く職場に活かす心理学』
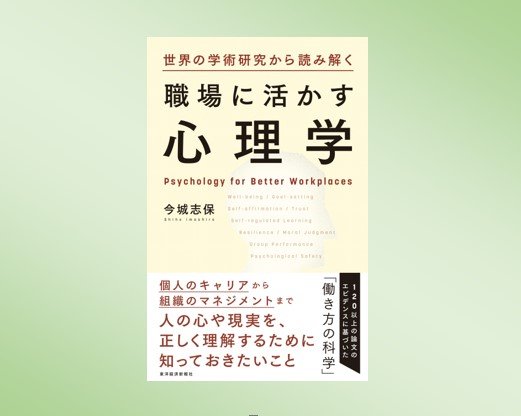
心理学研究と仕事の現場を結ぶ本
「心理学」という言葉を冠した一般書は、山ほど刊行されています。しかし、その手の本の中には、凡庸な自己啓発書に心理学の風味をまぶしただけの、いいかげんな内容のものも少なくありません。
そのような、いわば「俗流心理学」が幅をきかせる中にあって、本書は数少ない本格派と言えます。書名の通り、世界の心理学研究の最前線に目配りした上で、その研究を職場に活かす方途を探った1冊なのです。
著者の今城志保(いましろ・しほ)さんはニューヨーク大学で産業組織心理学を学び、東京大学で社会心理学の博士号を取得した研究者です。現在は、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所の主幹研究員を務めています。
リクルートマネジメントソリューションズは、人材系コンサルティングやトレーニングを提供する企業です。今城氏はそこで、アカデミックな研究のかたわら、心理学の知見を企業の現場に活かすための仕事を行っています。
まさに、心理学研究と現場の仕事を結ぶ役割を担ってきた方なのです。本書にもその経験の蓄積が十二分に活かされています。
《組織や職場で働く人の心理を扱っているものには、産業組織心理学という専門分野があります。(中略)ただし、産業組織心理学の研究の多くは、組織の視点から行われていて、どうすれば従業員のパフォーマンスが向上するかを問題意識の中心に置いています。
しかし、本書ではそうではなく、働く1人1人に心理学の知見を活用するヒントを与えることをめざします》(「はじめに」)
企業で働く個々人が直面する、働き方にまつわる問題解決のヒントを、心理学の最前線の中に探った本なのです。
本書の帯には、《120以上の論文のエビデンスに基づいた、「働き方の科学」》という惹句が躍っています。引用される120本以上の論文は、ほとんどが《世界のメジャーな学術誌に掲載され、引用数が100を超えているもの》なのです。
目標設定のコツから怒りの鎮め方まで
本書で扱われる、働き方を巡る問題は多岐にわたります。
たとえば、第1章第1節では、仕事を通じて幸福感を感じるためには何が大切なのかが、心理学研究から探られています。
1つの節ごとに、《心理学の研究成果》と《職場への応用ポイント》が箇条書きでまとめられており、この節では仕事を通じて幸福感を高めるためのポイントとして、次の3点が挙げられています。
《・幸福感が高いと、仕事のパフォーマンスは向上する。
・自ら意図して仕事に取り組むことで、仕事での幸福感が高まる。
・仕事の意義を再認識する場面を継続的に作ることで、仕事の幸福感を持続させる》
そのように、章ごと、節ごとにテーマが立てられ、著者はテーマに即した心理学研究を引用して、働き方の改善を考えていくのです。
ほかの章で取り上げられているテーマを、いくつか列挙してみましょう。
個人の目標設定と組織の目標設定の関係、ストレス耐性を強める「コントロール感」(環境への働きかけがうまくいくという感覚)の高め方、自己評価が甘くなる理由、行動変容(悪い習慣をやめるなど)の上手な促し方、プレッシャーに負けないためのポイント、「レジリエンス」(精神的回復力)を高めるコツ、職場の心理的安全性を損なわないための知恵、集団での仕事のパフォーマンスを向上させるポイント……。
ご覧のとおり、すぐに職場に活かせる知恵がたくさん詰め込まれているのです。そして、それらの知恵はいずれも心理学研究に基づいており、科学的エビデンスがあるので、読者の納得感も高いといえます。
たとえば、次のような一節があります。
《ネガティブな感情は、その感情にラベリングをすることでコントロールしやすくなるといわれてきました。たとえば、腹が立っているときに、「自分はとても腹を立てている」と自覚するといったことです。
なぜ感情のラベリングにこのような効果があるかは、従来はよくわかっていなかったのですが、近年の脳の神経画像を用いた研究では、ネガティブな刺激(怒りや恐怖の感情を表す表情の画像)を与えられた後に、感情にラベリングをすると、脳の感情反応が抑制されることが示されています》
「怒りは、その中身を書き出すことで抑制できる」とは、アンガーマネジメントの分野でよく言われることです。皆さんもきっと聞いたことがあるでしょう。しかし、そうした効果に科学的エビデンスが見つかったことは、まだあまり知られていないのではないでしょうか。
もう1つ例を挙げます。
私たちは仕事の大舞台(大切なプレゼンなど)に臨むときに強いプレッシャーを感じ、時にはそのプレッシャーのせいで失敗をしてしまいます。では、プレッシャーに負けないためのポイントを心理学研究から探すなら、どんなことが挙げられるでしょう? 本書には次のような指摘があります。
《大切なときや、本番や成功のプレッシャーがかかるときには、多くの場合、私たちは自分を強く意識すると考えられています。つまり、ある種の自意識過剰の状態になっているといえます。このような状態の心理的特徴を扱った理論にデュバルとウィックランドによる「客体的自覚理論」(Objective Self-Awareness Theory)があります。
この理論では、人が自分を対象として意識することで、どのような心理的影響が生じるかについて述べています。具体的には、人は自分を客観的に知覚すると、自分の望む姿とのギャップに気づかされ、その結果、怒りや失望、悲しみなどのネガティブな感情が喚起されるとしています。そして、その状態を回避しようとしたり、ギャップを埋めようとしたりすると考えられています》
つまり、大舞台の前には、自分をあまり意識してはいけないのです。
《仕事で大切なプレゼンテーションを行う際に、自分の評価への影響をプレゼン直前に強く意識すると、相手の反応が気になってうまくいかないことが考えられます》と、著者は言います。
《成功へのプレッシャーがかかる場面では、自分の評価を気にするのではなく、良い成果を得ることに注意を向ける》ことが大切であり、そのためには十分な準備とリハーサルを重ね、《行動を自動化することでプレッシャーに対処できる》のだと……。
もちろん、そうしたことを知ったからといって、大舞台の前に自分に意識を向けないことがすぐにうまくできるわけではないでしょう。それでも、対処法を知っていることは改善の大きな一歩になるはずです。
中小企業の組織マネジメントにも活かせる
本書は「産業組織心理学」のような組織の視点ではなく、会社で働く個々人に焦点を当てている点に特徴があると、先に述べました。
しかし、個人に向けた視点を重視しているとはいっても、本書の知見は組織マネジメントにも十分に活かせるでしょう。
とくに、中小企業経営者が本書を読めば、社員一人ひとりがいっそう幸せに、やりがいを持って働けるようにするための改善のヒントが、多数得られるはずです。
たとえば、目標設定とやりがいの関係について論じた部分(第2章第1節)には、次のような一節があります。
《自分で目標を決めると、その目標へのコミットメントが高まることがわかっています。80を超える関連する研究を統計的にまとめたクラインらによれば、目標へのコミットメントを高める重要な先行要因は、自分で決める、あるいは自分がかかわって決めるということでした 。
さらに同研究では、目標へのコミットメントが高いほうが、難しい目標であってもパフォーマンスをあげることができると論じています》
《また別の研究では、仕事の負荷が高く、裁量が小さいといった、一般にストレスを高めるような条件下でも、自分で決めた目標を追っており、それを達成できるとの信念を持つことで、仕事への満足感は11% 上昇し、気分の落ち込みは12% 軽減することが報告されています》
社員一人ひとりが自分で決めた目標を持つことが、仕事にやりがいを感じていきいきと働くためにどれほど大切かを、このくだりは改めて教えてくれます。
本書を読んで、「これは、自分が経営者としての経験から得た実感とは異なる」と感じる部分もあるかもしれません。しかし、著者は次のように述べています。
《学術的な知見は、多くの研究者が長い時間と精緻な研究手法を通じて作り上げてきたものです。自分の考えとの同異を考えるだけでも、価値があるのではないでしょうか》(終章)
心理学の研究に基づいているとはいえ、本書の内容をすべて鵜呑みにする必要はもちろんありません。しかし、書名のとおり「職場に活かす」ことができる知恵がちりばめられていることは間違いないのです。ぜひ活用してみてください。
今城志保著/東洋経済新報社/2023年9月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






