『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第98回/『シン・日本の経営――悲観バイアスを排す』
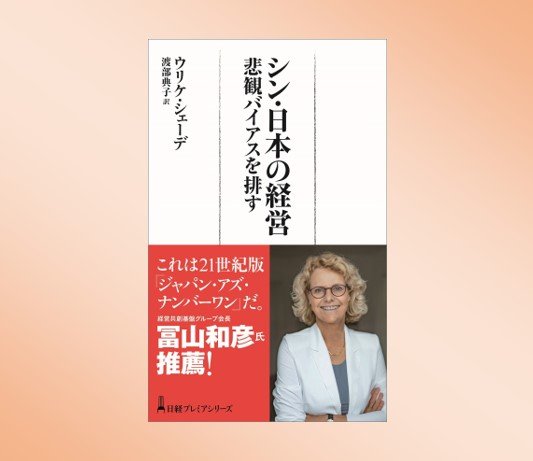
自信喪失した日本人に希望を贈る書
「失われた30年」と呼ばれる長い経済低迷の間、私たちはずっと、日本経済と日本企業についてのネガティヴな評価にさらされてきました。
とくに近年は、「安いニッポン」という言葉が流行り、インバウンド(訪日外国人客)たちの豪遊が頻繁にマスコミで報じられるため、ますます日本の低迷ぶりが印象づけられています。
日本企業についても、バブル時代までの隆盛と比較して低迷が語られ、ネガティヴな評価がマスメディアにあふれています。
しかし、本当に日本経済と日本企業はそんなに「ダメになった」のでしょうか? 一度立ち止まって冷静に考えてみる必要があると思います。
そのための格好のテキストとなるのが、今回取り上げる『シン・日本の経営――悲観バイアスを排す』。親日派の経営学者が、マスメディアで幅をきかせる「日本悲観論・衰退論」に異を唱えた1冊です。
《日本のビジネスは世界に後れをとっておらず、30年間ずっと停滞してきたわけでもない。事実を見つめ、データを比較し、事業戦略を分析すれば、日本のビジネスが停滞どころか、再出発の準備をしてきたことがわかる。そろそろこの変革を解析すべき頃合いだ。本書では「停滞する日本」ではなく、「変貌を遂げて再浮上する日本」に目を向けたい》(「はじめに」)
日本経済と日本企業の底力、そして再興の予兆に焦点を当てた本書は、この30年間ですっかり自信喪失してしまった我々日本人に、希望の光を贈る書と言えます。
日本をこよなく愛するドイツ人経営学者
著者のウリケ・シェーデ氏は、ドイツ出身で米国在住の経営学者です。現在は米カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル政策・戦略大学院の教授を務めています。
ちなみに、「両利きの経営」の提唱者の1人として知られる著名な経営学者、チャールズ・オライリー(米スタンフォード大学経営大学院教授)氏の妻でもあります。
シェーデ教授は1982年に初来日し、各地を旅するなどして、すっかり日本に魅了されました。そして、「日本について研究することを一生のテーマとする」と決意し、一橋大学の博士課程で学び、ドイツ・マールブルグ大学で日本学と経済学の博士課程を修了。現在までずっと、日本の企業戦略を専門に研究を続けています。これまでの日本在住経験も通算9年以上に上るそうです。
シェーデ教授は日本をこよなく愛する人ではありますが、研究者ですから、その評価は感情的でやみくもな「日本礼賛」ではありません。データとエビデンスに基づく、客観的で冷静なものです。
とくに、本書は教授が2010年から続けてきた、日本の高収益企業を研究する大掛かりなプロジェクトを踏まえていますから、その信憑性は高いと言えます。
《この研究プロジェクトに私が着手したのは2010年に遡る。幸運にも、日本政策投資銀行(2008年に株式会社となった)設備投資研究所の下村フェロー(海外客員研究員)として招かれたのだ。プロジェクトの目的は日本の高収益企業を研究することにあった。(中略)それ以後、数年にわたって、何度も日本を訪れては、成功企業に挙がった数社の経営者にヒアリングを行った》
10年以上を費やしたこの研究プロジェクトの成果をまとめたのが、本書なのです。日本人すら気付かなかった日本経済・日本企業の底力が浮き彫りにされています。
「舞の海戦略」と「ジャパン・インサイド」
《本書を通じて、私が何よりも払拭したいのは、日本はもう終わりだとする考え方だ。そんなことはない。日本企業は力強く、機敏で、賢い新タイプのプレイヤーとして再浮上している》
「はじめに」にはそんな一節もあります。では、日本の「再浮上」とは何を指すのでしょう? シェーデ教授はそれを、《世界の製造やインフラ・システムに欠かせない多くの中間財や市場で、世界リーダーとして復活を遂げつつある》ことだと表現しています。
30年間も悲惨な状況であり続けてきたのなら、なぜ日本はいまも世界第4位の経済大国なのかと、教授は問います。なぜ世界20位くらいにまで急落していないのか、と……。そして、次のように指摘するのです。
《日本が世界経済を牽引する立場を維持している主な理由は、何といってもグローバルな技術リーダーであるからだ。意外に思う人もいるかもしれないが、これにはデータの裏付けがある。ハーバード大学グロースラボの「経済複雑性ランキング」を見ると、日本は過去 30 年にわたって世界第1位だ》
ここでいう「複雑性」とは、“技術的に複雑で、作れる国がごく限られている機械や素材などを作る能力”を指します。その能力においては30年前もいまも日本が世界第1位であり、それこそが日本「再浮上」のカギだと言うのです。
《30 年にわたる「停滞」の後で、どうして日本が技術面の複雑性と多様性で世界をリードし続けているのだろうか。それは、マクロ経済的にはいくつかの課題を抱えていたが、ミクロ経済的な企業レベルで、日本は長い間、特定の技術分野で中核的な強みを持ち続けてきたからだ》
そのような強みを持ち続けてきたにもかかわらず、過去30年間で日本企業が大きく衰退したように見えるのはなぜでしょう?
理由の1つは、多くの日本企業が30年の間に「ピボット」(方向転換)し、規模の大きさを追求するのをやめて《アジャイルかつ機敏な人材が働く小規模拠点と技術力》に注力する方向に舵を切ったことだと、シェーデ教授は言います。
教授は、そのピボットを「舞の海戦略」と名付けました。もちろん、1990年代に活躍し、「技のデパート」と呼ばれた小兵力士・舞の海にちなんだネーミングです。
理由の2つ目は、多くの企業が「舞の海戦略」に転換した結果、日本の技術的優位が見えにくくなったことだと指摘されています。
《「舞の海戦略」にピボットした重大な結果として、技術リーダーシップがあまり目立たなくなったことが挙げられる。製造業では、技のデパートの組織能力は多くの場合、素材や部品など中間財に集中しており、視認しづらい》
その「見えにくさ」を、教授は「ジャパン・インサイド」と呼びます。
かつてインテルは、「インテル・インサイド(=インテル入ってる)」と呼ばれるマーケティング戦略を大々的に展開し、パソコンにインテル製品が欠かせないことをアピールしました。それを踏まえたネーミングです。
インテルとは違い、日本は「ジャパン・インサイド」――つまり、多くの製品が日本製の材料や部品を用いていることをほとんどアピールしていない……そのことが、日本企業の強さを見えにくくしているというのです。
《自動車、飛行機、携帯電話、コンピュータ、スマート・サーモスタットから電動歯ブラシまで、ほぼすべての家電が「ジャパン・インサイド」となっている。(中略)さらに、製造装置も多くは日本で生産されている。このように、「ジャパン・インサイド」はあまねく存在している。(中略)日本が製品の複雑さと影響力で世界第1位という理由はここにあるのだ。また、この「見えづらさ」は、第1位であることを知って驚く人が多い要因にもなっている》
《複雑でつくるのも模倣するのも難しい中間財について、日本への依存度が世界的に高まった結果、多くの日本企業は気づかれないうちにアジアの多くのバリューチェーンの技術的な支柱となってきた》
本書では製造業に焦点が当てられていますが、ほかの多くの分野でも同様の現象が起きていると、シェーデ教授は言います。
変化に時間がかかる「タイトな文化」の日本
日本企業の現状と今後の展望について、本書には目からウロコが落ちるような指摘が数多くあります。そのもう1つの例は、日本の「失われた30年」についての独自の分析です。
本書の後半でなされるその分析の中で、シェーデ教授は《1990年代から2010年代にかけては「失われた時代」でも「停滞した時代」でもない。むしろ、ある種の思春期のようなもので、日本の産業構造が大きく変わるシステム転換期といえる》と述べます。
つまり、バブル期までの経済に対応していた日本企業を、その後の時代にふさわしい形に転換するために30年を費やしたというのです。それは転換のために必要な年月であり、けっして無駄に失われたわけではない、と……。
ではなぜ、転換に30年もかかったのでしょう? その理由として、教授は「タイトな文化」と「ルーズな文化」という二分法を持ち出します。
元はミシェル・ゲルファンド(スタンフォード大学経営大学院組織行動学教授)という心理学者が提唱した理論で、国などの文化を、何事にも大胆で変化が早い「ルーズな文化」と、安定を好み、慎重で変化が遅い「タイトな文化」に大別するものです。
その理論によれば、日本は典型的な「タイトな文化」の国であり、社会の変化には非常に長い時間を要します。一方、アメリカは典型的な「ルーズな文化」の国です。どちらが上という話ではなく、タイプの違いであり、どちらにも長所と短所があります。
そして、極めて「タイトな文化」を持つ国だからこそ、日本は《昭和モデルから 21 世紀のシン・日本モデルへとピボットする》までに30年かかったのだと、シェーデ教授は言うのです。
《たとえば、終身雇用制度が変わるまでに 30 年かかった。1990年代から自然にその方向へ進んだが、働き方改革の法案が制定されたのは2019年である。これは、適応するために 30 年間の猶予を与えたとみなすことができる。実際に、現状では失業率の増加は比較的小さく、大量倒産、所得格差の拡大、政治不安、ポピュリズムの高まりを起こさずに、変革が達成されてきた。
この安定性のために日本が支払った代償が、経済成長の鈍化だ》
日本は、30年を費やした変化をようやく終え、これから成長に向けてギアを上げていくというのが、シェーデ教授の見立てなのです。
ただし、教授は日本の未来を手放しでバラ色だと言っているわけではありません。《経済成長率や経済規模で日本が再び「ナンバーワン」になることはまず見込めない》とも指摘しており、「再浮上」は限定的と捉えているのです。
それでも、「日本はこれから衰退する一方だ」という悲観的言説にすっかり慣れてしまった私たちに、本書はうれしい驚きをもたらすでしょう。
本書は大企業の話が中心ですから、中小企業経営者が読んで、すぐに経営に役立つわけではありません。
しかし、日本企業の明るい未来を描き出す本書は、中小企業経営者にも希望を与えるものであり、一読の価値があります。
ウリケ・シェーデ著、渡部典子訳/日経プレミアシリーズ/2024年3月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






