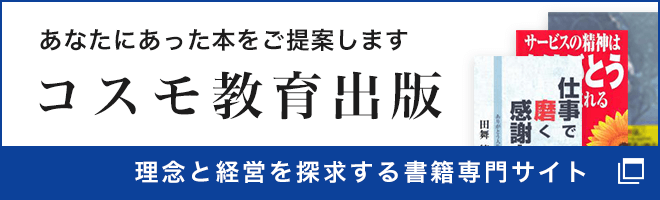『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第95回/『アナーキー経営学――街中に潜むビジネス感覚』
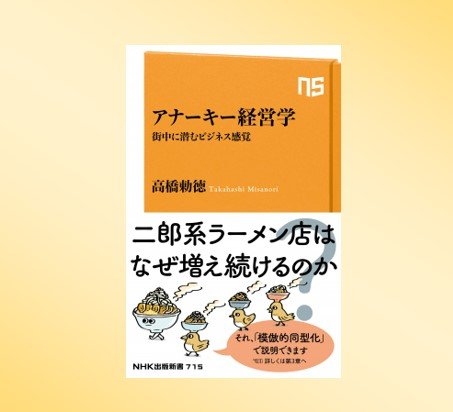
タイトルに込められた意味とは?
『アナーキー経営学』……アナキズムが「無政府主義」と邦訳されることを考えれば、なかなか挑発的なタイトルです。
しかし、本書で言う「アナーキー」とは、反体制社会運動ともパンク・ロック(「アナーキー・イン・ザ・U.K.」という、パンク・ロックを代表する楽曲があるのです)ともまったく無関係です。
この言葉に込めた意味について、著者の高橋勅徳(みさのり)氏は「はじめに」に次のように記しています。
《経営学に野生の経営感覚を取り戻すためには、アナーキーという力強い言葉の力を借りる必要があるのではないかと考えたわけです。
アナキズムとはもともと、「支配者がいない」ことを意味する古代ギリシア語のanarkhiaを語源としています。あらゆる組織と権力からの統制と抑圧を拒否し、否定するその考え方の裏には、一人ひとりが社会との関係を見直し、どう生きるかを問い直す考え方が存在していたはずです》
『野生の経営学』というタイトルでもよかったのかもしれませんが、よりインパクトの強い言葉を求めて『アナーキー経営学』にしたというニュアンスでしょうか。
「野生の経営感覚」を取り戻すために
高橋氏は経営学者(東京都立大学大学院経営学研究科准教授)ですから、本書も当然、経営学の最先端の研究成果を踏まえた内容です。ただ、『アナーキー経営学』と銘打つだけあって、経営学の本としては型破りとも言える1冊になっています。
というのも、著者自らの趣味(フグ釣り、筋トレ、二郎系ラーメンなど)や身近な見聞を通じ、経営と経営学の役割を問い直していくエッセイであるからです。
その点で、当連載で前回取り上げた『世界は経営でできている』(岩尾俊兵著)と、共通項が多いと言えます。2冊とも、経営が単なる「企業の金儲け」と同一視されがちな風潮に異を唱え、幅広い視点から経営の本質を問い直す試みなのです。
たとえば、本書には次のような一節があります。
《経営という概念の起源は、マックス・ウェーバーの宗教社会学の中で提唱されたBetriebに求められます。英語でmanagement、日本語で経営と翻訳されたBetriebは、「一定種類の持続的行為」として定義され、「経営という概念は目的継続性という標徴にあてはまる限り、政治上の事業や教会上の事業、協会上の事業、等々」にあてはまる行為であるとウェーバーは指摘します。
(中略)
経営という概念が本来見据えようとした対象が、「一定種類の持続的行為」であるならば、その目的は「儲けること」や「イノベーションを起こす」ことに限りません。むしろ、 ビジネスという手垢が付いた対象の「外」には、日常生活の中で「生き残るため」に経営体を組織し、運営していく「野生の経営感覚」があるのではないでしょうか》
しかも、そのような経営概念の問い直しを、大上段に構えず、個人的体験を綴る軽エッセイのスタイルで行っている点でも、2冊は共通しています。
よく似た傾向を持つ2つの新書が同時期(1ヵ月違い)に刊行されたことは、単なる偶然ではなく、時代の潮目を反映しているのかもしれません。
「資本主義の行き詰まり」が指摘され、「新しい資本主義」を模索する試みも盛んに行われている昨今、経営や経営学にもまた問い直しが求められているのでしょう。
経営学者の視点から「街のビジネス」を見る
《街中に潜むビジネス感覚》という副題のとおり、各章では、二郎系ラーメン、フグ釣り漁船、筋トレ用プロテイン、お寺のサイドビジネス、転売ヤー、マッチングアプリなど、一般の経営学ではあまり俎上に載ることがない「街のビジネス」――言い換えれば「野生のビジネス」――に光が当てられています。
そして、それらの「街のビジネス」の本質を、経営学の理論を用いて読み解いていくのです。
一例として、本の帯にも取り上げられた二郎系ラーメンについての章を挙げてみましょう。その章では、《同じジャンルのラーメン屋があちこちで増殖している》理由が、経営学的観点から鮮やかに解説されています。
《銀行の融資担当者やお客さんの立場から、いかにお店を立ち上げ、軌道に乗せていくのかを考えると、流行っているラーメンを模倣するというのは安易な選択ではなく、最も合理的な選択であると考えられるのではないでしょうか?
経営学における制度派組織論では、このような現象を模倣的同型化と表現します》
そして、他にないようなオリジナリティあふれるラーメン店を開こうとしても、出店自体のハードルが高い上に成功も難しいことが、次のように解説されています。
《経営学では、新奇性の脆弱さ(liability of newness)として知られる、著名な議論が存在します。多くの企業は、競合他社との競争に勝つために、商品やサービスの内容から、組織構造まで新奇性=イノベーションを求め続けています。実際、私達は「新しさ」を求めることはどこかで正しい、と無自覚に信じてしまっているでしょう。しかし、実際に商品やサービスを購入する消費者や、企業を投資対象とみなす投資家や銀行からすると、新奇性が高い企業=新しすぎる商品やサービスを提供する斬新な企業ほど、購入や投資を見送られることが指摘されています》
《そう考えると、臆面もなく流行りを模倣したお店からはじめて、まず生き残ることからはじめる、街のラーメン屋のほうが現実的で、スマートな経営感覚を有しているのではないでしょうか》
この例のように、「日常に溶け込んだ『街のビジネス』が、経営学者の目にはこんなふうに映るのか!」という驚きが、本書の随所にあるのです。
中小企業経営者にとっても学びが多い
もう一つ例を挙げます。第5章で、お寺がビルや駐車場などを経営することの意味を考察したくだりも新鮮です。著者はそのことを、経営学の「脱連結」という概念を用いて解説しています。
《昨今の経営学では、脱連結という議論が展開されています。
企業組織にとって、目的と手段の一致を目指すことは、強力な組織を形成するための必然に見えます。しかし、その前提となる環境が変わった時(例えば明治維新のように)に、目的─手段の関係が固く結びついていると、組織は変化に対応できず死滅してしまう。激しい環境変化に対応して生き残るのは、目的─手段の連結が弱く、容易に脱連結して手段を入れ替えることのできる組織なのです》
古くからあるお寺がビル経営や駐車場経営をするのは、信仰と稼ぎを「脱連結」する試みであった……という見立てです。
《信仰と稼ぎを緩やかに分離した寺院は、檀家の減少を気にすることなく、信仰を継続する道が切り開かれました。結びつけるのではなく、切り離すことで生き残り、イノベーションに至る道が存在しているのです》
お寺のサイドビジネスをこのような角度から捉えた解説を、私は初めて読みました。
本書で光が当てられる「野生の経営感覚」は、大企業経営者よりも中小企業経営者に近しいものだと思います。
身近な街のビジネスを通じて経営学の最先端が学べる本書は、中小企業経営者にとって、学術的な経営学書よりも読みやすく、それでいて学びも多い内容と言えるでしょう。
高橋勅徳著/NHK出版新書/2024年2月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
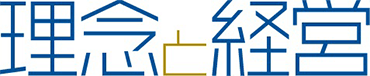


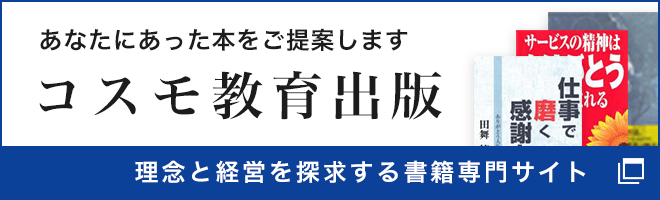





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)