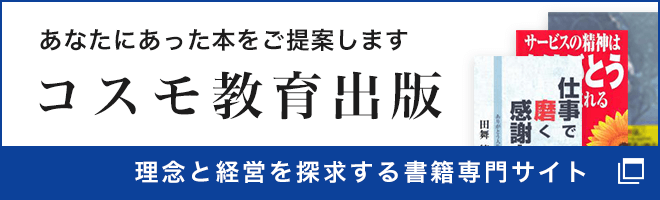『理念と経営』WEB記事
巻頭対談
2024年 4月号
異能を育て、異質と出合える 「現場づくり」を急げ!

国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長 石村和彦 氏 ✕ 株式会社シナ・コーポレーション代表取締役 遠藤 功 氏
日本最大級の公的研究機関である産業技術総合研究所(以下「産総研」)では大胆な組織改革が進行中だ。石村和彦理事長は、世界屈指の素材メーカー・AGCを率いた経験を活かし、研究成果の社会実装をさらに加速させる仕組みづくりを指揮する。日本の製造現場を長年見続けてきた遠藤功氏との対談から浮かび上がる、日本のものづくりの課題と再生への道筋。
「現場の力」を信頼することを、経営者として貫いてきた
石村 僕は旭硝子(現AGC)の社長時代から、遠藤先生の『現場力を鍛える』や『現場論』(いずれも東洋経済新報社)などのご著書を愛読してきました。ですから、今日は初対面ですが、初めてお会いするような気がしないんです。
遠藤 ありがとうございます。私のライフワークの一つが、いま挙げていただいた「現場力」の研究なんです。石村さんは、まさに旭硝子の製造現場からキャリアをスタートされ、経営者としても現場力重視で歩んでこられた方だと認識しております。
石村 僕が1979(昭和54)年に入社して最初に配属されたのは、工場のガラス製造設備が故障したら飛んでいって修理する部署でした。
夜中でも早朝でも、機械が壊れたら呼び出されて修理に行かないといけない。頻繁に呼び出しがあったものですから、「なるべく呼び出されないで済むように、壊れない設備にしよう」と思って、改良を重ねました。同じ設備でも、故障しなくなると歩留まりが上がってくるんです。
遠藤 そういう原点があるからこそ、経営側に回ってからも現場力を重視されたのですね。
石村 ええ。遠藤先生がご著書で「製品は真似できても、現場力は真似できない」と書いておられたとおり、製品だけで他社と差別化することは難しいんですね。製品はすぐに真似されてしまいますから。だからこそ、現場力に支えられた生産技術力を磨かないといけないのです。
遠藤 私はそのことを、「現場力の模倣困難性」という言葉で表現しています。
石村さんの大きな節目は、2000(平成12)年に赤字だった子会社「旭硝子ファインテクノ」の社長に就任され、4年で見事に再建されたことだと思っています。その過程でも現場力がカギになったのでしょうか?
石村 そうですね。僕が赴任したときには赤字垂れ流しの状態で、借金が100億円以上ありました。そんな中で、僕は現場の社員が100%以上の力を出せるようにすることに集中したんです。
遠藤 最初はどこにメスを入れられたんですか?
石村 当時、開発部隊の人間はみんな、旭硝子本社の社員が駐在の形で来ていました。出向ではなく、駐在です。当然、製造部隊との一体感なんかありません。
僕は本社に言って、まずそこを変えてもらいました。開発部隊を出向に変えたのです。その瞬間から全員が僕の部下になり、そのうえで真っ先に行ったのが「開発部と製造部のリーダーの入れ替え」でした。
遠藤 なるほど。組織の上層部を交ぜることで、縦割りになっていた会社の壁を壊して、一体感を高めようとされたわけですね。
石村 ええ。それからは、製造現場と開発部隊のコミュニケーションが劇的に密になっていきました。
遠藤 私の用語で言う「ツボ割り」ですね。大きな会社は必然的に各組織がタコツボ化していくので、経営者が意識してそれを割っていかないといけないのです。
石村 改革は他にもいろいろやりましたが、最初の一手がそれでした。
遠藤 子会社の再建成功が、本社の社長就任の決め手になったのですか?
石村 それも要因の一つでしょうが、その後に関西工場の工場長になったときの出来事も大きかったと思います。
液晶ガラスのもとになる大きなガラスを作る工場なんですが、当時、ある技術的な困難を抱えていました。その困難が突破できないと、液晶部門全体が存続の危機に陥りかねない状況でした。突破するアイデアを現場が考えていたのですが、本社が反対してそれをやらせずにいたんです。
僕は「他にやることがないなら、やってみたらいい。失敗してもこれ以上(状況は)悪くならんだろう」と、工場長権限でゴーサインを出しました。運よくそれが成功したんですよ。僕自身は何もしていませんが(笑)。
遠藤 いやいや、現場の知恵を信頼して決断をされたわけで、リーダーとして大手柄ですよ。
オープンイノベーションの前に
「部門の壁」を壊すことが先決
遠藤 子会社の社長や工場長としてのご経験が、旭硝子の社長になられてから活きましたか?
石村 そうですね。旭硝子でもタコツボ化は進んでいたので、ツボ割りをやっていきました。ほとんどの人は自分が属する事業部のことしか知らなくて、その中から出たこともない。それを壊さないといかんと思ったのです。
それと、工場の若手と話していたら、「技術面で困ったときに、相談できる人が近くにいない」と言われたんですよ。それなら、誰に相談したらよいのかを全社的に「見える化」しようと考えました。遠藤先生の『見える化』(東洋経済新報社)というご著書も参考にしまして……。
遠藤 それは光栄です。
石村 例えば、ガラスを溶かす技術の専門家は、全社合わせて200人ほどいましたが、液晶部門、建築部門、自動車部門、研究所とバラバラに散っていて、部署が違うと交流がなかったんです。そういう専門人材を分野別にスキルマップ化しました。専門領域と自分のレベルを自己申告させて、そのレベルで妥当かどうかを上長にも確認して、完成したスキルマップを全社的にオープンにしました。イントラネット上に分野別のコミュニティーを設けて、例えば若手が「いまこういうことで困っている」と書き込めば、詳しい人にアドバイスしてもらえる仕組みをつくったんです。さらに、分野別の「社内学会」もつくって、部門を横断して専門家同士がつながるようにしました。
遠藤 素晴らしい。まさにツボ割りですね。
私が最近感じているのは、いまの経営者は昔と比べてはるかに複雑で難しい問題に直面しているということです。だからこそ、組織全体で知恵を出し合うことが重要で、部門の壁を越えて活発に意見が飛び交う環境をつくらないと、難易度の高い問題には立ち向かえないと思います。
私はコロナ禍になる前まで毎年のようにシリコンバレーに行って、Googleを筆頭とする先端企業を視察していました。そうした企業の幹部たちが口を揃えて言うのは、「社内で自由闊達にものが言えないといけないし、人的交流が活発でないといけない」ということでした。それこそイノベーションが起きるための大前提だ、というのです。
石村 同感です。社外とつながって起こす「オープンイノベーション」の大切さが言われる昨今ですが、それ以前にまず、社内のネットワーキングをきちんとやらないといけません。
遠藤 私がGoogleの本社を訪問したとき、社内に部門を越えて雑談するオープンコミュニティーがありました。社内の多彩な人材―例えばAIの専門家、自動運転の専門家、量子力学の専門家などが、自由に出入りして会話をするスペースです。
石村 なぜそこにみんな集まるんですか?
遠藤 ネットワーキングそれ自体が目的です。自分とは異なる分野の専門家と雑談して、知的刺激を得ることを求めて集うんです。そうした仕組みがあること自体が、Googleのイノベーション力の源泉の一つなのでしょうね。
石村 実はいま、産総研でも所内にそうしたエリアをつくることを考えているんです。まず手始めに、つくばで2カ所ほど用意しようとしています。一番心配しているのは、そこに本当にみんなが来るかどうかです。人を呼び込むことを何か考えろと言っているところです。
また、産総研には7つの研究領域がありますが、それらの領域が融合して研究に取り組めるように、「融合研究センター・ラボ」というものも立ち上げました。
遠藤 研究者は自分の研究テーマに固執しがちですから、一般社員以上にツボ割りが大切ですね。みんなすごく深いことをやっているのに、広さがないから、その深さが活かせていない。石村さんが推進されている所内ネットワーキングは、広さを与えるツボ割りの第一歩だと思います。おそらく研究者には対人関係が苦手なタイプも多いでしょうから、仕組みをつくってコミュニケーションのハードルを下げてあげることが、とくに大事です。
石村 若い人たちは対面のコミュニケーション能力が下がってきているから、なおさらですね。
構成 本誌編集長 前原政之
撮影 中村ノブオ
本記事は、月刊『理念と経営』2024年 4月号「巻頭対談」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
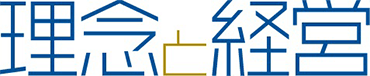


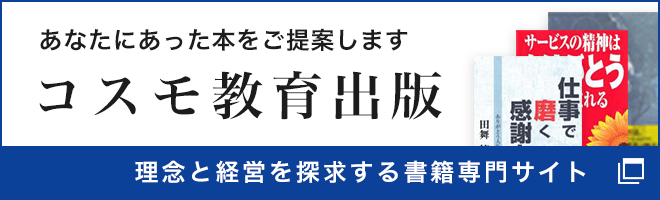





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)