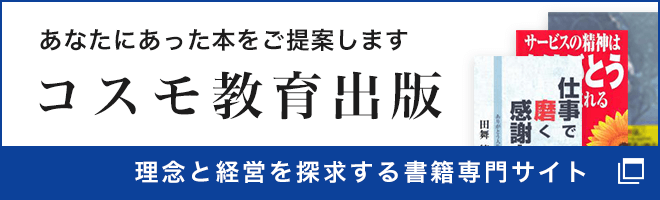『理念と経営』WEB記事
人とこの世界
2024年 3月号
訪問看護の現場で 「できることをできる範囲で」続けたい

全国訪問ボランティアナースの会 キャンナス代表 菅原由美 氏
各地の災害現場で、みんなに頼りにされたのは、ピンクのTシャツを着た看護師(ナース)たち。ふだんは地域の訪問看護のために『サンダル履き』で駆けつける。その志と現在の訪問看護問題について詳しく聞いた。
「できることを“精一杯”やるしかない」と思った東日本大震災
東日本大震災の後、宮城県のいくつかの避難所で"避難所のナイチンゲール"と話題になった看護師たちがいた。ピンクのTシャツを着た「キャンナス」の面々である。
キャンナスは1997(平成9)年に設立されたNPO法人で、訪問ボランティアのナースの集まりだ。言い出しっぺで代表の菅原由美さんが英語のキャン(できる)とナース(看護師)をつなげて名づけたという。
菅原さんたちが被災地に向かったのは、地震発生8日目、3月19日の深夜のことだった。いち早く現地で活動していた知人の医師から要請を受け、気仙沼市の総合体育館(ケー・ウエーブ)に入った。
「私も含めて、まず8人が行きました。その後、入れ代わり立ち代わりで被災地に入っていったのです」
ケー・ウエーブを足場に、松島町、石巻市と常駐する避難所を増やしていった。避難所に入ると彼女たちは何より衛生環境の整備をした。
「避難所内の掃除とトイレ清掃です。みんな当たり前のようにそれをやり、その後はお年寄りから赤ん坊まで、健康状態を聞き、いま何が必要なのかを聞き取っていきました」
ストローや爪切り、血圧計、補聴器、車いす、ベビー用品などなど。キャンナスでは、それらの物資と交代のナースを乗せ、神奈川県藤沢市にある本部から毎週火曜日と金曜日、被災地に向け車を出した。
物資の輸送は6月で止めたそうだが、支援は1年半、翌年9月まで続けた。「できることをできる範囲で」という会のモットーをいったん置き、菅原さんは「できることを精一杯やろう。看護師として恥じない行動を」というメッセージを被災地に行く仲間たちに伝えたという。
「避難所に泊まり、24時間支援活動をしました。夜中にはいろんなことが出てくるんです。細かいお困り事もキャッチできました」
昼間は我慢しているが、子どもが寝た後に嗚咽する母親がいる。気を張って自宅の整理などを続けている壮年も夜、一息つくと不覚にも涙を流す。誰もが思い出を流され、肉親を津波で失っているのだ。
「私たちはただ話を聞くだけですが、ナース相手だと安心できるのか、心を開いて話をしてくださるんです」
それが、どんなにか心の支え、ケアになったことだろう。
ケガの治療や必要な薬の調達もし、感染症対策のために玄関の泥よけマットの代わりに濡らしたバスタオルも置いた。お年寄りの夜中のトイレの見守りをしたり、入れ歯をなくした人のためにお粥をつくったり……。やることはいっぱいあった。
それができたのも、キャンナスのナースたちが日頃から利用者たちの生活支援をしているからにほかならない。これ以降、豪雨や地震などの被災地にはピンクのTシャツを着たナースたちの姿があった。
自宅で看取れば、みんながハッピーになるケースも多いはず
菅原由美さんは東京生まれの鎌倉育ちである。大学病院で看護師として勤めた後、結婚退職した。
「専業主婦になったんですが、ひと月で限界。ハハハハ」
そう、大声で笑った。狭いアパートで、朝、夫を送り出すと、すぐにやることがなくなったと言う。それで、家の近くの企業の保健室や保健所のパート職員として働いた。働きながら3人の子を育て、親族の介護も経験した。
なかでも夫の祖母の介護がキャンナスの発想につながったと、話す。
祖母は1989(平成元)年に体調を崩し入院した。すでに100歳を越えていた。入院中は夫の母と1日交代で病院の祖母に付き添った。
「子どもを実家に預け、泊まるんです。翌日は寝不足で大変でした」
ところが、年齢を考えると手術もできないだろうと、祖母が退院した。
「みんなに、いつもの生活が戻りました。一番喜んだのは祖母でした」
自宅で祖母を看取ることになったそうだが、菅原さんは「みんなハッピー」だったと言うのである。この経験から、在宅での看護や介護の手伝いができるナースが地域にいれば、多くの人の役に立てるのではないか、と思うようになった。
取材・文/鳥飼新市
撮影/鷹野 晃
本記事は、月刊『理念と経営』2024年 3月号「人とこの世界」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
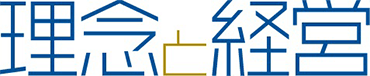


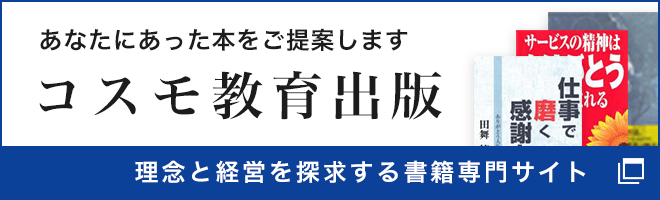





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)