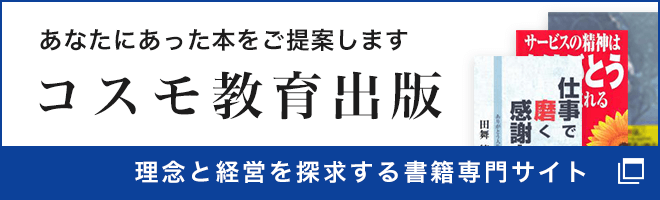『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第86回/『文豪、社長になる』
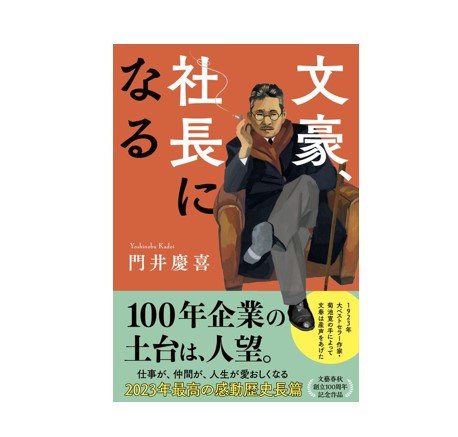
100年企業を築いた経営者としての菊池寛
今回は、当連載で初めて小説を取り上げます。
企業小説や歴史小説など、経営を学べる小説もたくさんありますから、今後も折にふれ小説を取り上げていきたいと思います。
さて、今回取り上げる『文豪、社長になる』は、株式会社文藝春秋の創業者・菊池寛(1888~1948)の伝記小説です。
巻末に《この物語は、史実に基づくフィクションです》と但し書きがあるとおり、一部に作者の創作も含まれていますが、基本的には事実に即しています。
文藝春秋は、いうまでもなく日本を代表する出版社です。人気作家でもあった菊池寛によって創業されたのは、1923(大正12)年のこと。つまり、昨年(2023年)「100年企業」の仲間入りを果たしたのでした。
まさに「文藝春秋創立100周年記念作品」として、文春側から著者にオファーされて刊行されたのが、この『文豪、社長になる』です。
著者の門井慶喜(かどい・よしのぶ)氏は、推理小説から歴史小説まで幅広い作品を手がける人気作家。2018年には、父親の視点から宮沢賢治を描いた『銀河鉄道の父』で直木賞を受賞しています。
文春の看板の一つである直木賞の受賞作家であり、しかも歴史小説が得意であることで、記念作品の書き手に選ばれる資格は十分でしょう。
それに加え、門井氏にはもう1つ、社史マニアとしての顔もあります。さまざまな企業の社史を読むのが大好きで、自宅の書斎にはたくさんの社史が所蔵されているのだそうです。
もちろん文藝春秋の社史も読んでおり、菊池寛の主要作品もすべて読んでいました。そんな背景から白羽の矢が立ったのです。
社史マニアでもある作者らしく、本作は“経営者としての菊池寛”に的を絞った伝記小説になっています。
菊池寛は、くり返しテレビドラマ化・映画化された『真珠夫人』などのベストセラーを放った人気作家でした。本作のタイトルのとおり、「文豪」と呼んでもよいでしょう。
人気作家が執筆のかたわら会社を経営するというと、不慣れな片手間仕事のイメージがあります。しかし菊池は、経営者として、ビジネスマンとしても優れた才覚の持ち主でした。そして、社長業と作家業を見事に両立させたのです。
ゆえに、“経営者としての菊池寛”をクローズアップした本作は、中小企業経営者にとっても学びの多い小説と言えるでしょう。
たぐいまれなアイデアマンだった
菊池寛が創刊した月刊誌『文藝春秋』は、創刊から100年を経たいまなお、日本を代表する総合誌として出版界に君臨しています。
また、菊池が制定した2つの文学賞――芥川賞と直木賞(正式には「芥川龍之介賞」「直木三十五賞」)は、1935(昭和10)年の開始から90年近くを経たいまも、文学界・出版界の一大イベントであり続けています。
そのことだけを取っても、経営者としての抜きん出た才覚がわかります。100年売れ続けるロングセラー商品と、90年近くも年2回ずつ社会現象を巻き起こしてきたビジネスモデルを、1人で生みだしたのですから……。
『文豪、社長になる』では、芥川賞と直木賞が生まれるまでの経緯に、全5章のうちの各1章が割かれています。2つの章は、菊池寛と、芥川龍之介・直木三十五という2人の人気作家の友情物語でもあります。
菊池は、若くして亡くなった2人の親友の名を世に遺そうとして、芥川賞と直木賞を制定しました。しかし、そこにはもう1つ、文学賞をイベント化することで『文藝春秋』や書籍の売上を伸ばそうとする、冷徹でしたたかな計算もあったのです。
その計算どおり、芥川賞・直木賞は「文学賞のイベント化」の最大の成功事例となりました。かりに2つの賞がなかったとしたら、文藝春秋はいまのような大出版社にはなっていなかったかもしれません。
また、月刊『文藝春秋』を軌道に乗せるまでの経緯も、作中に詳細に描かれています。
『文藝春秋』は誌名のとおり、創刊当時は「文芸誌」でした。しかも、菊池寛が友人の作家たちにポケットマネーで原稿料を払って書かせる、同人誌的な雜誌からスタートしたのです。
それを、幅広い話題を扱う総合誌にリニューアルしたのも菊池寛でした。
路線変更当時、すでに先行の総合誌として『改造』や『中央公論』などが大部数を誇っていました。『文藝春秋』は後発だったのです。
にもかかわらず、『文藝春秋』は倍々ゲームで部数を伸ばしました。総合誌化第1号は1926(大正15)年12月号でしたが、翌月には部数が15万部を突破したのです。その背景にも、菊池寛の卓抜なビジネス・センスがありました。
《「中央公論」や「改造」のような硬派とはちがう、「講談倶楽部」や「キング」のような軟派ともちがう雑誌になる。そうして雑誌というものは、類がなければ、
(売れる)》
『文藝春秋』の総合誌化を思いついた心境を表現したそんなモノローグが、作中にあります。菊池寛は先行誌にない独自路線を歩むことによって、『文藝春秋』を人気雑誌にしていったのです。
独自路線の1つが、『改造』や『中央公論』のような硬い論文中心の内容にはしなかったこと。
たとえば、何人かの話者を集めた「座談会」形式の雑誌記事は、いまでは普通にありますが、実は菊池寛が発明して『文藝春秋』で始めたものでした。座談会を多用することで、高度な内容もわかりやすい読み物として提供したのです。
菊池が『文藝春秋』を人気総合誌にしていくプロセスは、現代において後発企業が先行企業に勝つ戦略を練る上でも、大いに参考になるでしょう。
他にも、作家を連れて講演会を行う「文芸講演会」を事業化するなど、菊池は多くの斬新なビジネスアイデアを形にしています。彼は、たぐいまれなアイデアマンでもありました。新規事業の種を探し出し、それを育て上げる手腕にも、経営者が学ぶべき点が多いのです。
弱さと人間臭さも赤裸々に描き出す
ただし、菊池寛はけっして完全無欠の名経営者ではありませんでした。失敗も多いのです。
失敗の最たるものが、「会社のカネ」の章で詳しく描かれる、社員による横領事件。広告部の社員3名が使い込みをくり返し、会社が《深刻な経理上の危機におちいった》ほどの損害を受けたのです。その3名は懲戒免職となりました。
菊池寛は、他の社員から“横領の疑いがある。犯人の目星もついている”という注進を受けていながら、当初はまったく本気にせず、事態を悪化させてしまいました。経営者としては大失態といえます。
しかしその失態も、経営者として社員を信じ抜くという美点が裏目に出たケースとも言えます。
本書の帯に《100年企業の土台は、人望。》という惹句があるように、菊池寛は社員や関係者からの人望が厚い経営者でした。そしてその人望は、菊池が大らかに人を信じ抜いたことが土台となっていたのです。
また、菊池の女性関係についても、彼が死の床で妻に懺悔する次のような言葉に託して、オブラートに包まず描かれています。
「かあちゃんには、頬紅ひとつ買ってやらなかった。でもはじめて会った芸者には三千円の帯を買ったことがある。好きな芸者に会いたいがため用もないのに新潟へ行ったこともある。女優とも寝た。ダンサーとも寝た」
一般の大企業であれば、周年記念作品として刊行される創業者の伝記に、このような言葉が載ることはけっしてないでしょう。
しかし本作は、菊池寛の弱さ、人間臭さまでも赤裸々に活写しているのです。「文春砲」で知られる『週刊文春』の版元らしい度量の広さとも言えます。
いたずらに神格化・美化することなく、“等身大の菊池寛”が描かれた本作――。経営者としての成功も失敗も余さず扱っているからこそ、中小企業経営者にとっても読み応えがあります。
門井慶喜著/文藝春秋/2023年3月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
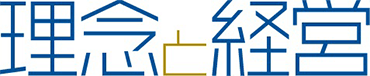


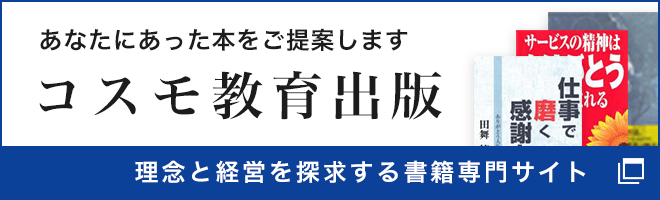





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)