『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第81回/『日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか』
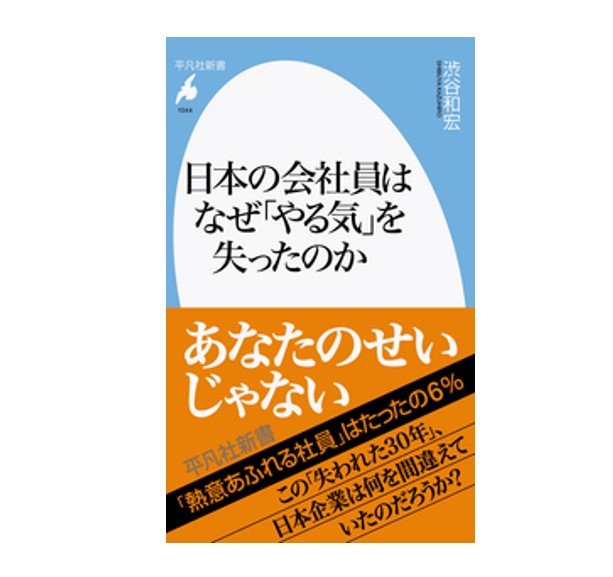
「やる気」をなくした背景要因を探る
いまの日本企業には、熱意あふれる社員がたった6%しかいない――そんな調査結果を、読者諸氏もどこかで目にしたことがあるかと思います。
それは米ギャラップ社による2017年の調査で、たとえば当時の『日本経済新聞』は次のように報じました。
《世論調査や人材コンサルティングを手掛ける米ギャラップが世界各国の企業を対象に実施した従業員のエンゲージメント(仕事への熱意度)調査によると、日本は「熱意あふれる社員」の割合が6%しかないことが分かった。米国の32%と比べて大幅に低く、調査した139カ国中132位と最下位クラスだった。
企業内に諸問題を生む「周囲に不満をまき散らしている無気力な社員」の割合は24%、「やる気のない社員」は70%に達した》(『日本経済新聞』2017年5月26日付)
――この調査結果はあまりに衝撃的だったので、さまざまな場面で引用され、広まっていきました。
高度成長期まで、いや、その後のバブル期に至っても、日本人はむしろ、会社への忠誠心と仕事への熱意が非常に高かったと思います。その度が過ぎて滅私奉公ぶりが揶揄されることはあっても、やる気のなさが国全体の問題となるなど、昔なら考えられなかったでしょう。
つまり、バブル崩壊後の「失われた30年」の中で、日本の会社員たちはジワジワと「やる気」を失い、ついには“やる気のなさが最下位クラス”になってしまったのです。
それはなぜなのか? その背景要因を、ベテラン経済ジャーナリストが平明に解き明かしたのが、今回紹介する『日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか』です。
著者の渋谷和宏氏は、『日経ビジネス』副編集長、『日経ビジネスアソシエ』の創刊編集長などを務めたのち、日経BP社から独立して幅広く活躍されています。
マスメディア出演の機会も多く、テレビの『シューイチ』や『情報ライブ ミヤネ屋』などでコメンテーターを務める姿に見覚えのある人も多いでしょう。
40年以上にわたる経済ジャーナリストとしての取材活動の蓄積が、本書の内容にも遺憾なく発揮されています。
“原因は企業側にある”と鋭く喝破
本書の帯には、「あなたのせいじゃない」というシンプルな惹句が大書されています。日本の会社員が「やる気」を失った原因は企業側にあり、個々の社員たちのせいではないという意味です。
では、日本企業が社員のやる気を削いでいった「原因」とは、具体的にどのようなことなのか? 著者はそれを、さまざまな観点から解き明かしていきます。
「やる気」を失った原因は、会社員であれば、何となくわかっているはずです。自らの経験に照らして、あるいは、周囲で見聞きする話によって……。
本書は、その「何となく」の理解にくっきりとした輪郭を与えます。原因を腑分けし、理路整然と解説して、「なるほど、そういうことか」と深く得心させるのです。
たとえば、主要な問題点として、日本企業が社員たちを「お金のかかるコスト」扱いするようになったことが挙げられています。
《家電やパソコン、事務機器メーカーなどの輸出企業の国際競争力低下や、バブル崩壊による消費低迷などの寒風が吹き始めた1990年代半ば以降、少なからぬ日本の大企業はコストダウンを最優先する「縮み経営」へと舵を切りました。この過程で、社員を会社の業績向上に貢献してくれる資産あるいは可能性ではなく、お金のかかるコストだとみなすようになってしまったのです》
そのようなコストダウン最優先の経営は、バブル崩壊後の危機を乗り越えるための《一時的な緊急避難》であるべきでした。ところが、多くの企業は最悪期を脱してからも「縮み経営」を続けてしまったのです。
その結果、社員たちのやる気は削がれ、日本企業の競争力は低下していきました。そして、ますますコストダウンせざるを得ない状況になり、給与水準は低迷し……と、恐るべき悪循環に陥っていったのでした。
日本企業の“4大失策”を各章で詳述
以上は、本書の「はじめに」で説明される大枠の構造です。そして、続く第1章から4章までの本文では、その大枠が4つの問題に切り分けられ、それぞれ深掘りして解説されています。
4つの問題とは何か? 各章のタイトルを並べてみましょう。
《第1章 「安い賃金の国」への転落――なぜ日本企業の賃金は上がらないのか
第2章 「脅しの経営」の弊害――社員を追い詰める減点主義的な処遇
第3章 コストカッターの罪――人材が育たず競争力が損なわれる悪循環
第4章 「無駄な仕事」のまん延と、自主性・成長機会を奪う「マイクロマネジメント」》
これらのタイトルから内容は推察できるでしょうから、各章について詳述はしません。要は、日本企業が社員たちの「やる気」を削いでしまった“4大失策”が詳しく解説されているのです。
特筆すべきは、第1章が、「賃金低迷は社員の労働生産性が低いからで、社員たちの側に原因がある」という俗論への見事な反論になっていること。
《日本の労働生産性はたしかに低く、それが「安い賃金」の一因であることは間違いありません。
しかし労働生産性が低いのは社員の働き方が悪いからではありません。問題はやはり経営にあるのです》
著者はそう言い、まず「労働生産性」の定義から説き起こします。
その上で、「日本企業の労働生産性が低く、賃金が安いのは、日本企業の生み出す付加価値(粗利益)が低いからである」 「付加価値(粗利益)が低いのは日本企業がつくる製品の値段が安いからである」という結論へと、手際よく解説を進めていくのです。
ここでも、「あなたのせいじゃない」というメッセージがリフレインされています。
自社の経営を見直すための「点検」に有益
以上述べたように、メインパートである1~4章は、『日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか』というテーマの詳細な解説になっています。そこまでで本が終わっていたら、暗澹たる思いだけが残ったでしょう。
そうした読後感になることを避けるためか、著者は「おわりに」で、《日本企業がかつての輝きを取り戻すための提言》を3つ掲げています。すなわち、社員たちが「やる気」を取り戻すための処方箋です。
それは、《1、社員に報い、社員に投資する》、《2、社員を信じ、加点主義で評価する》、 《3、起業家タイプのイノベーターに活躍の場を》という3点です。
本文が極めて詳細であるのに対し、3つの提言の中身はごくシンプルですから、処方箋としては物足りないかもしれません。しかし、最後に希望の光を示そうとした著者の配慮に、私は好感を覚えました。
中小企業経営者にとって、本書は自社の経営を見直すための「点検」に役立ちます。ここに詳述された、社員の「やる気」を削ぐ悪循環に、自社が陥っていないかどうか? それを1つひとつチェックするつもりで読むとよいでしょう。
「うちの会社にはまったく当てはまらないな」と思えるなら、ひとまず安心。逆に、「ピッタリ当てはまる」と感じるようなら、今日から改善に取り組むべきでしょう。
渋谷和宏著/平凡社新書/2023年11月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






