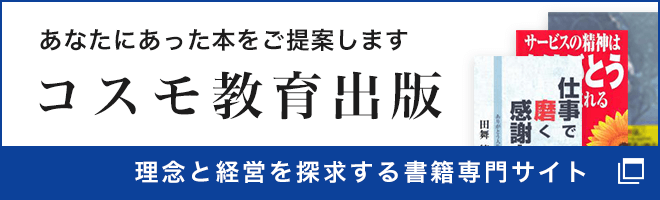『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第79回/『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』
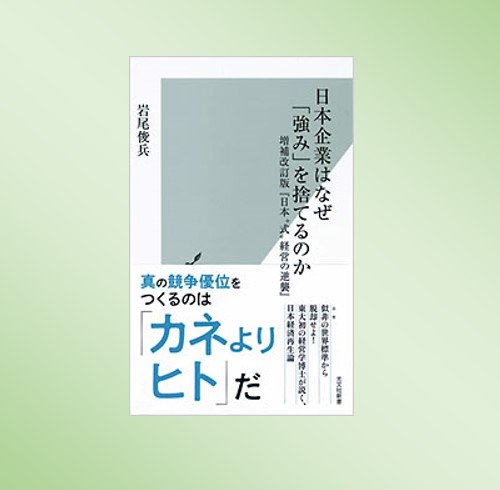
若手経営学者による日本企業再生論
著者の岩尾俊兵氏は、慶應義塾大学商学部の准教授。平成元(1989)年生まれで、まだ30代半ばの若さです。
東京大学史上初の経営学博士(=同大で経営学の博士号を取った初めての人)でもあり、経営学界期待のホープと言えるでしょう。
その岩尾氏の新著である本書は、2021年刊の『日本「式」経営の逆襲』(日本経済新聞出版)を増補改訂・改題して新書化したものです。
各章に長文の補足が付されるなど、大幅にアップデートされていますから、元本を読んだ人にも一読の価値があるでしょう。
帯には、《真の競争優位をつくるのは「カネよりヒト」だ》という惹句が躍っています。これは本書の内容を象徴的に示した言葉です。
「日本『式』経営」といえば、終身雇用・年功序列・企業別労働組合といった制度が思い浮かびます。それらの制度については正負両面のイメージがあるでしょう。ただ、確かなことは、ヒトを大切にする経営だったということです。
しかしいまや、終身雇用制は崩壊寸前で、労働組合も弱体化するなど、昔の「日本『式』経営」は失われつつあります。その大きな要因は、近年、《日本には「ヒトよりもカネが大事」な似非世界標準が広まった》(「はじめに」)ことでした。
《振り返ってみれば、平成の経営は、デフレという、カネ優位の時代におけるヒト軽視の経営だったのである》
日本企業がヒト軽視の経営に傾くことは、自らの「強み」をわざわざ捨ててしまうことにほかならない――それが著者の問題意識です。
そして、本来の「強み」を取り戻すための方途を、著者は探っていきます。本書は、気鋭の若手経営学者による、渾身の日本企業再生論なのです。
流行りの経営コンセプトの多くは、実は日本由来
本書で最も目からウロコが落ちる思いにさせられるのは、第1章《逆輸入される日本の経営》でしょう。
というのも、この章では、「両利きの経営」「オープン・イノベーション」「リーン・スタートアップ」「アジャイル開発」「ティール組織」などという流行りの経営コンセプトが、実は日本由来であることが論証されているからです。たとえば――。
「両利きの経営」については、生みの親であるオライリー教授とタッシュマン教授自らが、《2013年に『Academy of Management Perspectives』誌に発表した論文の329頁において、トヨタ生産方式が両利きの経営の最も分かりやすい例(most visible illustration)だと述べている》こと。
《オープン・イノベーションの提唱者であるカリフォルニア大学バークレー校のヘンリー・チェスブロウ教授もまた、2010年に日本の学術雑誌『研究技術計画』にて、日本企業はオープン・イノベーションに早くから取り組んできたと述べている》こと。
……そのように、米国生まれの最新経営コンセプトだと思われているものが、実は強かったころの日本企業によって生み出されていたことが、明らかにされていくのです。
だからこそ、米国の先進グローバル企業も、いまなお日本の経営を範としている面があります。
《アマゾンの創業者で、いまや世界有数の大富豪でもあるジェフ・ベゾスは、日本の経営から現在でも多くを学んでいると公言している》
《過去の日本式経営の強みは、今ではGAFAM(グーグル、アップル、フェイスブック[現:メタ]、アマゾン、マイクロソフト)をはじめとした世界的企業に取り入れられている》
にもかかわらず、「失われた30年」の間にじわじわと自信を喪失してきた日本の企業人の多くが、「日本の経営は遅れている。米国の経営に学ばないといけない」と思い込み、米国で流行する経営コンセプトをありがたがって、《日本式経営の自己破壊・逆輸入》をしてきました。
それは《「強みを捨て、弱みを取り入れる」という完全な愚行であり、日本企業の存続を危うくする》と、著者は言います。
本書は、「日本の経営は遅れている」という根拠なき悲観論を突き崩し、経営者たちの自信を回復することに役立つでしょう。
日本企業に足りないのは「コンセプト化」の力
ただし、本書は単純な日本礼賛本ではありません。日本企業の弱点も鋭く衝く内容なのです。
たとえば、流行りの経営コンセプトの多くが日本由来であるにもかかわらず、米国生まれの理論にすり替わってしまったのはなぜか? その根本原因は、日本の産官学に経営技術を「コンセプト化」する力が欠けているからだと、著者は指摘します。
《ここで取り上げきれなかったものを含めても、全体的に日本は経営実践や経営技術では健闘しているものの、コンセプトではほとんどボロ負けに近いという実感がある》
《日本は、抽象化・論理モデル化の力をつかって経営技術をコンセプトとしてまとめる点に、弱点があった》
《これまでの日本企業は、文脈に依存した緊密なコミュニケーションを強みとしてきたため、その対極にある抽象化・論理モデル化を相対的に苦手としてきた》
日本社会自体が比較的均一であるうえ、従来の日本企業は同質性の高い集団だったので、仲間内だけで通じる言葉によるコミュニケーションで事足りる面がありました。
そのため、「両利きの経営」「オープン・イノベーション」「リーン・スタートアップ」「ティール組織」などに相当する知恵を持っていても、部外者に説明する言葉に置き換えなくてもよかったのです。
そのことは、昔は日本企業の強みでもありました。しかし、異質な集団にも共有可能にしないといけないグローバル時代には、弱点となります。逆に、移民国家であるアメリカはコンセプト化が得意なのです。
《日本企業は、世界に先駆ける経営技術を数多く生みだしてきた。一方で、経営実務の中から生まれた経営技術をコンセプト化し、サービスやシステムとしてパッケージにして海外を含む他社に売りこむという点では、アメリカをはじめとする諸外国に後れをとってきた。
すなわち、日本は経営技術のコンセプト化に負けてきたのだ》
とはいえ、日本から世界共通の経営コンセプトが生まれた例も、ないわけではありません。その一例として挙げられているのが、『理念と経営』にも折々にご登場いただいている世界的経営学者・野中郁次郎先生が生み出した「知識創造理論」です。
そうした成功例もある以上、日本人にコンセプト化の力が乏しいといっても、その弱点を克服することは十分可能なはずです。著者は本書の後半で、そのための提言をしています。
錯覚に陥らないための予防薬
著者は「はじめに」で、本書の立ち位置を次のように説明しています。
《本書は日々の仕事に役立つ安易な経営上の「答え」を提示しない。むしろ 本書は、「問い」の書である》
《本書は国内外の経営実践や経営理論を手軽に紹介する教科書でも、それらの普及過程を詳述する歴史書でもない》
《本書における経営実践・経営理論は、議論の素材にすぎない。本書はそれらを題材に大局的な見方を提示する警鐘の書である》
これらの言葉が示すように、本書を読んでも、今日・明日の経営にすぐ活かせるというものではありません。
ただし、中小企業経営者にとっても、本書はいわば「錯覚に陥らないための予防薬」として役に立つでしょう。
「錯覚」とは、米国発の目新しい経営コンセプトに接したとき、「これを学んで経営に取り入れないと、時流に遅れてしまう」と思い込んで焦ることです。
また、「日本の経営は遅れている」という、本書で繰り返し否定される「根拠なき悲観論」も、一種の「錯覚」でしょう。
本書を読んでおけば、最新流行の経営コンセプトに対して、「待てよ、これって日本企業が昔からやってきたことに過ぎないのじゃないか」というふうに、立ち止まって冷静に考えられるでしょう。
その意味で、本書は「効能あらたかな予防薬」なのです。
岩尾俊兵著/光文社新書/2023年10月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
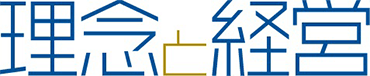


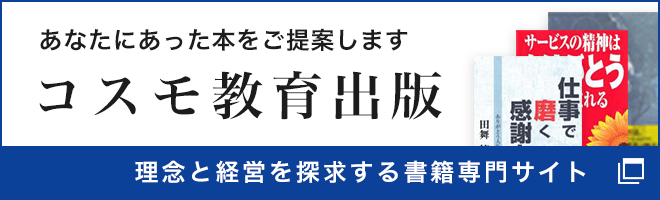





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)