『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第73回/『教養としてのドラッカー 「知の巨人」の思索の軌跡』
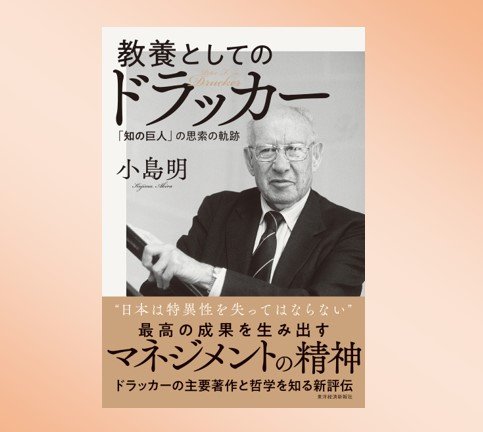
深い親交結んだ著者による力作評伝
「マネジメントを発明した男」と呼ばれ、現代経営学の祖とも言える「知の巨人」ピーター・ドラッカー(1909~2005)――。その名を知らない人は、当連載の読者の中にはいないでしょう。
『理念と経営』でも、ドラッカーをテーマとした記事をくり返し掲載してきました。
「顧客第一」「目標管理」「ベンチマーキング」「コアコンピタンス」など、いまではあたりまえに使われているマネジメントの手法・理念の多くは、ドラッカーが「発明」したものなのです。
しかし、ドラッカーの名、あるいは彼の経営学の一端を知っている人は多くても、思想家としての全体像や生涯について知っている人は少ないのではないでしょうか?
本書は、《「知の巨人」の思索の軌跡》という副題の通り、ドラッカーの思想家としての全体像をコンパクトにまとめた評伝です。
著者の小島明氏は、『日本経済新聞』記者として長いキャリアを積み、同紙の論説主幹なども務めた重鎮ジャーナリスト。慶應義塾大学教授を務めるなど、国際経済学者としても活躍してきました。
氏は1979年に初めてドラッカーをインタビューしてから、最晩年まで取材と親交を重ねてきた人でもあります。
《ドラッカーが来日するたびにインタビューしたり、食事をともにしたりするようになった。〝押しかけ弟子〟として勝手に〝恩師〟と決め、30 余年の交流が始まった》
小島氏自身が傘寿(80歳)の節目を迎えたのを機に、30年以上にわたった巨人ドラッカーとの交流を1冊にまとめる意義も込めて、本書を執筆したのです。長年の友誼を踏まえた、ドラッカーに対する深い理解とリスペクトが、本書には満ちています。
ドラッカーの生涯を辿り、主要著作を読み解くことによって、著者はその全体像を鮮やかに浮き彫りにしていきます。
ドラッカーの著書は『マネジメント』しか読んだことがない――そんな人は日本に多いでしょう(『マネジメント』は日本で大ロングセラーになっています)。
その人たちが「もう少しドラッカーについて知りたい」と思ったとき、本書はそのために読むのにふさわしい、質の高いドラッカー入門にもなっています。
「ドラッカー経営学」の本質を浮き彫りに
ドラッカーが経営学の巨人であることは言うまでもありません。ただ、経営学者としての側面は、思想家ドラッカーの一面にすぎないことは、理解しておく必要があります。
《ドラッカーが組織のあり方としてのマネジメントを研究しだしたのは、社会が「組織社会」となり、現代社会の機能が組織の運営の仕方に依存するようになったためだった。
(中略)
(現代社会は)企業だけでなく、医療、教育、研究などすべてが永続的な存在としての組織で運営され、人々も組織を通じて働き、組織に生活の糧を依存し、組織に機会を求めるようになり、あらゆる組織がマネジメントを必要とするようになった》
本書にそうあるように、ドラッカーの視点は「社会をよりよくする」ことにこそ向けられていて、マネジメントはそのための手段でした。
「経営者のバイブル」とも呼ばれる主著『マネジメント』も、《目先の利益をあげることを期待するようなノウハウを説いたビジネス本》ではありません。
それは《企業だけでなく、大学、病院、NPOなど、さまざまな組織のあり方、運営の仕方について情熱をもって説いている》書なのです。
本書の中に、著者の小島氏が一度だけドラッカーに叱られたという、印象的なエピソードが紹介されています。
《「ドラッカーさん、あなたはこの問題についてエコノミストとしてどう思いますか?」と訊ねたときだった。
「コジマさん。いまエコノミストと呼んだね。私は断じてエコノミストではない」
「では、あなたのエコノミストの定義はなんですか?」とたたみかけると、「エコノミストはフィギュアマン(数字を扱う人)で、私は数字ではなく人間を見る。社会を見る」という返答だった》
ドラッカー経営学も、目先の利益を追いかけるためのものではなく、人間を幸福にし、社会をよりよくするための知恵の集大成なのです。
《利益は、個々の企業にとっても、社会にとっても必要である。しかしそれは、企業や企業活動にとって、目的ではなく条件である》
《企業の目的は、それぞれの企業の外にある、企業は社会の機関であり、その目的は社会にある。企業の目的の定義は一つしかない。それは顧客の創造である》
……と、ドラッカーは述べています。
本書には、そのようなドラッカー経営学の本質が浮き彫りにされています。
未来を見通す慧眼に驚く
ドラッカーは、時に「未来学者(フューチャリスト)」と呼ばれました。
《ドラッカーは「私は予測しない」と繰り返し述べながらも、『見えざる革命』や『新しい現実』で的確な時代分析を行い、それは見事に的中した未来予測にもなった》
本書を読むと、ドラッカーの未来を見通す慧眼に驚かされます。
たとえば、1989年、ドラッカーが80歳のときに上梓した『新しい現実』では、2年後に起きたソ連(現ロシア)の崩壊が予見されているばかりか、それによってソ連の対ヨーロッパ関係が根本的に変わり、やがては軍事侵攻につながる可能性も否定できない、としています。つまり、ロシアのウクライナ侵攻を、すでに予見していたとも言えるのです。
また、1939年、ドラッカーが29歳のときに刊行された最初の単著『「経済人」の終わり』では、《ドイツのナチスが同じく全体主義のソ連のスターリンと手を組む可能性や、ユダヤ人虐殺の可能性》も予測していました。《当時、だれもが、そんなことはないという受け止め方だったが、現実にそれが起こった》のです。
ドラッカーはドイツ時代、新聞記者としてヒトラーやゲッベルス(ヒトラーの右腕)に何度もインタビューをしており、それも踏まえての予測でした。ドラッカーはナチスの弾圧を逃れてドイツから英国に渡った(その後に渡米)人であり、ナチスと戦った言論人の1人でもあります。
また、ドラッカーは1976年刊の『見えざる革命』で、いま世界を覆っている少子高齢化の衝撃をいち早く予見し、警鐘を鳴らしていました。
そのような慧眼の持ち主であったからこそ、ドラッカーの諸作はいまも時代の羅針盤としての価値を失わないのです。
ドラッカーが日本に寄せた、熱い期待
ドラッカーは日本の古美術に造詣が深く、水墨画などの日本画コレクターとしても知られていました(ドラッカーの没後、彼が集めた日本画197点が日本企業によって買い取られ、現在では千葉市美術館に寄託・所蔵されています)。
日本画への関心から日本に目を向けたドラッカーは、明治維新や戦後日本の急速な復興を高く評価しました。
「日本との出合いは運命的な出合いであり、日本は私にライフワークを与えてくれた〝恩人〟だ」と、彼が言っていたことが本書に明かされています。
日本をこよなく愛したドラッカーは、日本企業に対するアドバイスを、著作などを通じて折々に行っていました。
彼の発言の変遷を見ていくと、日本に対する熱い期待とリスペクトが、ある時期から失望に変わっていった様子が伺えます。
《戦後の日本の高度経済成長、経済大国化をいち早く洞察したドラッカーは1960年代、 70 年代の日本の企業家精神とイノベーションへの意欲に注目し評価したが、1990年代に入ってからの日本はその当時とまったく変わってしまった。1990年代半ば以降の発言には、彼が日本に対して不甲斐なさを感じていたことが実感される》
日本経済に「失われた30年」をもたらした変質に、ドラッカーはいち早く気付いていたのです。
また、著者によるインタビューの中で、ドラッカーは「日本が弱みだと思い込んでいる高齢化、環境制約、エネルギー・資源不足なども克服できる。日本の『強み』である技術力をそうした課題に組み込めばいい」と希望に満ちた発言をしていますが、その後の日本が彼の期待に応えられているか、大いに心もとないところです。
中小企業経営者にとって、本書の内容は、日々の経営に即役立つようなものではないでしょう。
しかし、「マネジメントの父」ドラッカーの思想と生涯を深く知ることで、『マネジメント』を筆頭とした彼の著作に対する理解も深まるはずです。
また、『教養としてのドラッカー』という書名のとおり、ドラッカーの思想を概略的にでも理解しておくことは、21世紀の経営者にとって必須の教養でもあります。その意味でも一読の価値がある、書くべき人が書いた力作評伝です。
小島明著/東洋経済新報社/2023年5月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






