『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第66回/『世界最高の伝え方』
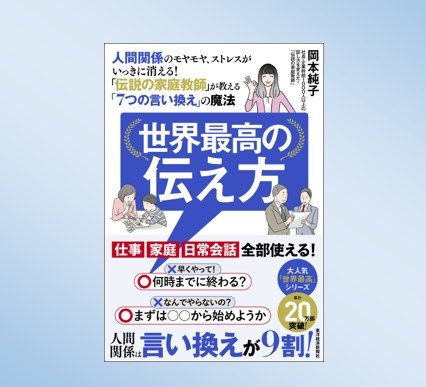
経営者の「伝える力」向上のために
著者の岡本純子氏は、「エグゼクティブ・スピーチコーチ&コミュニケーション戦略研究家」という肩書を持っています。
これだけだとよくわかりませんが、要は、大企業のリーダー、政治家、官僚など、「エグゼクティブ」と呼ばれる人たちに、スピーチやプレゼンなど「人の心を動かす話し方」の要諦を教えるプロのコーチなのです。これまでに、1000人を超えるビジネスパーソンへのプライベートコーチングに携わってきたと言います。
そのような仕事をするにふさわしい経歴の持ち主でもあります。
『読売新聞』の経済部記者として活躍したあと、電通のPRコンサルタントとして経営者向けメディアトレーニングやプレゼンコーチングに携わり、その後に渡米して、ニューヨークでグローバルスタンダードのコミュニケーション術を本格的に学んだ人なのですから。
岡本氏は、多くの研修・講演活動に携わる一方、自らが築き上げたコミュニケーション術を開陳した一般向け著作を続々と刊行しています。
そのうち、『世界最高の話し方』『世界最高の雑談力』(共に東洋経済新報社)は、2冊合わせて20万部を超えるベストセラーになりました。
今回取り上げる『世界最高の伝え方』は、今年(2023年)6月末に刊行されたばかりの、『世界最高』シリーズの第3弾。タイトルの通り、物事の「伝え方」に焦点を当てた内容です。
ビジネス書ですが、親から子へ、教師から生徒への「伝え方」にも応用可能であり、子育て本・教育書として読むこともできます。
ただし、著者の経歴から考えて、メインターゲットは経営者など、企業で人材育成に携わる人たちでしょう。
だからこそ、当連載で取り上げるのです。経営者にとって大切な「(社員に対する)伝える力」を向上させるために、本書は大いに役立つはずですから。
「以心伝心」幻想を捨て、科学的アプローチを
日本人には、「『伝え方』を努力によって磨き上げる」という発想そのものが乏しい面があります。
それは、日本社会に「以心伝心」幻想ともいうべきものが蔓延しているからでしょう。「親しい間柄なのだから、何も言わなくても気持ちは伝わっているはずだ」と考えてしまう幻想のことです。
しかし実際には、上司と部下、友人同士はもちろんのこと、親子であれ夫婦であれ、言葉にして伝えなければ伝わらないことのほうが圧倒的に多いのです。
著者は、アメリカでコミュニケーションについて学ぶ中で、日本人に「伝え方」教育が著しく不足していることに気づきました。
《アメリカで学んでわかったのは、 コミュニケーションは脳科学や心理学、人類学などから導き出された「正解」や「方程式」がしっかり存在する「科学」であるということでした。
日本では「コミュニケーション力=生まれつきの才能」と思われがちですが、海外では多くの人が、幼少期から学校で 1 から 10 までを学ぶスキルなのです》
本書はそのような認識を踏まえ、日本の大人たちに、科学的アプローチに基づいた正しい「伝え方」をレクチャーする内容なのです。
「伝え方」についての本はすでに汗牛充棟ですが、類書の中には科学的アプローチが乏しく、著者の経験だけに基づくものが少なくありません。
それに対して、本書の特徴は、著者のアドバイスにきちんとした科学的エビデンスがあるところです。それらのエビデンスは、本文の随所にさりげなく示されています。
たとえば、ほめることと叱ることのバランス配分に言及した箇所では、次のようにエビデンスが示されています。
《「ほめる頻度が高すぎると、ほめ言葉の価値が下がって、誠意が感じられないのではないか」、つまり、「ほめすぎると(相手が)慣れて、効果がなくなるのではないか」という心配には根拠がないことがわかっています。
シカゴ大学の教授らの研究では、「1週間にわたって 1 日 1 回ほめられた人は、日を追うにつれてその効果が下がるかと予想されたが、毎日同じように効果があった」と報告されています》
《「ポジティブとネガティブのフィードバックの最適割合」を科学的に証明しようとする研究も多々あります。
2005年、心理学者のマーシャル・ロサダ氏とノースカロライナ大学教授のバーバラ・フレドリクソン氏は、人間が幸福を感じる転換点は、「ポジティブな感情とネガティブな感情の比が 2・9013 のバランスにある」と結論付ける論文を発表し、ポジ 3:ネガ 1 の「ロサダ比」として話題になりました》
部下などへのフィードバックは「ほめる」に基本を置き、「叱る」などのネガティブ・フィードバックを3分の1以下に抑えるべきである(この比率については諸説あります)ことが、エビデンスとともに示されているのです。
あらゆる場面に応用可能な「7つの言い換え」
そのような科学的アプローチを土台に据えつつ、著者は上手な「伝え方」の極意を、シンプルにわかりやすく示していきます。
《人は生きていくうえで、さまざまな「伝える」場面を経験します。
あいさつ、雑談、会話、会議、商談、報告、指示、指導、説明、説得、プレゼン、スピーチ……。
目的や内容は多岐にわたるわけですが、シチュエーションは違っても、じつはそのコツはすべてのコミュニケーションに共通しています。
この本は、そんな全方位で役立つテクニックを網羅し、徹底解説した「伝え方の完全マニュアル」です》
著者の言う、あらゆる場面に応用可能な基本の「伝え方」は、「7つの言い換え」と銘打たれたものです。
《(1)「大」「抽象」を「小」「具体」に(Small/Specific)
対象範囲が大きくて、抽象的な言葉を、範囲が小さく、個別具体的な言葉に》
《 (2)「命令」を「提案」に(Proposal)
一方的で、高圧的な命令を、相手が気持ちよく動ける提案や問いかけに》
……などの7つの言い換えルールから成るもので、各ルールの具体的内容は本文で詳しく解説されています。
その「7つの言い換え」を原則として頭に叩き込んでおけば、あらゆる場面での「伝え方」がおのずと改善されていくように、全体が構成されているのです。
これからの時代のリーダー論でもある
本書は「伝え方」を改善するための実用書ですが、リーダー論として読むこともできる内容です。
著者は、有無を言わさず上から押さえつける強権型のリーダーシップが、いまや完全に時代遅れであることをくり返し強調しています。
《「上→下」ではなく「対等な立場」に立ち、相手を尊重するコミュニケーションが、これからのスタンダード》
《「新時代リーダー」はみなさん、「話を聞くこと」や「対話」「チーム」を大事にしています。
まったくエラぶる様子がなく、周囲の人に聞いても、「気さく」「話しやすい」「謙虚」という声が聞こえてきます。
サッカー日本代表の森保一監督や、WBC で日本代表を率いた栗山英樹監督なども、「チーム重視」「全員がリーダー」と口にするように、「共感・対話型」のリーダーシップを発揮していましたよね》
つまり、「これからの時代のリーダーはどうあるべきか」を、コミュニケーション学の側面から示した書でもあるのです。
その意味でも、中小企業経営者にぜひ読んでほしい一冊です。
岡本純子著/東洋経済新報社/2023年6月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






