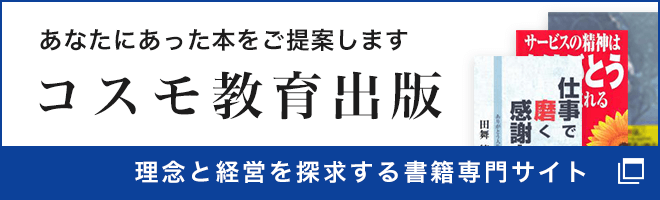『理念と経営』WEB記事
巻頭対談
2023年 7月号
社員をワクワクさせる “大きな物語”を語れ

産業技術総合研究所 最高顧問 中鉢良治 氏 ✕ 一橋大学名誉教授 野中郁次郎 氏
ソニー、産業技術総合研究所(産総研)のトップを歴任してきた中鉢良治氏が、経営者として強く影響を受けてきたのが「知識創造理論」である。暗黙知と形式知の相互作用から生まれるイノベーション創出のプロセスを、実際の現場で体験してきた中鉢氏と、その提唱者たる野中郁次郎氏との“知的コンバット”から浮かび上がった「経営者の条件」―。
現場を経験してわかった、「知識創造理論」の真価
野中 中鉢さんとは40年以上前からの知り合いです。初めてお会いしたのは、私が講師を頼まれた企業研修の席でしたね。
中鉢 そうです。その研修の課題図書が野中先生の『3Mの挑戦』(清澤達夫との共著/日本経済新聞社・87年刊)でした。イノベーションをテーマにした内容にも感銘を受けましたが、3Mという企業にも不思議な「縁」を感じました。
3Mは元々鉱山会社で、鉱山業の衰退で(鉱物を塗布した)サンドペーパーの会社になり、その後は磁気テープ・メーカーの名門になりました。私も大学では鉱山学を学び、ソニーで磁気テープの開発に携わっておりました。
野中 3Mという企業の歩みが、中鉢さんの技術者としての歩みと重なったのですね。
中鉢 そうなんです。そして、研修での講義を聞いてすっかり野中先生のファンになり、その後はたくさんのご著書を拝読しました。私の自宅の書斎には先生のご著書がズラリと並んでいて、棚一段に収まりません。経営者としても強い影響を受けました。
野中 光栄です。私が「知識創造理論」を完成させたのは1990年代ですが、そのプロセスでは、80年代にアメリカで3Mを視察したことも一つの契機になりました。
3Mの本社では社員たちが楽しそうに、自由にワイワイと仕事をしていました。3Mは付箋の「ポスト・イット」を生み出すなど、イノベーションの会社として名高いですが、その原動力が自由にワイワイと共感し合う企業文化の中にあると感じました。私の「知識創造理論」は個人の話じゃなくて、組織体による集合知のイノベーション理論です。だからこそ、共感から始まるのです。
中鉢 よくわかります。私もイノベーションの会社として知られるソニーで長年働き、商品開発などを手がけてきましたが、私一人で成し遂げたことは一つもありません。イノベーションは常に「仲間たちと一緒になって、現場で起こす」ものでした。世間はとかく、「一人の天才発明家が起こすイノベーション」というイメージを抱きがちですが、そのようなイノベーションは現実にはほとんどないような気がします。
野中 その通りです。知識創造理論の枠組みとなる「SECIモデル」は「共感」が起点になっていますから。デカルトの「我思う、故に我在り」という言葉が象徴するように、「思う・考える」は一人でできますが、共感は他者との関係から起きるので、一人ではできません。最低二人の人間がいなければいけない。その共感のプロセスがあってこそ、そこにイノベーションを醸成する環境も整うというのが、私の知識創造理論なのです。
中鉢 私はまだ若いころに野中先生の知識創造理論に触れて、正直、最初はよくわかりませんでした。でも、私自身がソニーでイノベーションのプロセスに携わる経験を積み重ねていったら、「ああ、そういうことか」と納得できました。SECIモデルの一つひとつのプロセス(共同化・表出化・連結化・内面化)が、商品開発の現場に即して腑に落ちたのです。そのときやっと、知識創造理論のすごさが理解できました。組織が暗黙知と形式知のダイナミックな相互作用によってイノベーションを生むプロセスが、理論化・体系化されていると感じたのです。
野中 ソニーを率いた中鉢さんにそう言っていただくと、うれしいですね。
「共感力」のないリーダーに部下はついていかない
野中 私のSECIモデルは、フッサール(オーストリアの哲学者)が創始した「現象学」と親和性が高いのです。現象学の眼目は「現象学的還元(エポケー)」「志向性」などがありますが、なかでも重要なのが「相互主観性(共感)」です。共感が起点となり知識創造がなされるプロセスでも、対話する者同士が一体化するような経験が不可欠です。平たく言うなら、赤子が母親に対して抱くような一体感― それが対話相手との間に感じられるようになってこそ、イノベーションが生み出される環境が整うのです。
中鉢 企業で同じプロジェクトに関わる者たちは基本的に赤の他人ですから、その間に母子のような一体感が生まれるまでには、共感の積み重ねが必要になるわけですね。出身地も過去の経験もバラバラですが、共通経験を積み、何度も酒を酌み交わして語り合ううち、共感が深まっていく。
野中 そうですね。私の用語で言う「知的コンバット」―全身全霊で向き合い、互いの主観をぶつけ合う徹底した対話を積み重ねるうちに、そうした共感が生まれるのです。
一口に「共感」と言っても、いろんなレベルがあります。英語の「シンパシー(sympathy)」と「エンパシー(empathy)」はどちらも「共感」と訳せますが、シンパシーには「同情」に近いニュアンスがあって、自分の立場から相手を思いやる共感を指します。つまり、そこには相手との一体感はない。それに対してエンパシーは、相手と一体化する全身全霊の共感を意味します。知的コンバットを重ねて生まれる共感は、シンパシーではなくエンパシーなのです。
中鉢 私は元々エンジニアですが、仕事とは関係なく心理学が好きで、独学で本を読み漁ったり、心理学の学校に通ったりしました。そうして学んだことの一つに、カール・ロジャーズという米国の心理学者が作った心理療法があります。それは「共感的理解(Sympathetic Understanding)」を重んじる方法で、心を病んだ人に対してそれを行うと癒やすことができる。つまり、人は深く共感されるだけで癒されるわけですね。いまのお話で、そのことを思い出しました。その場合の共感も、やはりエンパシーなのだと思います。
私はソニーの社長や産総研理事長を経験して、大組織のリーダーも務めてきたわけですが、その経験を通じて思うのは、リーダーにとって何より大切なのは「人間力」だということです。経営者としてどんなに優秀でも、人間として尊敬できないリーダーには部下はついてきません。そして、「人間力とは何か?」と考えてみると、その大きな要素の一つは「共感力」だと思うのです。相手の心を深く理解し、一体感を醸し出す力……それが欠落している人はリーダー失格ではないでしょうか?
野中 そう思います。私には『共感経営』(勝見明との共著/日経BP)という著書もありますが、一流の経営者やプロジェクトリーダーは例外なく優れた共感力の持ち主です。そして、共感は社員と心を結ぶだけではなく、企業としてイノベーションを起こすためにも不可欠なのです。
構成 本誌編集長 前原政之
撮影 中村ノブオ
本記事は、月刊『理念と経営』2023年 7月号「巻頭対談」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
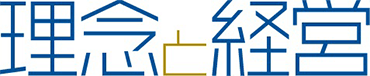


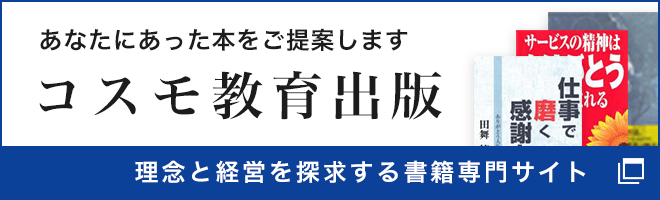





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)