『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第61回/『ゆるい職場――若者の不安の知られざる理由』
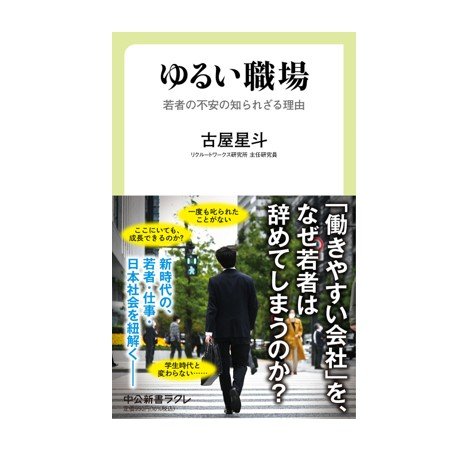
若者の職場環境が大きく変わった
『理念と経営』2023年7月号に、《なぜ、若者は「ゆるい職場」を去るのか》という4ページの単発記事が掲載されています。
取材・執筆は、大宅壮一ノンフィクション賞受賞作家の稲泉連さん。「リクルートワークス研究所」主任研究員・古屋星斗(ふるや・しょうと)さんへのインタビューです。
古屋さんの著書『ゆるい職場――若者の不安の知られざる理由』の内容を踏まえたものであり、そもそも私が同書を読んで企画した記事なのです。
『理念と経営』の記事は、同書のエッセンスを手際よくまとめた内容になっています。
ただ、「ゆるい職場」問題をより深く理解するためには、元になった古屋さんの著書も併読するとよいでしょう。……というわけで、今回は同書を取り上げます。
そもそも、同書の類書はこれまでにもありました。中でも有名なのは、城繁幸氏の『若者はなぜ3年で辞めるのか? ――年功序列が奪う日本の未来』(光文社新書/2006年刊)でしょう。
年功序列型の生涯雇用で成り立っていた日本の企業社会では、新卒で入った会社に定年まで勤め上げることが一般的でした。そうしたキャリアのありようが平成期に少しずつ崩れ、「最近の若者は、なぜせっかく入った会社を簡単に辞めるのだろう?」という疑問が、中高年を中心に広がっていきました。だからこそ、『若者はなぜ3年で辞めるのか?』はベストセラーになったのでしょう。
では、それから10数年を経て刊行された『ゆるい職場』は、『若者はなぜ3年で辞めるのか?』に屋上屋を架すような内容なのでしょうか? そうではありません。というのも、2006年当時と現在では、若者の職場環境が大きく変わっているからです。
「職場がゆるいから辞める」?
本書に詳述されていますが、《日本の職場環境が2010年代後半以降、5年ほどで構造的な変化を起こしたという事実》があります。
それは、「何となく職場の空気が変わった」などという曖昧な変化ではありません。《2010年代後半に日本の労働法令には様々な改正が行われた》ことによる、まさしく「構造的な変化」でした。
一連の労働法令改正は、「ブラック企業」が2010年代に社会問題化し、企業の新入社員が過労死や過労自殺を遂げる痛ましい事件が相次いだことが背景にあります。
改正の結果、日本の労働環境は大きく改善されました。
残業時間は減り、上司が新入社員を怒鳴りつけるようなパワハラは減りました。労働環境についての情報開示も進んだことから、いわゆる「リアリティショック」(入社前に抱いていた理想と入社後の現実とのギャップに対するショック)も以前より減っています。それ自体は望ましい変化と言えるでしょう。
ところが、若者たちへの聞き取り調査では、労働環境の変化を喜ぶよりも、むしろ戸惑う声が多かったそうです。
《筆者は2021年の年末にかけて、20 社程度様々な業種の大手企業の新入社員に仕事についてのインタビューを実施した。驚くべきことに彼ら・彼女らの多くが語ったのは、「正直言って、余力があります」「ゆるい。社会人ってこんなものなんですね」「学生時代に近くて肩透かしです」といった〝持て余し感〟であった》
そして、労働環境が改善されるにつれ、会社を辞める若者が減ったかといえば、むしろ逆でした。
《一般に労働環境の良さと離職率には明確な負の相関があり、環境が良い方が辞めない、と考えるのが普通である。しかし、ここ 10 年ほどの日本全体で考えた場合にはこの法則が当てはまらない。(中略)大手企業の入職3年未満の新入社員の離職率は、2009年卒では 20・5%であったが、2017年卒では 26・5%まで上昇していた(厚生労働省調査)。労働環境が改善されたのに、離職率が上がっているという謎が存在しているのだ》
これが、本書のテーマである「ゆるい職場」問題です。労働環境がゆるくなったのに、辞める若者が逆に増えたのはなぜか? その謎を解明していく本なのです。
「『職場環境がキツイから辞めたい』ならわかるが、『ゆるいから辞めたい』って、ゼイタク言うなよ」と、“気持ちがまだ昭和なおじさん”たちは思ってしまうことでしょう。
しかし、本書を読めば、辞めていく若者たちが「甘えている」わけでも「ゼイタク言っている」わけでもなく、切実な不安から行動していることがわかります。
「不満」から「不安」へのシフト
謎を解くためのキーワードは、「不満から不安へのシフト」です。
《私はこの「職場がゆるくて辞める」状況を、「不満型転職から、不安型転職へ変わった」と理解している。データからは不満は相対的にはかなり減少していると言って良いだろう。そもそも不満の源泉になってきた、職場環境や上司との関係性による負荷、労働時間の長さなどは相当程度改善されたことは明らかで、リアリティショックも低減している。
(中略)
会社や職場への「不満」はなくなりつつある。しかし問題は「不安」が高まっているということであり、特にキャリア不安にその源泉があることはすでに指摘した。これが、職場が嫌で上司と合わないことが「不満」で転職する不満型転職から、不安型転職へと変化していると言った現状である》
かつて、若者たちが辞める理由は会社に対する「不満」でした。それがいまは、今後のキャリア形成に対する「不安」が最大の理由になっているというのです。
若者たちから聞いた代表的な声を踏まえて、次のような「不安」の例が挙げられています。
《「この職場にいると転職できなくなるのではないか」
「自分の会社でしか生きられない人間になってしまう」
「同年代と比較して活躍できるようになるイメージがわかない」
「会社の仕事を続けていると、キャリアの選択肢が狭まるように感じる」 》
「不満」なら、上司が飲みに連れて行って「お前が頑張っていることはよくわかっている」などと共感を示したりすれば、ある程度は解消できました。
しかし、「不安」はそんなことでは解消されません。上司にいくら共感してもらい、褒めてもらったところで、将来のキャリア形成(=この会社を辞めたあと、やっていけるかどうか?)には1ミリも関係ないからです。
《企業や上司には、若手のキャリア不安をいかにして解消するのか、というこれまでに日本企業が直面したことのない新たな課題が発生しているのだ》
……と、著者は指摘します。
「横の関係」で育てるという処方箋
職場環境が改善されることでクローズアップされてきた、若者たちの将来への不安や、成長実感の乏しさという不安……それを解消させるために、時代の流れを逆回転させて、昔のような「キツイ職場」に戻ることは不可能です。
むしろ、「ゆるい職場」化は今後ますます進んでいくでしょう。
では、経営者・管理職側はどうすればよいのか? 本書の後半では、そのための具体的処方箋が、実例とともに挙げられています。
《突破口になりそうな事例が生まれている。筆者が注目しているソリューションのひとつに、「横の関係で育てる」がある。
一部の外食チェーン店で取り組まれている「新入社員だけがスタッフを務める研修店舗」はその具体例であり、実際に離職率が急激に下がったという報告もある。(中略)最も大きなメリットは、この育成手法がまさに「関係負荷なく質的負荷を与える」方法であるということだろう》
「関係負荷」とは「上司の指導が厳しい」など、職場の人間関係に起因する負荷であり、「質的負荷」とは仕事内容の質的な難しさによる負荷です。
「ゆるい職場」になって関係負荷が減ったのはよいことですが、それに比例して質的負荷も下がってしまい、若手社員は成長実感が得にくくなりました。
しかし、「新入社員だけがスタッフを務める研修店舗」には上下関係がないので、関係負荷もありません。一方、新入社員だけで現場を切り盛りしていくため、質的負荷はかなり高くなります。
《これを上下関係で育てる、ではない新たなアプローチとして、「横の関係で育てる」と呼びたい。
一部業種だけの話でしょ、と片付けるのはあまりに早計だ。「横の関係で育てる」類似の取組が実は社会のそこかしこで同時多発的に発生しているのだ》
外食産業以外の中小企業でも、上司が介入せず、若者たちだけで取り組むプロジェクトには、さまざまな形があり得るでしょう。
以上は、本書に挙げられた、若者が「職場がゆるくて辞める」ことを避ける処方箋の一つです。ほかにも多くの有益な提言が詰め込まれています。
本書に挙げられたデータや事例の多くは大企業のものですが、《その理由は人事労務を含めた環境改善、コンプライアンス重視の動きが、株式市場をはじめとする社会的責任が大きい大手企業から開始されているためである》と、著者は説明しています。
当然、その動きは中小企業にも波及しつつあります。したがって、本書の内容はすべて、中小企業経営者にとっても他人事ではありません。
じっさい、「労働環境を改善したのに、若手の離職率が下がらない」と悩んでいる中小企業経営者も少なくないはずです。
その謎の少なくとも一端は、本書が解き明かしてくれるでしょう。
古屋星斗著/中公新書ラクレ/2022年12月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






