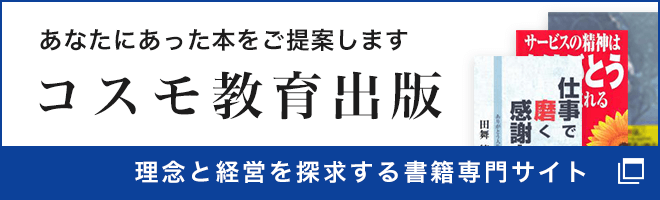『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第59回/『日本の電機産業はなぜ凋落したのか――体験的考察から見えた五つの大罪』
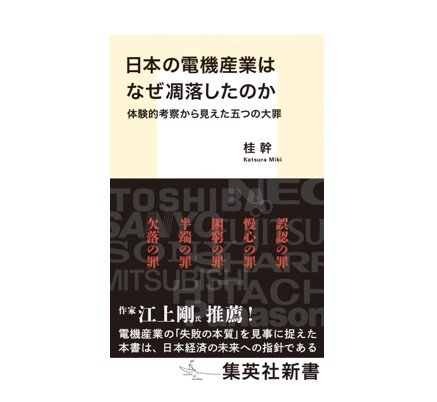
当事者自らが凋落の要因を考察
昭和後期に日本経済の発展を牽引したのは電機産業でした。家庭用VTR、ウォークマン、薄型テレビ、家庭用ゲーム機など、画期的な日本製品が次々と生まれ、グローバル市場を席巻したのです。
本書の一節に言うとおり、《技術大国ニッポンの称号は、電機産業が築いたと言っても過言ではない》でしょう。
ところが、平成の30年間で、花形だった日本の電機産業は見る影もなく凋落していきました。本書はその背景要因を詳細に分析した内容です。
「日本の電機産業の凋落」は人々の関心が強いテーマであるため、類書も少なくありません。しかし、本書には類書にない大きな強みがあります。著者が、凋落プロセスの只中に身を置いた当事者だったことです。
著者の父親(桂泰三氏)は、かつてシャープの副社長を務めました。また、著者自身は日米両国のTDKに約30年間勤務し、同社の米国子会社の副社長を務めた経験を持ちます。
シャープが電機産業の隆盛と凋落を象徴する大企業であることは、いうまでもありません。また、著者はTDKの記録メディア事業部門に所属し、カセットテープが稼ぎ頭だった時代と、逆に赤字で撤退に至った時代を、両方経験しました。
父子二代にわたって電機産業の盛衰を経験したことを踏まえ、当事者としての視点から分析した書なのです。副題のとおり「体験的考察」であり、学者や評論家が他人事として失敗を分析するのとはわけが違います。
《同じ過ちを繰り返さないためには、現実を直視し、当事者として過ちの原因を真摯に探り出すほかない。一つの事業に従事する中で私自身が犯した失敗を素直に顧み、未来への警鐘を鳴らすことが本書の目的であり、私たち平成世代に残された使命だと信じている》
「はじめに」にそうあるように、本書を著すための分析作業は、心の傷の瘡蓋を剥がして血を流すような、苦痛を伴うものだったことでしょう。だからこそ切実で読み応えがあるのです。
「イノベーションのジレンマ」も浮き彫りに
副題に言う「五つの大罪」とは、著者が日本の電機産業衰退の要因を腑分けしたものです。
「誤認の罪」「慢心の罪」「困窮の罪」「半端の罪」「欠落の罪」から成り、それぞれの意味が、1~5章の各1章を割いて説明されていきます。
たとえば、第1章「誤認の罪」では、電機産業がデジタル化の波にうまく乗れず、先進各国に追い抜かれていった理由が分析されます。
《さまざまなイノベーションを起こしたはずの日本の大手電機メーカーが、デジタル化が進むにつれてその存在感を失っていく。本来、技術力が高ければ、デジタル化にともなってますます飛躍しそうなものだが、現実は弱体化していったのだ》
その背景にあったのは、「画期的な簡易化」というデジタル化の本質を見誤った「誤認の罪」だと、著者は指摘するのです。
デジタル化が進むほど、「画期的な簡易化」を目指す競争が激化していきました。
ところが、日本企業はその本質を誤認し、高付加価値のハイスペックな製品を開発することで勝とうとした……そこに根本的な誤りがあったというのです。
《技術大国ニッポンとしてのプライドを引きずりながらたどり着いた先は、高品質、高性能、それに高付加価値こそが日本の製造業の強みだ、とする結論だった。利幅の小さな汎用品を大量生産する「製造」ではなく、利幅の大きな付加価値製品を作る「モノづくり」こそが、日本企業に相応しいと考えたのだ》
《高品質、高性能、高付加価値を極めれば競合に勝てると思い込み、より根源的なニーズだった「画期的な簡易化」の提供が疎かになった》
その誤認から生じた失敗の一典型が、《多くの名だたる企業が参加し、鳴り物入りで開発されたブルーレイは、欧米のB2C市場では、まったくと言っていいほど需要がなかった》ことでした。
《そもそもブルーレイはユーザーに新しい簡易化を提供できる技術ではなかったのだから、海外で普及が進まなかったのも仕方がない。テレビ番組や映画を録画するなら、画質は劣るがDVDがすでに存在したし、ハードディスクの大容量化も進んでいた。さらに言えば、海外では動画配信サービスがすでに広がり始め、何かを個人で録画して保存するという文化さえ廃れようとしていた。それらの市場の変化に目を向けず、ただロードマップを実現したところでブルーレイの需要が生まれるはずもなかった》
ブルーレイの失敗は、「誤認の罪」のほんの一例です。
そのような事例は、平成期の日本の電機産業が「イノベーションのジレンマ」(米国の経営学者クリステンセンが提唱した理論)に陥っていたことを痛感させます。
《イノベーションのジレンマとは、先を行く大企業が、あとから来る企業に足をすくわれる現象のことだ。後発企業は、新しい技術や低コストを武器にシェアの拡大を図る。先行する企業は優れた既存技術や事業に固執するあまり、新しい需要への対応が遅れ、最終的には追い抜かれるわけだ》
本書の第1章「誤認の罪」は、「イノベーションのジレンマ」を説明するために教科書に載せたいほど、典型的な例であり、見事な分析です。
他の4つの「大罪」については説明を省きますが、それぞれ、得心のいく分析がなされています。
電機産業版『失敗の本質』
当連載の第55回では、野中郁次郎先生の『「失敗の本質」を語る』を取り上げました。
野中先生が主著者となった『失敗の本質』(共著/中公文庫)は、旧日本軍が第2次世界大戦前後にくり返した失敗について、組織論的に研究した名著として知られています。
そして、本書『日本の電機産業はなぜ凋落したのか』は、“『失敗の本質』の電機産業版”と評され、いま大きな話題をまいているのです。
『失敗の本質』は、日本軍の特性や欠陥が、現代日本の組織にも“負の遺産”として引き継がれていると捉える内容でした。つまり、日本軍の失敗について企業が学び、同じ轍を踏まないようにすることこそ、同書の眼目であったのです。
同様に本書も、電機産業が平成期に重ねた失敗を分析することで、令和の日本企業(電機産業に限らない)が、同じ過ちをくり返さないための教訓とすることにこそ、著者の意図があるのです。
だからこそ、最後の第6章では、日本企業復活のための提言もなされています。
電機産業の失敗から中小企業も学べる
著者は「はじめに」で、《日本の組織は失敗から学ぶのが苦手なようだ》と指摘しています。一例として挙げられているのが、米国企業では一般的な「エグジット・インタビュー」(出口聞き取り)が、日本企業ではあまり行われていないことです。
「エグジット・インタビュー」とは、退社していく社員に対して、企業側が退職の日に面談し、「改善すべき点」を尋ねるものです。
《自己都合だろうが、会社都合だろうが、社員が会社を去る背後には何がしかの失敗があるものだ。アメリカ企業は、たとえ耳の痛い話になったとしても、その失敗を貪欲に利用しようとするのだ》
日本の中小企業経営者も、もっと貪欲に、自社や他社の失敗から学ぶことを心がけたいものです。
本書は電機産業、それも日本を代表する大企業に的を絞った分析ですが、それでも、彼らの失敗から中小企業経営者も多くのことを学べるでしょう。
桂幹著/集英社新書/2023年2月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
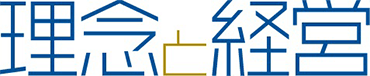


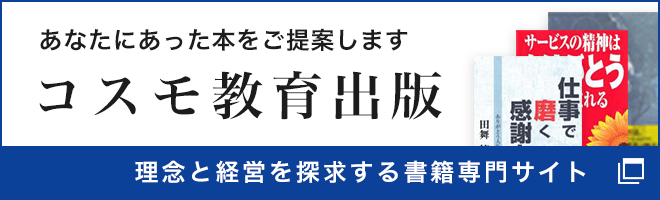





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)