『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第58回/『誰とでもどこででも働ける 最強の仕事術』
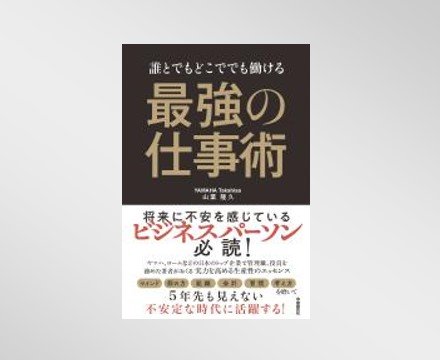
「ポータブルスキル」錬磨のために
著者の山葉隆久氏は、ヤマハ、ローム(半導体メーカー)などのトップ企業で管理職や役員を務めてきた、いわば“筋金入りのビジネスパーソン”です。
とくに、ロームでは常務取締役として、社長に次ぐNo.2を務めました。
また、工学博士号を持つ半導体エンジニアでもあります(加えて、ヤマハ創業家の子孫でもあるそうです)。
約40年のキャリアを通じて計6社の大企業に在籍し、一社員から経営層まですべての階層を経験してきた山葉氏は、会社員の仕事のあるべき姿を知り尽くした人と言えるでしょう。
その山葉氏の初の著書である本書は、タイトルの通り「仕事術」本です。
自らの経験と、これまでに出会った「できる人」たちが身につけていた共通のスキルから抽出した、“生産性向上の極意”を開陳しています。
一口に「生産性向上」といっても幅広いものですが、本書では「ポータブルスキル」(業種や職種が変わっても「持ち運び」できるスキル)の錬磨に焦点が当てられます。
それは著者自身が、会社が買収され、それまでの職場を失った経験を持つからこそでしょう。また、日本企業の雇用流動性が昔より高まり、ビジネスシーンの変化も激しくなった現在、一つの企業や業種の枠内だけで通用するスキルは、常に陳腐化のリスクにさらされています。
だからこそ、これからの時代は、ポータブルスキルを高めることが重要なのです。書名の『誰とでもどこででも働ける~』は、そのことを指しています。
本書の主要対象読者として念頭に置かれているのは、企業のミドル層、年齢的には40代くらいであるようです。
とはいえ、それ以外の層には不要というわけではありません。紹介されているスキルアップ法の多くは普遍的で、若手にも経営者にも有益だからです。
また、「リスキリング」という言葉は文中に使われていませんが、本書はビジネスパーソンのリスキリングにも生かせる内容と言えます。
「机上の空論」は一切なし
本書は、序章・終章も含めて全6章で構成されています。
そのうちの序章《買収されて分かった「できる」人の働き方》は、著者が所属していたヤマハの半導体工場が、ロームに買収されたときの体験談です。
続く第1章《生産性の高い働き方を磨き続けるマインド10か条》は、これからの時代に《70歳まで働く》ためには生産性向上がなぜ重要かが、公的機関のデータを駆使して整理されています。
その2つの章にも、もちろん読む価値はあります。とくに、M&Aが増えた昨今、序章の体験談はM&Aされた側からの“生の証言”として、貴重なものです。
ただし、「手っ取り早くスキルアップ法を知りたい」と思う向きは、序章と1章を飛ばして、第2章《誰とでもどこででも働ける生産性3つのスキル》と、第3章《日々の習慣を見直して生産性を上げる7つのルール》から読んでもよいでしょう。
というのも、この2つの章こそ本書のコアであり、書名の『誰とでもどこででも働ける 最強の仕事術』が開陳されたパートだからです。
《「どこでも求められる人」「できる人」「生産性の高い人」に近づくためのスキルを2章で、普段の振る舞いや考え方を3章で紹介します》(「はじめに」)とあるとおり、2つの章はワンセットになっています。
この2~3章が素晴らしいのは、現場に無知な一部の経営学者や評論家が振りかざすような「机上の空論」が一つもないこと。
紹介されるスキルアップ法のどれを取っても、著者自らの経験や見聞に裏打ちされており、効果がある程度“立証”されたものばかりなのです。
スキルの普遍的な本質を語る
仕事のスキルには、普遍的なものから個別的なものまでさまざまあります。そのうち、本書の第2章は、どの企業、どの業種にも当てはまる普遍的スキルに的を絞って紹介しています。
それは、《限られた時間で最大の成果を上げるためのスキル》であり、会計スキルのエッセンスであり、他の社員と差別化するための《自分だけのスキルの磨き方》です。
そこで語られるのは、小手先の仕事術ではなく、ポータブルスキルの本質を衝いたものなのです。
たとえば、《限られた時間で最大の成果を上げるためのスキル》の項では、仕事で壁にぶつかったときの対処法の要諦が解説されます。それは、《悩む時間を限りなく短く》するために、《悩む状態から、考える状態に、速やかにシフトしよう》とするものです。
《考えるとは、仮説が立てられて、その検証に向かって行動することです。
この切り替え手段として、つまり仮説を立てる手段として、上司や話を聞いてくれる人に相談する。自ら調査する。ここが大事です》
このように、本書の2~3章では、スキルのレイヤーを上げ、普遍的な本質のみがずばりと語られているのです。
将来の“シニアの仕事術”も
そして、終盤の第4章《働ける内は働きたい! 将来の選択肢を増やす6つの考え方》では、定年退職後の“シニアの仕事術”が語られています。
「人生100年時代」と言われるいま、「仕事術」本もシニア層を意識せざるを得ません。
著者自身がすでにシニア層(1959年生まれ)であるため、4章の記述も、実体験に裏打ちされたヴィヴィッドな内容になっています。
読者がミドル層であれ、あるいは若手であれ、将来の定年退職後をある程度見据えておくことは大切です。4章はそのために役立つでしょう。
中小企業経営者にも有益な書
本書は、「仕事術」本としてオーソドックスな作りと言えるでしょう。奇をてらったところがない分、派手さはあまりないものの、内容は濃密な一冊です。
当連載は「今週の経営に役立つ一冊」であり、主に中小企業経営者を読者対象に設定しています。“社員向け”である本書をあえて取り上げたのは、中小企業経営者にも有益な内容だと考えたからです。
第1に、本書には、著者が管理職・役員を務めた一流企業のマネジメントのエッセンスが、巧まずして詰め込まれています。中小企業経営者にとって、本書は大企業の経営手法の一端を学べる内容でもあるのです。
第2に、社員一人ひとりが生産性を高めるための「教科書」である本書は、中小企業の社員教育にも生かせるでしょう。
経営者が本書で学んだ「仕事術」を社員に教えるもよし、社員に本書を読ませるもよしです。
山葉隆久著/自由国民社/2023年3月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






