『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第52回/『テックジャイアントと地政学――山本康正のテクノロジー教養講座 2023-2024』
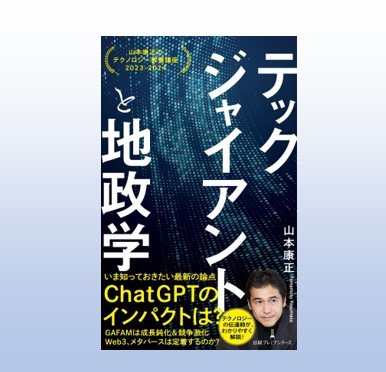
テック関連動向を一望できる
著者の山本康正氏は、京都大学経営管理大学院の客員教授。元は米グーグルで、日本企業のデジタル活用(フィンテックやAIなど)を推進していた経歴の持ち主です。
つまり、シリコンバレーと日本企業の最前線を、両方とも熟知している気鋭の論客なのです。ゆえに「テクノロジーの伝道師」とも呼ばれています。
当連載で以前取り上げた『2030年――すべてが「加速」する世界に備えよ』(ピーター・ディアマンディス著)には、山本氏が長文の解説を寄せていました。私はそれを読んで氏のことを知り、「こんなにすごい論客が日本にいたのか」と驚き、以来注目していたのです。
山本氏は現在、『日本経済新聞』電子版に「教えて山本さん!」というコラムを連載中です。本書は、同連載の2022年掲載分をまとめて加筆・再構成したもの。書名のとおり、Apple、Google、Amazon、Microsoftなどのいわゆる「テックジャイアント」(「ビッグテック」ともいう)各社を中心に、テック関連動向を1年間ウォッチした記録です。
タイトルが『テックジャイアントと地政学』となっているのは、対象となる2022年が、ロシアのウクライナ侵攻や米中の対立激化など、地政学的要因が世界に大きく影を落とした年だったからでしょう。
テックジャイアントの動向について語るにも、地政学的リスクを避けて通れない。逆に、地政学について語るにも、テクノロジー要因を避けて通れない――いまはそんな時期だと言えます。全5章からなる本書の第2章(Part2)が、「テクノロジーが変える地政学」というタイトルであることは、象徴的です。
昨年から今年にかけては、イーロン・マスクがツイッターを買収したり、ツイッターやメタ(旧・フェイスブック)が大量解雇を行ったりと、テック関連の激動が続いた時期でした。
それらの動向を新書一冊で一望できるので、本書は経営者やビジネスパーソンにとって学びの多い内容です。
「ChatGPT」にもいち早く注目
本書の帯には、「ChatGPTのインパクトは?」と大書されています。また、本書のPart1は「ChatGPTが与える衝撃」というタイトルです。
昨年末から今年にかけ、テック関連で最大の話題となった対話型AIサービス「ChatGPT」の、簡便な解説書としても読める内容なのです。
ただし、ChatGPTの解説は全体の10分の1程度と短く、あまり深掘りはされていません。ChatGPTが公開されたのは22年11月後半であり、一般に脚光を浴びたのは23年に入ってからですから、22年分の連載をまとめた本書で扱いが大きくないのは、無理もありません。
むしろ、公開後すぐにChatGPTの革新性に気付き、22年12月のコラムでいち早く取り上げたあたり、さすがの慧眼と言えるでしょう。
ただし、本書はChatGPT以外の部分だけでも、十分に価値があります。テックジャイアントの動向や日本の状況などについて、これほど手際よく解説してくれる本は稀でしょう。
世界の最先端を知るための一冊
テックジャイアントは、米国のみならず、世界の経済や政治にさえ影響を与え得る存在です。その動向をウォッチすることは、日本にいるだけではわかりにくい世界の最先端を知ることにほかなりません。
その意味で、本書はテック関連企業の関係者のみならず、すべての企業経営者にオススメしたい一冊です。
たとえば、日本では今年(2023年)に入ってからもメタバースやWeb3についての解説書が次々と刊行され、ブームが続いている印象があります。ところが、本書を読むと、著者がメタバースやWeb3の未来に懐疑的で、あまり期待を寄せていないことが目を引きます。
《2四半期連続の減収となった同社(メタ社)が初の大幅な人員削減に踏み切った背景には、メタバースへの巨額投資がふるわない現状が大きく影響しているとみられます。日本はまだメタバースへの熱狂の渦中にあるかもしれませんが、米国ではすでにWeb3やメタバース(仮想空間)への熱気は下火になりつつあるからです》
米国と日本にはそのような温度差があり、テックジャイアントの動向を知らなければ、日本で時代遅れの悪手を打ってしまいかねないのです。
また、日本でも大きな話題となったイーロン・マスクによるツイッター買収についても、著者ならではのディープな解説がなされます。
《混迷を深めるツイッターと、苦戦を強いられるメタ。巨大プラットフォームを擁する2社がどのような生き残りの道を探っているのか、まだ明らかになっていません。両社に共通する弱点をひとつ挙げるのであれば、「自社固有のテクノロジーの弱さ」があるのではないでしょうか。(中略)
フェイスブックは 04 年、ツイッターは 06 年、メタ傘下に入った米インスタグラムは2010年にそれぞれ誕生していますが、革新的なテクノロジーというよりも、ユーザーインターフェースによる差別化が急成長を促してきました。テック企業が次なるステージへと進化していくためには、それを支えるための革新的なテクノロジーを開発するか、買収などによって自社に取り込む戦略が欠かせないのです》
……と、そのようにツイッター社の脆弱さに危惧を寄せる一方、イーロン・マスクのリーダーとしての資質に、著者は高い評価を与えています。
《(マスクに)毀誉褒貶はありますが、企業のビジョンを行動で示していくトップの姿に、刺激を受ける方が非常に多くいるはずです。誹謗中傷や批判、炎上を恐れずに率直にコミュニケーションを取ろうとする姿勢や、「こんな騒動のタイミングだからこそ当人の声が聞きたい」という一般ユーザーのニーズに素早いタイミングで呼応していく迅速な行動はなかなかまねできるものではありません。
資金調達の能力が高いCEOは数多くいます。しかしこうしたセンスを併せ持つ人材は極めてまれでしょう。上層部にいくほど業界外の人間とのコミュニケーションが減っていき、顔も見えにくくなる日本企業とは対照的といえるかもしれません》
シリコンバレーと日本を行き来しつつ、最前線を肌で知る著者のこのような分析が読めるだけでも、本書には価値があります。
世界から見た日本の立ち位置がわかる
著者はテックジャイアントの動向を解説する際にも、「この点、日本企業はどうか?」という視点を随所に持ち込んでいます。元が『日経』電子版のコラムなので当然ですが、シリコンバレーから見た日本の立ち位置を常に意識した内容なのです。
その意味で、本書は「米国のテックジャイアントをフィルターとして、日本企業の未来を展望する書」として読むことができるでしょう。そこには、次のような構造も深く関わっています。
《米国のテクノロジー企業が日本に提供するサービスは基本的に米国で試してみて、うまくいったサービスであることが多く、このような経済圏の拡大の動きはまず米国の動きを注意深く見なければ気づくのが遅くなってしまいます。
そのため日本企業の経営者は、まだ日本で提供されていない米国のサービスを意識的に把握しなければなりません。これは特にデジタルとは疎遠だと思い込んでいる業界関係者にとっては重要です》
もはや、「うちみたいな中小企業には、テックジャイアントなんて関係ないから」などと、他人事でいられる時代ではありません。テックジャイアントの今日の動向が、明日の日本企業を大きく左右するのですから。
また、本書は米国の話が中心ではありますが、中国、韓国、ヨーロッパ各国などのテック関連動向にも、随所で言及されています。
その意味で、シリコンバレーのみならず、世界から見た日本の立ち位置がわかる本でもあるのです。たとえば――。
《日本がいま参考にできる国の一つはフランスでしょう。欧州の中でも保守的なことで知られるフランスが近年「フレンチテック構想」という看板を掲げて、企業や組織の垣根を越えて知識や技術を持ち寄る「オープンイノベーション」の促進に向けて本格的に動き出しています。(中略)
10 年代半ばまでのフランスは日本と非常に近い立ち位置にありました。保守的でリスクを回避する傾向が強く、伝統的な教育機関が存在感を持っており、起業する人口は他国に比べて少なかったのです。要するにフランスも数年前まで「出るくいは打たれる」という風土であったため、スタートアップが育たないという日本と同様の悩みを抱えていたのです。
そのフランスですらも大きく変わり始めているのです》
海外の先端動向を概観しつつ、「いま日本企業の経営者が何をすべきか?」にも大きな示唆を与えてくれる好著です。
山本康正著/日経BP / 2023年3月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






