『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第51回/『SF思考――ビジネスと自分の未来を考えるスキル』
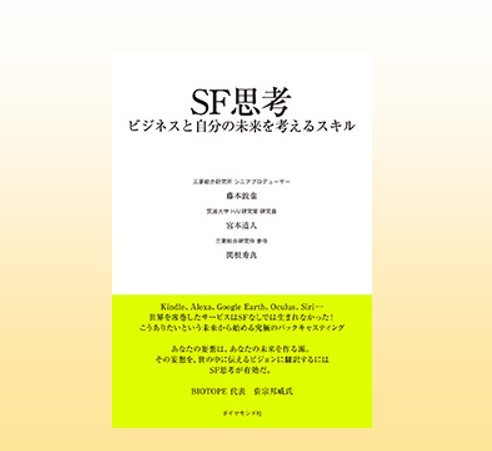
いま脚光を浴びる「SF思考」
一昨年(2021年)くらいから、SF(サイエンス・フィクション)をビジネス/経営的観点から捉える書籍が、続々と刊行されています。また、ビジネス系メディアが「SF思考」についての記事を掲載する例も増えました。
たとえば、以下のような書籍があります(刊行順)。
『SFプロトタイピング――SFからイノベーションを生み出す新戦略』(早川書房/2021年6月刊)
『SF思考――ビジネスと自分の未来を考えるスキル』(ダイヤモンド社/2021年7月刊)
『未来は予測するものではなく創造するものである――考える自由を取り戻すための〈SF思考〉』(筑摩書房/2021年7月刊)
『AI 2041――人工知能が変える20年後の未来』(文藝春秋/2022年12月刊)
『古びた未来をどう壊す?――世界を書き換える「ストーリー」のつくり方とつかい方』(光文社/2023年1月刊)
『「これから何が起こるのか」を知るための教養――SF超入門』(ダイヤモンド社/2023年3月刊)
そこで今回は、「SF思考」が脚光を浴びている背景を探るべく、先鞭をつけた一冊であり、入門書としても好適な『SF思考――ビジネスと自分の未来を考えるスキル』を取り上げます。
「未来を見通す知恵」としてのSF
『SF思考』の帯には、次のような惹句が躍っています。
《Kindle、Alexa、Google Earth、Oculus、Siri……世界を席巻したサービスはSFなしでは生まれなかった!》
この惹句のとおり、いわゆる「GAFAM」の創業者などにはSFマニアが多く、彼らのビジネスにはSFからの影響が強いのです。
《SFは、もはや世界のビジネスパーソンの常識である。
いや、より正確にいえば、SFは、世界の一流のビジネスパーソンの常識である。 ジェフ・ベゾス、イーロン・マスク、ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、ラリー・ペイジ、セルゲイ・ブリン……。彼らの共通点は何か? そう、いずれも世界の長者番付トップ10 にランクインする成功した実業家だ。そして、もうひとつ大きな共通点がある。全員、好きなSF作品があると公言しているのである。(中略)
個人的にSF小説やSF映画を楽しんでいるだけではない。インタビューや著作において、みずからのビジネスに関連づけて具体的な作品やガジェットに積極的に言及している人もいる。ふつうに考えて、世界で十指に入る億万長者のうち6人がSFファンというのは、結構すごい》
KindleやAlexa、SiriやGoogle Earthには、彼ら(「GAFAM」創業者など)がかつてSFで見た世界を実現するために生まれた、という側面があるのです。
さらに、いまや時代を象徴するキーワードとなった「メタバース」(ネット上の仮想空間)や「アバター」(仮想空間上の分身)も、初出は1992年発表のSF小説『スノウ・クラッシュ』(ニール・スティーヴンスン)であり、シリコンバレーのイノベーターたちの多くが同作に影響されています。
米国の先進的企業が、第一線のSF作家をアドバイザーなどとして迎える事例も多く、いまやビジネスの最先端とSFは分かちがたく結びついています。
そうした動きに呼応して、日本の大企業にもSFのビジネス活用は広がりつつあります。冒頭に挙げた一連の書籍は、その反映なのです。
そしてもう一つ、SF思考が注目される背景として、先の見えにくい「VUCAの時代」に突入していることがあります。
先が見えないからこそ、「未来を見通すための知恵」としての「SF思考」が脚光を浴び、ビジネスの世界に取り込まれているのです。
「SF思考」がイノベーションを生む
本書は、SFがビジネス/経営の世界で注目される背景を1章で詳しく解説したうえで、2章から5章で「SF思考」をビジネスに活用するノウハウを紹介しています。
また、6章では企業がプロのSF作家と組んで、イノベーションの土台となる「未来ストーリー」を作っていくワークショップの手順が解説されます。
そして、最後の7章では、三菱総合研究所が2020年に実施した「2070年のSF思考ワークショップ」から生まれた5つの短篇SF小説(5人のプロ作家に執筆を依頼したもの)が、全文掲載されて紹介されています。
米国の大企業のようにSF作家を顧問に迎えたり、三菱総研のように作家とコラボしてSF小説を作るのは、中小企業にはハードルが高すぎるでしょう。
それでも、本書の6~7章は、「SF思考をどうやって現実のイノベーションに結びつけていけばよいか?」の手本として、参考になるはずです。
そしてそれ以上に、2~5章で解説されるSF思考のノウハウは、そのまま経営にも活かせるでしょう。
具体的には、新事業や新製品・新サービスなどを考えるときに、斬新なアイデアを得るための発想トレーニングとして役に立つはずです。
著者たちは、《 ① 予想外の未来社会を想像し、 ② そこに存在する課題を想像し、 ③ その解決方法を想像する》という「三段階の未来予測」にこそSFの特徴がある、と言います。
《「三段階の未来予測」は、小説、演劇、映画など、さまざまなフィクションで使われる「三幕構成」というモデルに近い。ただし、リアリティに軸足を置いたフィクションはSFとは異なり、 ① 現実的な世界での日常→② トラブル発生→③ その解決、と、第一段階からしてきわめて現実的な世界観に立脚している。こうした「リアリティのある物語」に親しんでいる読者なら、SFで斜め上の未来を見せられるだけで、「いや、それはないでしょ」と否定したくなるのもうなずける》
現実に立脚した一般のフィクションとは逆に、いまの現実ではあり得ない「斜め上の未来」から出発するからこそ、SF思考からは斬新なアイデアが生まれます。《SF思考の肝は、現実から虚構に発想を飛ばし、それをまた現実に引き戻して着地させることにある》のです。
《(SF思考では)いまの現実はひとまず忘れて「こうしたい」と思える未来を描く。そして、その未来を起点に、バックキャストで方策を考える。未来を予想するのではなく、創造するのです。イノベーティブな概念は、こうしたアプローチから生まれます》
私たちの発想は、無意識のうちに「目の前の現実」に縛られています。斬新なアイデアをひねり出そうとしても、「それはあり得ないだろう」という現実的判断が足枷となるのです。
《論理的に考えすぎることで、思考の柔軟性、創造力・妄想力に無意識にリミッターが掛かってしまい、現在からの延長線にない意外性のあるもの(一見そんなことはあり得ないと思うようなこと)に対して否定的な反応となってしまうこともあります。
〝想定外〟が当たり前となるこれからの時代においては、いったんリミッターを外してアイデアを創るとともに、そのアイデアをストーリーとして(必要に応じて論理的に) 組み立てることが大切です》
その「思考のリミッター」を一度外すための鍵となるのが、目の前の現実に囚われない「SF思考」なのです。
つまり、イノベーションを生むための発想トレーニングとなるのが「SF思考」なのであり、それは大企業も中小企業も変わりありません。
「SFは苦手だ」という中小企業経営者も少なくないでしょうが、経営者が「VUCAの時代」を生き抜く発想力を身につけるために、本書の一読をおすすめします。
そして、本書に紹介されている優れたSF小説も読んでみるとよいでしょう。即効性はないかもしれませんが、SF思考を身につければ、いつか大きなイノベーションとなって花咲くはずです。
藤本敦也・宮本道人・関根秀真編著/ダイヤモンド社/ 2021年7月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






