『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第47回/『人的資本の活かしかた――組織を変えるリーダーの教科書』
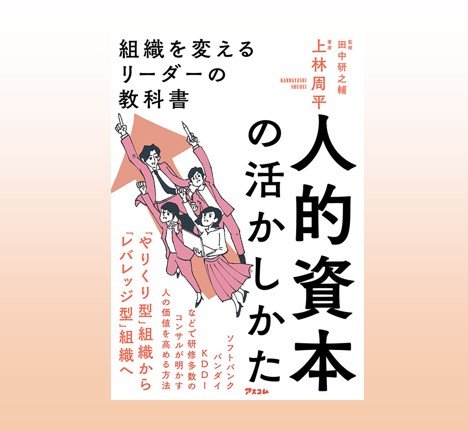
「人的資本経営」の平明な入門書
「人的資本経営」という言葉は、数年前からよく目にするようになりました。
この言葉をタイトルに冠したビジネス書・経営書も、すでに数多く刊行されています。
昨年(2022年)8月には、一橋大学CFO教育研究センター長の伊藤邦雄氏を筆頭とする7名が発起人となり、「人的資本経営コンソーシアム」が設立されました。
このコンソーシアム(共同事業体)には経済産業省・金融庁もオブザーバーとして参加しており、国を挙げて「人的資本経営」の推進がなされているのです。
しかし、「『人的資本経営』という言葉は知っているが、それがどのようなことを指すのか、よくわからない」という人も多いことでしょう。
経済産業省のサイトでは、「人的資本経営」が次のように定義されています。
《人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です》
この定義を見ると、なおさらわかりにくくなります。
なぜなら、昔から「ヒト・モノ・カネ」が「3大経営資源」だと言われてきましたし、「企業は人なり」「人材こそ最大の財産」ということも言われ続けてきたからです。
にもかかわらず、いまさら事改めて「人的資本経営」と強調するのはなぜか? それは、「経営には人材が何より大切だ」というあたりまえの話と、どこがどう違うのか? そんな疑問を感じている人も少なくないはずです。
実を言えば筆者もよくわかっていなかったのですが、本書を読んでようやくスッキリ理解できました。
本書は「人的資本の最大化」のための実用書ですが、同時に、「そもそも『人的資本経営』って何?」という素朴な疑問に、わかりやすく答えてくれる入門書でもあります。
「人的資本」への注目度が高まった背景
全10章からなる本書の第1章「人的資本の世界へようこそ」は、「人的資本経営とは何か?」という疑問に答える入門編です。
通読する時間がない場合、とりあえずこの1章だけを読んでおけば、「人的資本経営」の概要と、それが注目される背景がわかります。
ここで簡単に説明しておけば、背景には「人的資本価値の向上」と「非財務情報への関心の高まり」という2つの要因があります。
「経営には人材が何より大切」であるのは、昔もいまも同じです。
ただし、少子高齢化などによる人手不足の深刻化と、デジタル化の急進展などの変化に対応できる専門人材不足のため、人的資本の価値が昔より大きくなっているのです。
また、近年、財務諸表には表れない潜在的実力や将来性を知るための「非財務情報」の開示が、企業に求められるようになってきました。
その一つとして、「人的資本をどう活用しているか」を、企業が外部に向けて示すように迫る動きが高まっています。たとえば、「国際標準化機構」(ISO)は、2018年12月に「人的資本に関する情報開示のガイドライン」(ISO30414)を発表しました。
背景にあるのは、「ESG(環境・社会・ガバナンス)投資」の浸透です。人的資本は、ESGのうち、とくに「S」に深く関わります。
要は、人材への投資状況が、企業の成長性を評価する大きな判断ポイントとなってきたのです。
そのため、投資家から人的資本情報開示の要請が高まっており、開示を怠る企業はもはや市場から相手にされない時代になってきました。本書にも、《投資家は、人に投資しない企業を「未来のない企業」とみなします》との一節があります。
そうした世界的趨勢を踏まえ、日本でも経産省主催の「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」が設けられ、2020年9月にはその最終報告書「人材版伊藤レポート」が公開されました。
本書の第1章では、そのような背景が解説されます。そして同時に、従来から言われる「人を大切にする経営」と「人的資本経営」の違いが、わかりやすく説明されています。たとえば――。
《過去の「人を大切にする経営」では社風や経営者の姿勢といったフワッとしたものを指すことが多かったように感じます。(中略)
一方、「人的資本経営」ではISO30414のように具体的なデータを重視します。すべてを数値化することはできないとしても、測定できる項目をできるだけ多く設定し、それらを開示していこうとする点に大きな特徴があります。
「人的資本経営」に関連して語られることの多い従業員の「ウェルビーイング」や「エンゲージメント」も、主観的な概念ではありますが、それを客観的な数値で測定しながら向上させていこうとする点に特色があります》
「人的資本時代」のリーダー像を探る
要するに、「人を大切にする経営」の意味が、昔といまでは大きく変わったのです。
著者はその変化を、《与えられた人材(資源)を効率よく使う「やりくり型」組織》から、《組織の枠を越えて人材(資本)から利益を生み出す「レバレッジ型」組織へ》の変化と表現しています。
そのような一大変化に応じて、企業で求められるリーダー像も、当然変わってきました。
著者の上林周平さんは、ソフトバンク、バンダイ、KDDIなどの大企業で多数の研修を行ってきたベテラン・コンサルタントです。豊富な経験を踏まえ、「人的資本時代」にふさわしい新しいリーダー像を、本書では探っています。
「組織を変えるリーダーの教科書」という副題のとおり、本書の2~10章は、その新しいリーダー像をさまざまな角度から解説していく内容です。
リーダーといっても経営者ではなく、管理職の役割にフォーカスしている点が、本書の大きな特徴といえます。
著者は、「人的資本経営」の時代における管理職を「TMO(Team Management Officer)」と名付け、どのような能力が求められるのかを解説していきます。
「キャリア支援力」「強み発見力」「仕事アサイン力」「チームビルディング力」「人材獲得力」「オンボーディング力」「全体俯瞰力」に腑分けされたそれらの能力を見ると、TMOが従来の「やりくり型」リーダーとは異なる存在であることがわかります。
そのようなスキルを兼備した管理職がいたなら、経営者にとってどれほど心強いことでしょう。
著者は、大企業を渡り歩く「プロ経営者」がいるように、これからの時代は汎用性のあるスキルを身につけた「プロ管理職」が台頭するだろう、と指摘しています。
たしかに、本書でいうTMOは、どの企業からも引く手あまたとなるに違いありません。
「人的資本経営」時代にふさわしいリーダーになるための具体的手法を解説した本書は、管理職のみならず、中小企業経営者にとっても学びの多い一冊です。
上林周平著/アスコム/ 2022年7月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






