『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第42回/『武器としてのカーボンニュートラル経営――中堅・中小企業のサバイバル戦略』
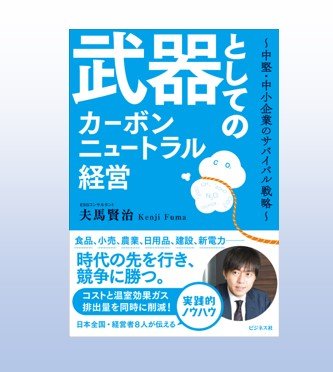
中小企業も待ったなしの「脱炭素」
「カーボンニュートラル」は、菅義偉前総理が2020年10月の臨時国会での所信表明演説で「2050年カーボンニュートラル宣言」を行って以来、日本でも一般的な言葉として定着しました。
カーボンニュートラルとは、CO2(二酸化炭素)に代表される「温室効果ガス」の排出が、「全体としてゼロ」(=排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする)になる状態を意味します。2050年までに、日本がカーボンニュートラルの「脱炭素社会」となることを目指すと、菅前総理は世界に向けて宣言したのです。
当然、後任の岸田文雄内閣になってからも、その流れは受け継がれています。
2022年、岸田政権は、カーボンニュートラル化推進のために《官民で150兆円規模のファイナンス、そして政府として国債発行で20兆円の資金を集める政策を打ち出した》(本書「終章」)のです。
そうした動きの背景には、もちろん、地球規模の気候変動(温暖化)という一大危機があります。それは人類全体で対処していかねばならない問題であるため、企業経営もカーボンニュートラルを避けては通れません。
カーボンニュートラルに無頓着で何ら対応をしていない企業は、もはや市場から相手にされず、ビジネスが成り立たなくなってきました。ここ数年の間に、世界でも日本でも、そのように「時代の潮目」が変わったのです。
ただ、中小企業経営者の中には、そのような趨勢に無関心な人も、まだ少なくないでしょう。
「地球温暖化対策? 大切なのはわかるけど、それは大企業がやるべきことで、うちのような中小企業には関係ない。それに2050年はずいぶん先だから、いまはまだ考えなくていいだろう」――そんなふうに考えている人も多いことでしょう。
それは認識不足で、中小企業もすぐに「カーボンニュートラル経営」を目指すべきなのだ、と訴えるのが、今回取り上げる『武器としてのカーボンニュートラル経営』です。副題に「中堅・中小企業のサバイバル戦略」とあるとおり、本書は主に中小企業経営者に向けて書かれています。
8つの企業の経営者が著者の対談相手として登場しますが、そのうち上場企業は1社(ニッコー)のみで、ほかは中小企業なのです。
《企業の大小を問わず、カーボンニュートラル化を進めることは、企業が存続していける前提となってきたのだ。(中略)もはや、温室効果ガスの排出量に無関心のまま、これまでと同じ事業を続けられると考えてしまうことは、巨大な経営リスクなのだ》
「中小企業には関係ない」どころではありません。中小企業にとっても、カーボンニュートラル化を目指す経営シフトは、もはや「待ったなし」なのです。
先駆的企業8社の事例に学ぶ
著者の夫馬賢治(ふま・けんじ)さんは、株式会社ニューラルのCEOで、信州大学特任教授などを務めています。
日本における「カーボンニュートラル経営」研究の第一人者です。早くからサステナビリティの重要性を訴え、企業などのカーボンニュートラル化を推進してきました。『超入門カーボンニュートラル』(講談社+α新書)などの著作もあります。
その夫馬さんが、各分野で「カーボンニュートラル経営」に取り組んできた企業8社の経営者と対談したのが本書です。
つまり「対談集」であるわけですが、1章1人ずつの対談の末尾には、著者によるまとめ・総論が付されています。
それは、対談相手が属する業界の地球温暖化への関わりを概観したうえで、各企業が推進するカーボンニュートラル化の意義を解説するものです。
簡にして要を得た優れた内容で、通読する時間がない場合、この総論部分だけを読んでも、かなり深い学びが得られるでしょう。
もちろん、メインとなる対談も充実しています。
食品・小売・農業・日用品・建設・新電力・伝統的ものづくり業……登場する8人は、それぞれ異なる分野のいわば“代表”であり、その分野における「カーボンニュートラル経営」の先駆者です。
(ちなみに、『理念と経営』にご登場いただいたことのある愛媛県今治市のタオルメーカー「IKEUCHI ORGANIC」も、そのうちの1社として登場しています)。
彼らの経営ノウハウを、著者は専門家ならではの的確なレスポンスで、鮮やかに引き出していきます。同じ分野の中小企業経営者はもちろんのこと、それ以外の経営者であっても、実践的ノウハウが大いに参考になるでしょう。
カーボンニュートラルが経営を強くする
8人との対談を終えたあと、著者が全体を総括する形で書かれているのが、終章「カーボンニュートラルは経営を強くする武器になる!」です。この章題は、本書全体を象徴するフレーズとも言えます。
一般には、「カーボンニュートラルを目指すことによって、製造などの手間が増え、コストは増大する。それは経営の足枷になる」というイメージが強いでしょう。
本書の「はじめに」の次の一節は、そのイメージを踏まえたのです。
《おそらく、カーボンニュートラルの話を耳にした経営者の多くは、嫌な顔をすることが多いだろう。今でも経営が大変なのに、カーボンニュートラルなんてやっていられないよということに違いない。特に、中堅・中小企業からは、大企業以上に抵抗感が強いように感じる》
つまり、“カーボンニュートラルの推進は、経営上の余力がある勝ち組企業が、その余力を使って社会貢献として行うもの”というイメージです。
ところが、じつは必ずしもそうではなく、カーボンニュートラルに取り組んだことによって業績が上向く事例も多いのです。なぜそうなるのかは、本書を読めばわかります。
《政府はカーボンニュートラルを進める企業に味方する》からでもありますが、それだけではありません。カーボンニュートラル推進が、むしろコスト削減と経営体質強化につながるケースも多いのです。
《今回紹介した8社からは、コスト削減に繫げられたという話がいくつも登場している。省エネ型の機器を導入したことや、製法・農法を改善したことで、燃料や資源の購入費を減らすことが出来、結果的に設備導入コスト以上にコストを減らすことが出来ているものも多い》
もちろん、コスト増大につながるケースもあるわけですが、それでも、時代の変化に対応するためには、あらゆる分野の企業がカーボンニュートラルを目指さざるを得ません。
そこで思い出すのは、1970年代、米国の厳しい自動車排ガス規制を乗り越えるべく懸命に努力したことが、日本の自動車メーカーの技術力を高め、強くしたという歴史的事実です。
同様に、カーボンニュートラルを他人事ではなく「自分事」として捉え、自社に何ができるかを真剣に模索した中小企業が、これからの時代に生き残るのでしょう。
そのための「サバイバル戦略」を考えるヒントが、随所にちりばめられた良書です。
夫馬賢治著/ビジネス社/2022年7月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






