『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第41回/『だから僕たちは、組織を変えていける――やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた』
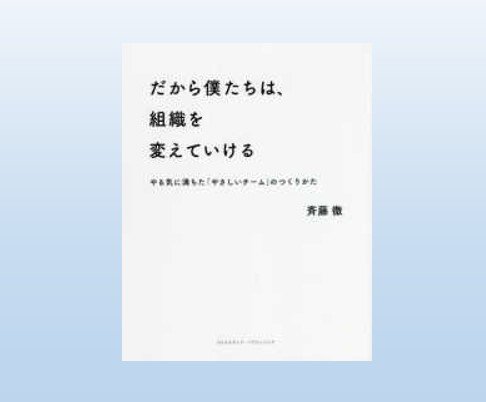
組織のアップデートを進めるために
今回取り上げる『だから僕たちは、組織を変えていける』は、今年(2022年)1月の刊行以後、すでに10万部突破のベストセラーになっています。
長いタイトルを略した「だかぼく」の愛称で読者に親しまれ、12月には実践編『だから僕たちは、組織を変えていける ワークブック』も発売されました。
読んでみれば、好評なのも納得がいきます。組織を変えるための本は多々ありますが、本書はまさに「いま」という時代に即した、時宜にかなった内容になっているからです。
著者に本書を書かせたものは、 “企業経営のありようが、社会変化に対応できていない” という問題意識です。その点については、第1章「時代は変わった。組織はどうか?」で詳述されています。
人間社会は産業革命によって「工業社会」に変わり、20世紀後半からのコンピュータの発展によって「知識社会」へと変わりました。ところが、経営のありようは21世紀のいまも「工業社会」モデルのままであり、「知識社会」にふさわしいものになっていない、と著者は言います。
従来、《組織経営の基本は「トップダウンで、いかに一糸乱れぬ統制をとるか」という視点で語られて》いました。工業社会においては、それは組織の生産性を高める最善の方法だったからです。
しかし、PC、ネット等による情報革命が起きたいまは、そのような「統制型組織」は時代遅れになっています。トップダウンで統制を強めようとすれば反発を招き、かえって組織のパフォーマンスを下げてしまうのです。
にもかかわらず、多くの企業ではまだ統制型管理が行われている。いまにふさわしい、人間重視の「学習する組織」「共感する組織」「自走する組織」に変革していかなければならない……そのように著者は言い、具体的な変革の方途を本書で解説していくのです。
つまり、多くの企業で20世紀のままになっている組織のありようを、いまにふさわしい形にアップデートするための本なのです。
著者の言う「学習する組織」「共感する組織」「自走する組織」がそれぞれどのようなものなのかは、本文でじっくりと解説されています。
著者自身の体験を踏まえた組織改革論
著者の斉藤徹氏は、日本IBMを経て29歳の若さでベンチャー企業を起こし、30年に及ぶ起業家経験を持っています。そのかたわら、近年は学習院大学経済学部特別客員教授やビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授を務め、組織論・起業論などを講じてきました。
斉藤氏の起業家人生には、大きな挫折もあったようです。
起業した会社を時価総額100億円超のテクノロジー・ベンチャーに育て上げたものの、《時に強引な営業を促し、取引先を困らせ、社員を路頭に迷わせ、あげくの果てに創業者追放の憂き目にも遭いました》と、氏は振り返っています。
そうした挫折を経て、氏は自らの経営手法を大きく転換し、そのことによって会社を奇跡的に復活させました。その転換こそ、「統制型組織から人間重視の組織へのシフト」でした。
つまり本書は、著者自身の体験を踏まえた組織改革論なのです。どういう組織が時代遅れで、どういう組織が時代に合っているか――経験に裏打ちされているからこそ、著者の言葉には重い説得力があります。
最新の組織論を幸せ視点で体系化
ただし、著者の体験が素のままで語られるのは、終盤のみです。そこまでの大部分は、著者が研究してきた広範な組織論が、適宜引用されて構成されています。
著者と同様に、「統制型管理ではもう駄目だ」と悟り、いまの時代にふさわしい組織運営を模索してきた人は、たくさんいます。経営学者、経営者、さまざまな分野の研究者など……。それらの研究成果が随所で紹介され、著者の主張を補強していくのです。
《この本は、第一章がWhy、第二章がWhat、そして第三章から第六章までがHowとして構成され、全体で「知識社会の組織のつくりかた」に必要な最新の組織論を、幸せ視点で体系化したものです》
そのような一節があるとおり、本書は「最新の組織論」ガイドとして読むこともできます。
たとえば、「心理的安全性」、「シェアド・リーダーシップ」、「パーパス」、「主体性を持つギバー」、「モチベーション3.0(内発的動機づけ)」、「従業員エンゲージメント」「セルフ・アウェアネス(自己認識力)」など、いまどきの組織論には欠かせないキーワードが本書にも次々と登場し、わかりやすい解説がなされます。
それらのキーワードをまとめて学ぶために、本書を読んでもよいでしよう。
また、《幸せ視点で体系化》とあるとおり、著者は組織の構成員個々の「幸せ」を何よりも重視しています。
企業は、社員や顧客が幸福になるための手段である――それは本来、あたりまえであるはずです。にもかかわらず、統制型管理では社員個々人の幸福はないがしろにされ、売上などの数字が目的化する本末転倒が常態化してきました。
本書はその転倒を正し、企業が「組織のための人間」から「人間のための組織」という原点に回帰するための知恵を体系化した一冊と言えます。
誰もが「組織変革の起点」になり得る
3章から6章までの「How」の部分では、自らが所属する組織を変えようとする個々人が、何をどのように変えていけばよいのかが、具体的に解説されています。
そのためにはまず自分が変わる必要があり、会社全体を変えるための一歩として自らのチームを変える必要があります。
《今の組織をよりよくするために、自分を変えるところからはじめる。数々の困難を学習の機会ととらえ、組織変革の起点となってゆく。僕は、そのような方々のことを、敬愛を込めて「スモールイノベーター」とお呼びしています》
組織変革というと、「トップ層、リーダー層が行うもの」というイメージが浮かびがちです。しかし、著者はそのように限定的には考えていません。たとえ一社員であれ、誰もが「スモールイノベーター」として「組織変革の起点」になり得ると捉えているのです。
その意味で、本書は経営者のみならず、「自分の組織を変えたい」と思っているすべての人にすすめたい一冊です。
とはいえ、《一人ひとりの意識変化はもちろん重要ですが、最も大きな影響を与えるのは、経営者自身の考え方です》との一節もあるとおり、経営者が率先して主体者となることが、組織変革の早道であることは言うまでもありません。
中小企業経営者にとっても、「これからの時代にふさわしい組織」への変革を促す良書です。
斉藤徹著/クロスメディア・パブリッシング(インプレス)/2022年1月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






