『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第39回/『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』
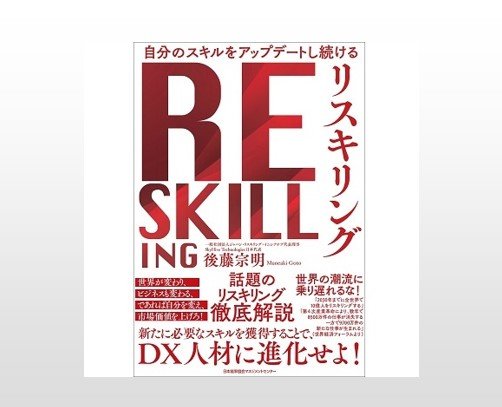
リスキリングが社会課題となった背景
2022年10月、岸田文雄首相は所信表明演説で、「リスキリングの支援に今後5年間で1兆円の予算を投じる」との方針を示しました。それ以前からすでにビジネス界でブーム化していた「リスキリング(Reskilling/Re-skilling)」は、この方針によって一気に“国を挙げて解決すべき社会課題”となったと言えます。
出版界でも、リスキリング関連書の刊行が少しずつ目立ってきました。2023年にはもっと増えるでしょう。
今回取り上げる『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』は、一般向けのリスキリング関連書としては日本でいちばん早く出たものです。
本書の「はじめに」には、次のようにあります。
《現在日本では、リスキリングに「学び直し」という訳が当てられていることが多いですが、実は半分正解ですが不正確な表現です。リスキリングは、
「新しいことを学び、新しいスキルを身につけ実践し、そして新しい業務や職業に就くこと」
を指しています》
リスキリングに「学び直し」の側面もあるのは当然です。しかし、「学び直し」だけで終わってしまったら、リスキリングとは呼べません。学んだスキルを活用して「新しい業務や職業に就くこと」までが、リスキリングのワンセットであるからです。
混同されがちな「リカレント教育」との違いも、そこにあります。
《リカレント教育においては、「学び直し」そのものが目的かつ、職業と関係ない学びも含むのに対し、リスキリングは新しい職業に就くことを目的としているため、職業に直結するスキル習得を指しています》
リスキリングがクローズアップされた背景には、デジタルテクノロジーの急激な進歩とオートメーション化の加速で、人の仕事の多くがAIやロボットに代替される「技術的失業(Technological Unemployment)」の問題があります。
「世界経済フォーラム」(ダボス会議)の2020年10月の発表によれば、「今後5年間で、人間、機械、アルゴリズムの労働分担が進むことによって、8500万件の雇用が消失し、9700万件の新たな雇用が創出される」と予測されています。
つまり、デジタルテクノロジーの進歩は人間の仕事を奪うだけではなく、それ以上に新たな仕事も大量に生み出すのです。
ただし、これから生まれる仕事に就くためには、新しいスキルが必要になります。それを身につけていない人たちの大量失業という危機が、ごく近い未来に迫っています。多くの労働者が「技術的失業」に陥る前に、リスキリングで需要と供給の巨大なギャップを埋めることが、急務となっているのです。
本書では、そのような社会的背景も詳しく解説されています。
リスキリングの第一人者による初の単著
著者の後藤宗明氏は、米国フィンテック企業の日本法人代表、通信ベンチャーの国際部門取締役などを経て、2021年に「一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ」を設立しました。
同法人では、《リスキリングの啓蒙活動や政策提言、海外におけるリスキリング成功事例の紹介、リスキリングを導入する企業や自治体へのコンサルティングや研修、ワークショップ等》を行っているとのことです。
日本におけるリスキリングの第一人者である後藤氏が、《リスキリングに関する調査研究結果と政策提言、そして自治体や企業へのリスキリング導入支援の経験をもとに執筆》した初の単著が、本書なのです。
質の高いリスキリング入門であり、「リスキリングについて、一通りのことが知りたい」と思った人が最初に読むべき本と言えるでしょう。
後藤氏は、リスキリング先進国である米国の状況を目の当たりにし、日本企業のリスキリングへの取り組みが欧米より数年遅れている現状も熟知しています。
また、後藤氏自身、失業やパニック障害発症などによるどん底をいくつも経験し、そのつどリスキリングしてキャリアアップしてきた当事者でもあります(そうした経験も本書で赤裸々に綴られています)。
そのように、リスキリングの最前線を知り、当事者としての目線も持つ人ならではの、ヴィヴィッドな現場感覚に満ちた内容になっています。
リスキリングの幅広い論点を網羅
本書は、「なぜリスキリングする必要があるのか」(第1章のタイトル)を詳しく解説したうえで、リスキリングに取り組むための心構えやノウハウを説いていきます。
とくに第3章では、リスキリングを「10のプロセス」((1)現状評価、(2)マインドセットづくり、(3)デジタルリテラシーの向上など)に分け、その一つひとつを詳細に解説しているため、読者がリスキリングを実践するときに役立つでしょう。
また、一口にリスキリングといっても、そのための制度が会社によって整備されている大企業と、まったく未整備な中小企業では、取り組み方を変える必要があります。
本書の第2章は、「会社員(大企業)編」、「会社員(中小企業)編」、「個人事業主、フリーランス編」などに分けられており、読者の立場に応じてリスキリングを考えやすいよう、工夫がなされています。
そして、本書の後半では、今後、リスキリングの進展によって労働環境・人材トレンドがどう激変していくのかが展望されます。
たとえば、学歴重視の採用は終わりを告げ、今後は「スキルベース採用」が主流になっていくと、著者は言います。
すでに海外企業ではスキルベース採用が導入されており、そのためにAIを用いた「スキルテスト」をオンラインで行って可否を決めることも増えているとか。
リスキリングといえば、とかくデジタルスキルの面のみから語られがちです。リスキリングの主舞台が新たなデジタルスキル習得にあるのは確かですが、それ以外の側面もあることを見逃すべきではありません。
本書は、デジタルスキル以外の側面にも目配りされています。たとえば、環境重視の「グリーンジョブ」に対応したスキルを習得する「グリーン・リスキリング」が、今後は重要性を増していくことが説得的に論じられています。
そのように、リスキリングをめぐる幅広い論点が一通り網羅されている本なのです。
中小企業もリスキリングを避けて通れない
《日本の99・7%の会社が中小企業であることから、ほとんどの方は現時点で会社にリスキリングの制度が整っていない場合が多いのではないかと思います。
特に就業時間中にリスキリングを行うための時間確保がままならず、帰宅後や週末に時間を捻出しないといけないという声をよく聞きます》
本書にそんな一節もあるとおり、欧米よりもリスキリングの取り組みが遅れている日本企業の中でも、中小企業の遅れはとくに深刻です。
とはいえ、《リスキリングは、やりたい・やりたくないの議論ではなく、雇用を維持し、成長していくためにマストなのです》から、中小企業もリスキリングを避けては通れません。
では、中小企業経営者は、いったい何からリスキリングに取り組めばよいのか?
そのことを平明に教えてくれるのが、本書なのです。
後藤宗明著/日本能率協会マネジメントセンター/2022年9月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






