『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第37回/『THE HEART OF BUSINESS(ハート・オブ・ビジネス)――「人とパーパス」を本気で大切にする新時代のリーダーシップ』
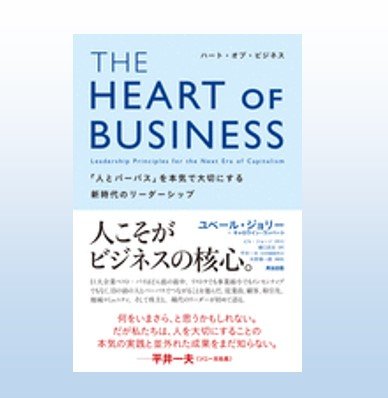
全米最大の家電量販店の再建物語
『理念と経営』2022年12月号に、株式会社ユーグレナの出雲充社長と、経営学者・入山章栄先生(早稲田大学ビジネススクール教授)の「巻頭対談」が掲載されています。
その対談の中で入山先生が言及し、「『日本経済新聞』で書評担当を始めて以来、最高評価をつけた一冊」として絶賛していたのが本書です。「入山先生がそこまで絶賛される本なら、読まなければ」ということで、さっそく手に入れて読んでみました。
著者のユベール・ジョリーは、母国フランスとアメリカで数々の大企業を再建してきた、再建請負人ともいうべき名経営者です。『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌によって「世界のCEOベスト100」の1人に選出されるなど、世界的名声を得ています。
彼のキャリアの中でもひときわ輝いているのが、2012年に米家電量販最大手「ベスト・バイ」のCEO(最高経営責任者)に就任し、どん底状態にあった同社を再建したことです。
「ベスト・バイ」は、日本ではなじみがありませんが、全米最大の家電量販店チェーンであり、12万人以上の従業員を抱える巨大企業です。
しかし、ジョリーがCEOに就任した当時、ネット通販に押されて売上は下がり、株価は10ドルそこそこになり、倒産は時間の問題と見られていました。
ジョリーは、CEOに着任した年のうちに売上の減少を止め、2017年には株価50ドルを突破させました。そして、2019年までの在任7年間で、ベスト・バイの利益を3倍、株価を9倍に伸ばし、見事なV字回復を成し遂げたのです。
本書はジョリーの経営者としての来し方を振り返るものですが、中心となるのはベスト・バイ再建劇の舞台裏です。
大企業の再建を成し遂げた経営者の著書は、すでに汗牛充棟です。類書にはない本書ならではの価値は、ジョリーが拠り所としたのが「パーパス経営」だった点にあります。
「パーパス経営」のたぐいまれな実践論
パーパス経営の関連書として、当連載ではすでに、『パーパス経営』(名和高司著)や『パーパスのすべて』(山田敦郎・矢野陽一朗・グラムコパーパス研究班著)を取り上げています。
その2冊が主に理論面からの概説書であったのに対し、本書はパーパス経営によって大企業を再建した経営者の実践記録です。その点に重い説得力があります。
本書には、Amazon創業者のジェフ・ベゾスが、「世界中のビジネススクールで教えられるべきであり、教えられていくであろうケーススタディだ」との讃辞を寄せていますが、それもうなずけます。経営学者やコンサルタントではなく、大企業経営者自らがパーパス経営のAtoZを明かした本は、これが初めてだからです。
ジョリーは、最初からパーパス経営を標榜していたわけではありません。元々は、「ビジネスの社会的責任は利益を増やすことだ」というミルトン・フリードマン(経済学者/ノーベル経済学賞受賞者)の教えに則って、利益至上主義・株主最優先の経営を追求していたのです。
しかし、多くの企業の再建に関わるうち、ジョリーは利益至上主義の経営が時代遅れになっていることを思い知りました。
経営者と社員たちが共に目指す「北極星」としてパーパス(会社の存在意義)を掲げ、それを中心に経営する“パーパス至上主義”の経営のほうが、結果的にうまくいく。利益もあとからついてくる……そう気付いたのです。
だからこそ、ベスト・バイの再建に当たって、ジョリーは最初からパーパス経営を標榜しました。掲げたパーパスは、「テクノロジーを通して顧客の暮らしを豊かにする」。このパーパスを定めるまでに、ジョリーはベスト・バイの幹部たちと2年以上も会議を重ねたといいます。
そして、利益を増やすことではなく、パーパスを実現することを会社の目的としたのです。「利益は不可欠ではあるものの、それは結果として得られるものであり、それ自体が目的ではない」と、ジョリーは言います。
ただし、それは利益を度外視したわけでも、株主を無視したわけでもありません。経営者と社員たちがパーパスを羅針盤として心一つに進めば、社員たちのエンゲージメントも高まり、そのことでパフォーマンスも上がって利益も上がり、結果的に株主も喜ぶのです。
「人に備わる魔法のような力」を引き出す経営
ジョリーは次のように書いています。
《私は、ビジネスの根本はパーパスや、人や、人間関係にあると信じている。少なくとも、利益は第一ではないはずだ。企業とは、魂のない「モノ」ではない。一人ひとりの個人が共通のパーパスを目指して協働する、人間らしい組織である。この共通のパーパスが、各個人の生きる意味と重なったとき、人に備わる魔法のような力が解き放たれ、目覚ましいパフォーマンスが発揮される》
この「人に備わる魔法のような力」=「ヒューマン・マジック」という言葉が、本書にはくり返し登場します。それは、会社のパーパス(存在意義)が社員個々人のパーパス(生きる意味)と合致したときに生まれる力のことです。
パーパスは大仰なものでなくてもよいのですが、少なくとも、サステナビリティ(持続可能性)に合致し、人々の幸せに寄与するものでなければなりません。
そうであってこそ、社員たちは「自分がこの会社で頑張ることが、世のため人のためになっている」と自信を抱くことができ、それがやりがいにつながるのです。単なる利益至上主義であれば、そのようなやりがいは感じられません。
ジョリーがCEOになる以前のベスト・バイは、家電を売って利益を上げることだけが目的になっていました。それを、ジョリーは「テクノロジーを通して顧客の暮らしを豊かにする」というパーパスを目的に変え、その目的に沿って会社も変えていったのです。
たとえば、高齢者にヘルスケアサービスを提供する事業や、「トータル・テック・サポート(家のすべての電化製品に対するサポート)」の提供など、全米津々浦々に根を張った店舗ネットワークを生かし、各地域の人々に貢献することを事業化していきました。
《ベスト・バイの技術サポート部門「ギーク・スクワッド(Geek Squad)」は、トータル・テック・サポートの一環としてベスト・バイ以外の小売店で購入した製品であっても相談に応じることにした》
単に家電を売って利益を上げることが目的なら、そんなことは決してしなかったでしょう。
「顧客の暮らしを豊かにする」ことを目的に据えたからこそ、顧客満足度(CS)が高まり、その結果として従業員満足度(ES)も高まり、好循環が生まれて利益も上がっていったのです。
本書の帯には、「人こそがビジネスの核心」という惹句が躍っています。
利益や株価にではなく、人(社員、顧客など)に「ビジネスの核心」(ハート・オブ・ビジネス)を置く……それこそがジョリー流再建術の肝なのです。
だからこそ、彼はベスト・バイの再建に当たって、米企業の常套手段である大規模なリストラを行わず、給与カットも最小限にとどめました。
《2012年以来、ベスト・バイは当初目標としていた7億2500万ドルを大きく上回る、約 20 億ドルのコストを削減してきた。そのうち約3分の2は給料以外のコスト削減だ》
人を大切にし、社員のエンゲージメントを高めることで経営を改善させるパーパス経営のモデルケースが、本書には記録されています。
舞台となるのは巨大企業ですが、本書で明かされたジョリー流のパーパス経営と企業再建術は、中小企業経営者が読んでも参考になるものばかりです。
そして、全4部構成のうちの第4部「パーパスフル・リーダーになる」では、これからの時代にふさわしい、パーパスを重視するリーダー(経営者)像が探られています。新時代の経営者論としても出色です。
ユベール・ジョリー、キャロライン・ランバート著、樋口武志訳/英治出版/2022年7月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






