『理念と経営』WEB記事
僕らがどう生きるか
2022年12月号
孤独問題への取り組みは、“本気の他人事”。
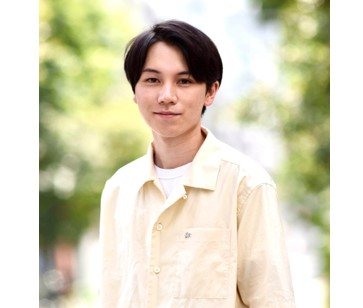
社会実業家 大空幸星 氏
24時間365日対応の無料チャット相談窓口「あなたのいばしょ」代表の大空幸星さんは、大学時代から孤独問題を解決するための活動に尽力してきた。まもなく24歳を迎える大空さんは、いわゆる「Z世代」に数えられる。いったい、どのようなスタンスで社会問題と向き合っているのだろうか。
あらゆる社会問題の根源は“望まない孤独”
日本は「孤独担当大臣」というポストを有する、世界で唯一の国だということをご存じだろうか。NPO法人「あなたのいばしょ」代表の大空幸星さんは、そのポストを誕生させた張本人なのである。
「孤独担当大臣は2018(平成30)年にイギリスで世界で初めてできたんですが、去年10月に廃止されたのでいまは日本だけになりましたね」
大空さんは、そう話す。孤独は大きな社会課題だと、大空さんは考えているのだ。
「自殺や虐待、DV、いじめ、不登校などあらゆる問題の根源的なものとして孤独があるんです。孤独を感じている人は何かの問題や悩みを抱えていても誰にも頼れないんです」
そこで思いあまって、何らかの問題行動を起こす。それを事前に防ぐことができればと、大空さんはNPOを設立し、365日24時間対応の「チャット相談」を始めたのだ。
同時に政府に孤独担当大臣設置の働きかけを続けたのである。そうして孤独担当大臣が日本にできたのが2021年2月のことだった。
すでに1年10カ月経つが、大空さんの評価はどうなのだろう。
「これまで孤独や孤立感を感じている人の支援は不十分でしたから、まずそこの対症療法的な支援がいまは主流です。だけど、やがては予防的な方向に移っていかないといけないと思っています。
ただ残念なのは、孤独の定義を設けると、そこから漏れる人が出る可能性があるという理由で定義はしないとした政府の方針です。僕は定義するべきだったと思います」
定義が明確でないと具体的な対策も考えられない。では、社会課題としての孤独の定義とは何か。それは “自らが望まない孤独”だという。
「誰かに頼りたくても頼れない。誰かと話したくても話せない……。自分では望んでいないのに、そういう状況に追い込まれる。孤独というのは『お腹がすいた』『喉が乾いた』とかとまったく同じ感情なんです。単純に孤独を感じたら人とつながることが必要なんです」
大空さんがチャット相談の窓口を開設したのも、その “つながり”をつくるためなのである。
無料チャット相談「あなたのいばしょ」のロゴデザインには、「あらゆる年齢・性別の人が利用しやすいように」という願いが込められている
弱みを見せて、人に頼ること
「孤独を英語にするとLoneliness(ロンリネス)とSolitude(ソリチュード)の2つがあります。Solitudeは積極的な孤独で『孤高』とかに近いものです。われわれが問題にしているのはLonelinessの孤独です。でも、日本の難しさは孤独が孤高と混同され、ときに孤独は愛すべきものだとか、自分を強くするものだとかと礼賛されることがあることです。そういう日本の文化が孤独を個人の問題として矮小化してきたんです」
大空さんが興味深いデータを紹介してくれた。
英国『エコノミスト』誌と米国のカイザー・ファミリー財団が共同で、4年前に日米英で実施した調査だ。この調査で日本人は44%が「孤独は自己責任である」と答えていて、アメリカ人の23%、イギリス人の11%を圧倒的に越えているのだ。
孤独を自己責任と考える限り、それは個人で対処すべき問題になる。
「本来はボランタリーな価値観である自己責任が、日本では自業自得だと考えられています。不本意な結果になったとしても、それは自分が悪かったと考える。こうした懲罰的な自己責任論という考え方が生まれ、それが家庭に広がり、子どもたちにも蔓延しているんです」
結局、それは “真面目な子ども”を生んでいると大空さんは指摘する。
「あなたのいばしょ」の相談でも親にも先生にも迷惑や心配をかけたくないと話す若者が多いという。そんな10代から20代の相談者の39%が孤独を「常に感じている」と答え、35%が「しばしば感じる」と答えているそうである。
「懲罰的自己責任論は自己否定のループを生み出すだけではなく、孤独を抱えても誰にも頼ってはいけないなどというスティグマ(偏見や烙印、決めつけ)も強くしていくのです」
自殺を見ても、日本の自殺者の特徴は約7割が男性で、しかも中高年層が多いことが知られている。
その原因として考えられるのは、中高年のビジネスパーソンが「責任あるものは強くならねばならない」「部下に弱みを見せてはいけない」などといったスティグマを強く抱えているからだと、大空さんは言う。
普段は多くの人に囲まれて仕事をしていても、いざというときにこのスティグマに囚われて悩みを相談することができないのだ。こうしたことを考えても孤独を社会課題として捉えていくことの必要性がわかる。
「孤独というのは社会関係の量だけではなくて、質の乖離から生まれるものなのです。社会的な関係の量が充足していても自殺は起きたりします。だから、質の部分が大切なんです。たった一人でもいい。頼れる人がいればいいんです。それがSNSの中の人でもいいと思います」
大空さんたちがやっている相談窓口など、さらにその先の匿名でのチャンネルでしかない。しかし、それでもそこで悩みや思いを吐き出すことで、「明日も生きてみようかな」と思ってもらうことはできる。そう考えているのである。
「僕たちがやっているのは、あくまで問題の根本的な解決の手前、いわばマイナスからゼロ・フラットの状態まで持っていくことなんです。必要なのは安心感なんです。その安心感は傾聴で担えるんです」
取材・文 鳥飼新市
撮影 富本真之
本記事は、月刊『理念と経営』2022年12月号「僕らがどう生きるか」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)







