『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第33回/『絶対悲観主義』
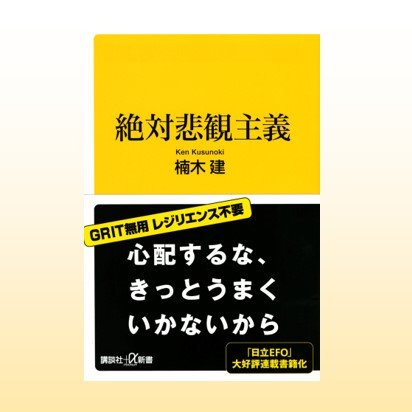
人気経営学者の「仕事論」「幸福論」
メディア露出も多い人気経営学者の楠木建先生(一橋ビジネススクール教授)には、『理念と経営』にもよくご登場いただいております。
楠木先生の専門は競争戦略論であり、主著『ストーリーとしての競争戦略』(東洋経済新報社)は累計30万部突破のベストセラーとなりました。
同書のような本格的経営書を著す一方、楠木先生には書評集や読書論など、一般書の著作も少なくありません。
最新著作である本書も、タイトルからわかるとおり経営書ではなく、広く一般向けの内容になっています。それでも、内容には経営者に役立つ部分も多いことから、当連載で取り上げることにしました。
本書は、日立製作所のオウンドメディア「Executive Foresight Online」で、楠木先生が週1回ペースで連載中のコラム「EFOビジネスレビュー」をベースにしています。
同連載は《自分の思考の断片を思いつくままに書いてきました》(「Executive Foresight Online」の『絶対悲観主義』発刊記念インタビューより)というもので、50近い多様なテーマを扱ってきました。
そのテーマの一つに「絶対悲観主義」があり、それを軸に連載からセレクトしたコラムを集めたのが本書なのです(ただし、全面的な再構成・加筆修正がなされています)。
そのため、書名に即した“絶対悲観主義のススメ”がストレートに展開されているのは、第1章のみです。それ以降の各章は、「絶対悲観主義者」である楠木先生の思考スタイルを踏まえ、さまざまなテーマが俎上に載ります。
たとえば、第2章「幸福の条件」のテーマは幸福論ですが、それは絶対悲観主義の哲学に即した幸福論なのです。
また、随所で楠木先生のこれまでの歩みが振り返られていますが、それらは絶対悲観主義者の視点から見た仕事論、人生論にもなっています。
“前向きな悲観主義”のススメ
中小企業経営者のみなさんは、悲観主義という言葉によいイメージを抱いていないかもしれません。経営の世界ではとかく、逆境すら「ピンチはチャンス」と前向きに捉えるような楽観主義の重要性が強調されがちだからです。
しかし、当たり前ですが、楽観主義一辺倒では経営はうまくいきません。経営層が全員極端な楽観主義者揃いの企業は、早晩致命的な失敗をして消えていくでしょう。悲観主義の視点に立って状況を見極める人も、経営には必要なのです。
悲観主義には、悲観主義ならではのプラス面があります。本書はまさに、悲観主義の効用・プラス面に的を絞った一冊なのです。
そもそも、本書で言う悲観主義は、すべてを悲観的に捉えて「何をやっても無駄だ」とあきらめて何もしないニヒリズムではありません。
むしろ逆に、「どうせうまくいくことなんて滅多にないのだから、ダメ元で気楽にやろう」と、フットワーク軽く行動するための気構えのことなのです。
《仕事である以上、絶対に自分の思い通りにはならないと僕は割り切っています。「世の中は甘くない」「物事は自分に都合のいいようにはならない」、もっと言えば「うまくいくことなんてひとつもない」──これが絶対悲観主義です。
ただの悲観主義ではなく「絶対」がつくところがポイントです。仕事の種類や性質、状況にかかわらず、あらゆることについてうまくいかないという前提を持っておく。何事においても「うまくいかないだろうな」と構えておいて、「ま、ちょっとやってみるか……」。これが絶対悲観主義者の思考と行動です》
うまくいかないことを大前提にするからこそ、何事にも気軽に取り組めて実行スピードが早まり、失敗しても落胆が小さい。また逆に、もしもうまくいったら、小さな成功でも喜びが大きい……絶対悲観主義は、そのようにいくつもの利点を持っています。
《どうせうまくいかないのだから……という絶対悲観主義は究極の楽観主義でもあります》
――そんな一節があるとおり、本書の全編に流れ通う哲学は、いわば“前向きな悲観主義” (形容矛盾のようですが)なのです。
経営者にとっても示唆に富む一冊
本書は、書名だけ見るとまるで哲学書です。また、ポジティブであることが礼賛されがちな既成の自己啓発書の逆を行く、“逆張りの自己啓発書”という趣もあります。
その印象はある意味で正しく、これは風変わりな哲学書でも自己啓発書でもあります。ただし、全体の印象としては楽しい読み物であり、論というよりはエッセイ集です。
文章はしばしば脱線しますが、その脱線部分にも卓見があります。また、意外なほど「笑える」一冊でもあり、私は読みながら何度も吹き出してしまいました。
とはいえ、第一線の経営学者の著作であるだけに、経営者にとって示唆に富む指摘が随所にあります。
たとえば、「ブランディング」と「ブランデッド」は似て非なるものだが、多くの企業がその場限りのブランディングに走りがちである……という、著者ならではのブランド論が展開されるくだりなどがそうです。
《ブランドというのは、振り返ったときにそこにあるものだというのが僕の考えです。毎日の商売の積み重ねで段々と信用が形成され、気がついてみるとその総体がブランドになっている。すなわち、動名詞のブランディングよりも過去分詞の「ブランデッド」です》
《ブランドはある一時点での顧客認知の大きさではなく、顧客の中に積もり積もった価値の総体です。独自の価値提供に自信がない会社ほど、ブランディングというお化粧で勝負しようとする。お化粧はそのうち剝がれてしまいます。ベースがしっかりしていないところにお化粧をしても、たかが知れています》
また、“「組織力」と「チーム力」は異なり、時代はチーム力重視にシフトしつつある”と指摘するくだりは、卓抜な組織論として読むことができます。
《チームの定義は「お互いの相互依存関係を理解し合っている人間の集団」です。この定義からして、チームには規模の上限があります。1000人のチームというのはあり得ません。お互いの顔が見えないのはもちろん、そこにある相互依存関係を認識できないからです。
マネジメントによって設計されるシステムの性能が組織力であるのに対して、チーム力は現場の相互作用の中から湧き上がってくるものです》
《組織力とチーム力の掛け算でパフォーマンスは決まります。パフォーマンスの規定因として、かつては組織力のほうが大きかった。ところが、今はどんどんチーム力のほうにシフトしている。両方の掛け算であることに変わりはありませんが、チームの力がよりパフォーマンスを左右するようになりつつあるというのが僕の認識です》
このように、メモしておきたくなるような一節が随所にあります。それでいて、全体としては軽快で楽しい読み物なのです。
《筋トレに明け暮れがちな読者にとって、本書が思考のストレッチとなれば幸いです》
「はじめに」にそうあるように、成功を求めて血眼になりがちな中小企業経営者に、「どうせうまくいかないんだから、気楽にやろうよ」と、凝った肩をもみほぐしてくれるような一冊です。
楠木建著/講談社+α新書/2022年6月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






