『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第31回/『進化するブランド――オートポイエーシスと中動態の世界』
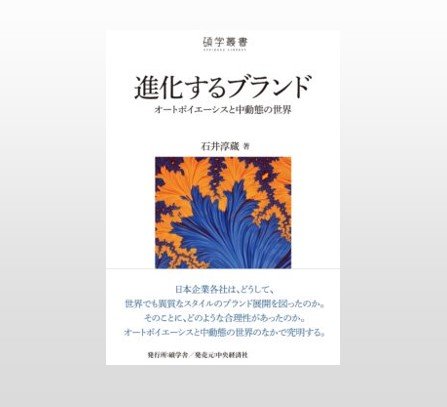
第一人者のブランド研究の集大成
『理念と経営』にもよくご登場いただいている石井淳蔵先生(神戸大学名誉教授)が、この8月に上梓された新著です。
石井先生は、日本におけるマーケティング研究のパイオニアです。
マーケティングとブランディングは地続きですから、日本におけるブランド研究の泰斗でもあり、『ブランド 価値の創造』(岩波新書/1999年刊)などの著作もあります。
本書は、23年前に刊行された『ブランド 価値の創造』の「姉妹編」(本書「あとがき」)ともいうべき一冊。つまり、過去20数年間の深化も踏まえた、著者のブランド研究の集大成なのです。400ページ近い大著でもあり、渾身の一冊と言えるでしょう。
脚注の付け方や、「(小林・一九二五)」などという形式の出典表記は、学術論文の作法に則っています。そのため、一見難しそうに思える本ですが、読んでみれば意外に平明です。
「です・ます」(敬体)のやわらかい語り口調で書かれていますし、中盤で大きく紙数が割かれる企業事例などは、エピソード中心で読み物としても楽しめます。
研究書ではありますが、一般向けの経営書としても読めるのです。
日本企業独特のブランド構築とは?
本書は「プロローグ」でまず、《日本型のブランドと西欧型のブランドには違いがある》という問題提起から始めます。
これは、ブランド研究の世界的権威2人――デービッド・アーカーとジャン=ノエル・カプフェレによる、《国や文化の違いによって、そもそものブランドのありようが違っている》との指摘を踏まえたものです。
では、「日本型のブランド」と「西欧型のブランド」にはどのような違いがあるのか? それを具体的な事例と理論によって明らかにしていくことが、本書のメインテーマといえます。
著者は、ブランディングは2つに大別できるとし、その2タイプを、欧米型の「進化しない(反進化型)ブランド」と、日本型の「進化するブランド」と名付けました。書名はそのことに由来しています。
ただし、ここでいう「進化する・しない」は、優劣を意味するものではありません。“日本の「進化するブランド」は、欧米の「進化しないブランド」より優れている”などという国粋的な主張ではないのです。
「進化するブランド」とは、《同一性を保ちながら変容するコトとしての性格をもつ》ブランド・タイプを指します。
といっても、この一言では意味がよくわからないでしょうが、著者は本書で、日本企業の「進化するブランド」の具体例を挙げ、それを理論的に裏付けていきます。
つまり本書全体が、日本企業の事例を通した「ブランド進化論」なのです。ブランドが進化するとはどのようなことなのかが、さまざまな角度から解説されていきます。
「オートポイエーシス」と「中動態」とは?
副題の「オートポイエーシス」と「中動態」は、2つとも、一般的には聞き慣れない言葉でしょう。そのことが、本書の「難しそう」なイメージを増幅している面があります。しかし、2つとも本書にとって重要な概念なのです。
「オートポイエーシス」とは、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンが提唱した「オートポイエティック・システム論」に出てくる概念で、元々は生物学用語です。
「オート」は「自己」、「ポイエーシス」は「生成・制作」を意味します。「オートポイエーシス」には、「自己創出」「自己生成」という訳語が充てられることが多いようです。
生物が何もしなくても自ら変化していくように、組織やシステム、社会現象にも自己生成して変化していく側面がある……というのが「オートポイエティック・システム論」の主張。著者はそれを「進化するブランド」に当てはめたのです。
つまり、“企業ブランドも、その「ブランドらしさ」を軸として、自ら変化していく”というブランド観が、本書の根底にあります。
もう一つの「中動態」は、言語の「受動態・能動態」に対応する概念です。
私たちは、「山が見える」とごく普通に言います。しかし、「私は山を見る」という能動態でもなく、「山は私によって見られた」という受動態でもない、主語が不明確な「山が見える」という「中動態」の表現は、欧米語には翻訳不可能なのだそうです。
そのような日本語独特の言語表現に、著者は日本の「進化するブランド」の背景要因を見いだします。言語の特徴は、その国の文化のありように大きな影響を与えるものだからです。欧米語にはない中動態の表現が普通に使われることが、日本人の心のありように影響し、ひいては日本型ブランドにも影響を与えているはずだ、というのが著者の見立てなのです。
ブランドを哲学的に裏付ける画期的論考
「本書は意外に平明だ」と先に書きましたが、企業事例集はともかく、「理論編」に当たる第Ⅲ部「ブランド進化の研究」は、正直、かなり難解です。
しかし、第Ⅲ部の冒頭で著者が《理論編の以下の二つの章はともに、経営学やマーケティング論においてこれまでほとんどだれも試みたことのない議論になります》と書くとおり、この難解な理論編こそ、本書で最も独創性の高い、価値ある内容なのです。
そこでは、すでに述べたオートポイエーシスや中動態を巡る議論が掘り下げられます。また、西田幾多郎・木村敏・丸山真男・阿部謹也などという日本の誇る碩学たちの言葉が、縦横無尽に引用されます。
哲学・精神医学・政治学・歴史学など、広い分野の知見を総動員して、日本型の「進化するブランド」の特徴が浮き彫りにされていくのです。
経営、企業ブランドについて論ずる本で、これほど深い議論が体験できるとは、読む前には予想だにしませんでした。
これは、ブランドというものを哲学的に裏付けていく画期的論考であり、“日本企業のありようをフィルターとした日本文化論”としても読めます。
以上のように紹介すると、中小企業経営者の皆さんは「自分には関係ない本だ」と思ってしまいそうですが、そんなことはありません。
たしかに、本書に登場する事例の多くは大企業・グローバル企業です。しかし、中小企業であれ、またどんな分野の企業であれ、ブランディングは重要な課題といえます。
本書には、中小企業経営者が自社ブランドについて深く思索するためのヒントが、随所にちりばめられているのです。
石井淳蔵著/碩学舎/2022年8月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






