『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第23回/『リモート経済の衝撃――日本経済再建のラストチャンス!』
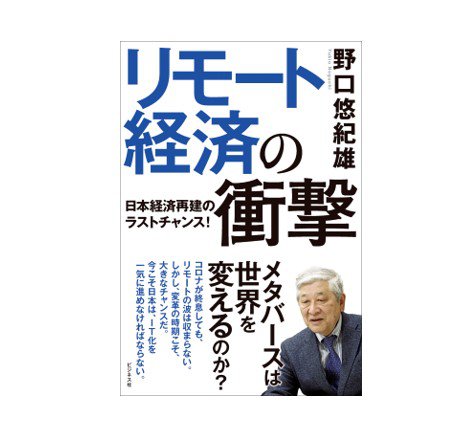
「人生100年時代」のロールモデル
野口悠紀雄氏は東京大学、早稲田大学などの教授を務めた高名な経済学者ですが、同時に、『「超」整理法』シリーズなど、多くの一般向けベストセラーを持つ人気著者でもあります。
私が感心するのは、氏は1940(昭和15)年生まれですでに80歳を超えているのに、最先端のITツールを見事に使いこなし、あまつさえその解説書を刊行し続けている点です。
同年輩の人たちの中にはいまだにスマホもPCも使えない人たちが多いのに、野口氏の知的活動の旺盛さには敬服します。
この近著『リモート経済の衝撃』においても、話題の「メタバース」(仮想空間を用いたサービスの総称)の解説を盛り込むなど、その知的好奇心は衰えを知りません。
野口氏は貪欲に学び続けています。
たとえば、70歳を超えてから、仕事に直接関係のないロシア語を本気で勉強し始めたそうです。そのことについて、2011年刊の旧著『実力大競争時代の「超」勉強法』(幻冬舎)では、次のように書いていました。
《勉強するのに遅すぎることはない。トルストイは70歳を過ぎてからイタリア語の勉強を始めた。私は、昔この話を聞いて感心したのだが、最近、「なんだ。大したことはない。自分もやっている」と気がついた》
「人生100年時代」の到来が言われる一方、『80歳の壁』(和田秀樹著)がベストセラーになり、80歳を目前にして寝たきりや要介護になる人が多いと指摘される昨今です。そうしたなかにあって、学び続け、書き続ける野口氏は、後期高齢者の生き方の一つのロールモデルとなるでしょう。
「野口悠紀雄さんがあれだけ頑張っているのだから、私も頑張ろう」と、シニア層の背中を押し、また、シニア層が最先端のITツールに接するためのよき指南役となっているのです。
リモート化を不可逆の大転換と捉える
さて、今回紹介する『リモート経済の衝撃』は、書名のとおり、コロナ禍で一気に加速した「リモート化」――リモートワークの広がりを、社会や経済を一変させる大変革として捉えた概説書です。
Zoom等のツールを介して行うリモート会議に代表されるリモートワークは、コロナ禍からの2年間ですっかり一般的になりました。
それでもなお、多くの人がこの変化を一時的なものとして捉え、「コロナが収束すれば元に戻る」と考えているでしょう。
しかし、著者はそうした見方を否定します。きっかけはコロナ禍であっても、すでにリモート化への扉が開いてしまった以上、それは不可逆の大転換となり、コロナ収束後も社会は元に戻らないと言うのです。
《リモートとはリアルの代替物ではなく、新しい大きな可能性を開くものだ。このことは、すでに企業の業績に現れている。(中略)産業構造は、リモート化によって大きく変わりつつあるのだ。
日本がリモートの広がりを一時的なものと考えて対応を誤れば、技術の大きな転換に再び乗り遅れるだろう。
最初の乗り遅れは、インターネットを中心とするIT革命だった》
そのような認識のもと、企業も個人も、リモート化という大転換に適応して変わっていくべきだと説く本なのです。
リモート化が不可逆である一つの証拠として、本書では出張費の削減傾向が挙げられています。
《企業はコロナ下の状況をきっかけに、「出張」のあり方を見直している。
これまで出張によって行なってきた業務を、テレビ会議などのリモート手段で代替できることがわかった。それによって多大の経費を節減できることがわかった。つまり、これまでは深く検討することなく、無駄な出張を惰性的に続けてきたことがわかったのだ。ことに遠距離出張について、そのことがいえる》
《マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツ氏は、2020年 11 月中旬に行われたニューヨーク・タイムズ紙主催のイベントで、「出張需要の 50% は未来永劫、戻らない」と予測した。そして、「今後は、会議や商談のために出張することは〈非常に高いハードル〉になる」ともした。
Zoom創設者のエリック・ユアン(袁征) 氏も、Zoomの急成長にコロナ下の特殊事情が反映していることは認めつつも、ビデオ会議の利用が永続的な変化につながるだろうとしている。これまでの出張の多くは、費用や時間的損失などを考えると、正当化できないという。したがって、コロナが終息しても、出張は元に戻らない可能性が高い》
リモート化の波は中小企業のビッグチャンス!
『リモート経済の衝撃』という書名だけを見ると、「リモート化に乗り遅れると大変なことになる」と不安を煽る本のように思えるかもしれません。
しかし、読めばそうではないことがわかります。副題に「日本経済再建のラストチャンス!」とあるように、本書はむしろ、リモート化の波を日本経済の再生につながるチャンスとして捉える本なのです。
また、企業や個人にとっても、リモートの波はうまく乗ればビッグチャンスになる――著者は本書の中で、そのようにくり返し強調します。これは、リモート化のプラス面に光を当てた、希望に満ちた書なのです。
本書は、オンライン教育や遠隔医療など、リモート化のさまざまな側面を、各一章を割いて扱っています。つまり、リモート化の全体像を捉えたものであり、ビジネス面のみを扱った本ではありません。
それでも、本書は企業経営者、とくに中小企業経営者に薦めたい内容です。
というのも、リモート化の波が中小企業にとって大きな福音になり得ると、随所で感じさせるからです。
明るい未来が見えてくる本
たとえば、リモート化によって「本当の意味での地方の時代が始まる」(第3章の小見出しの一つ)と、著者は言います。
《在宅勤務は、従業員にとって魅力的なオプションだ。悪天候の日に無理して出社する必要がないし、通勤ラッシュから逃れることもできる。
都心に通勤しないで済むなら、郊外や地方都市に住んで働くこともできる。そして、住居費を節約することができる。
会社側としても、多様な働き方を認めることによって、人材の確保が以前よりも容易になる。
また、家賃の高い大きなオフィスを借りる代わりに、小さめのスペースを借りることによって経費を削減できる。オフィスは「従業員が毎日集まる場所」から、重要な会議や共同作業のための「ミーティングスポット」に変わっていくだろう》
このような変化によって、東京一極集中による地方企業の不利は、かなり解消されていくでしょう。
また、都市部の中小企業にとっても、重い負担であるオフィス維持費用が大幅に削減できることが、追い風となるでしょう。
さらに、中小企業にとって大きな課題である人材確保の面でも、リモート化は福音です。
《採用面接は、大学講義のオンライン化率と並んで、日本でもっともオンライン化が進んでいる分野であろう。(中略)
オンライン面接の広がりは、学生にとっても企業にとっても、面接の機会を増大させるという意味で歓迎すべき変化だ。実際、多くの学生が、オンライン面接をよいことだと考えている。
地方に住んでいる学生が東京など大都市にある企業の面接を受けようと思えば、これまでは東京まで出かける必要があった。だから、受けられる企業の数が限定された。面接の機会という点で、地方居住者が不利だったことは否定できない》
これも、地方の企業に限ったことではありません。
採用時のオンライン面接や在宅勤務があたりまえになり、国内どこでも、あるいは海外から勤務できるようになれば、中小企業もよい人材が採用しやすくなるでしょう。
そのように、中小企業経営者にとって、読んでいると未来に希望が湧いてくる本なのです。
本書は、日本社会、とくに企業のリモート化への対応が、諸外国に比べて遅れていることを憂える内容でもあります。
その点でも、小回りが利かず、急には変われない大企業に比べ、中小企業のほうが変わりやすいはずです。中小企業にはオーナー経営者が多く、組織も比較的小規模であることから、経営者の決断一つで一気に変わり得るからです。
《デジタル時代を「生き抜く」とか、「生き延びる」とか、「対応する」という発想が出てくるのは、デジタルが「敵」だと考えているからだ。だから、「それに負けないためにはどうすればよいか?」ということになる。
しかし、デジタルは敵ではない。うまく利用すれば味方になる。しかも、強力な味方になる。考え方の基本を転換させ、どうしたらデジタル化を自分の味方にできるかを考えるべきだ》
著者がそう言うように、中小企業経営者はいまこそ、リモート化の大波にうまく乗り、デジタル化を自社の味方にすることを考えるべきなのです。
また、新たなオンライン・ビジネスのヒントも多数挙げられており、その点でも中小企業経営者に有益でしょう。
野口悠紀雄著/ビジネス社/2022年1月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






