『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第21回/『イノベーションの競争戦略――優れたイノベーターは0→1か? 横取りか?』
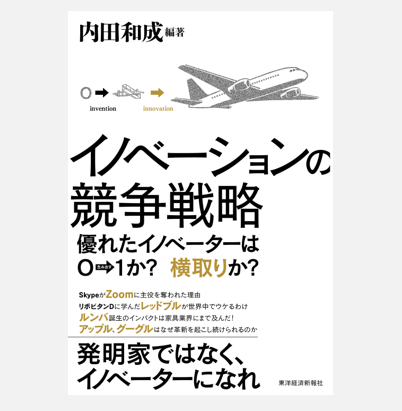
読者のイノベーション観を一変させる本
『理念と経営』2022年8月号(7月21日発売)では、経営学者の内田和成先生と、凸版印刷株式会社の金子眞吾会長の「巻頭対談」を掲載しています。
その内田先生の新著を、今回は取り上げましょう。
『理念と経営』にくり返しご登場いただいている内田先生は、2000年から04年にかけて「ボストンコンサルティンググループ(BCG)」の日本代表を務め、06年には米『コンサルティング・マガジン』によって「世界の有力コンサルタント25人」に選出されています。
また、06年から22年3月までは早稲田大学ビジネススクール教授として、競争戦略論やリーダーシップ論などを講じてきました。
本書は内田先生の「早稲田大学時代最後の書籍」であり、内田ゼミの卒業生たちと立ち上げた「イノベーション研究会」の研究成果をまとめたものです。
「イノベーション本」はビジネス書の定番の一つであり、すでに汗牛充棟ですが、その中にあって本書は一頭地を抜くものといえます。読者のイノベーション観を一変させるほど、新鮮な驚きに満ちた内容なのです。
イノベーションの本質は「行動変容」
イノベーションというと、多くの人は画期的な技術革新や発明を思い浮かべるでしょう。
だからこそ、中小企業経営者の中には、「うちみたいな小さな会社にはイノベーションなんて無理だ」とか、「うちは文系の会社だからイノベーションなんて関係ない」などと決めつけてしまう人も少なくないのです。
中小企業経営者に限ったことではありません。日本には、「イノベーションとは画期的な技術革新や発明のこと」という偏ったイメージが深く根付いてしまっています。
その原因の一つは、本書にも言及があるように、1956(昭和31)年の『経済白書』で「イノベーション」が「技術革新」と訳されたことでしょう。以来、現在に至るまで、「イノベーションのゴールとは技術革新である」という認識が広まってしまっているのです。
そのため、昨今盛んな「近年の日本企業にはなぜイノベーションが生まれないのか?」という議論では、しばしば、画期的発明やアイデアの不足が問題視されます。
「かつてウォークマンのような画期的商品を多く生み出した日本が、なぜiPhoneのような商品を生み出せなくなったのか?それは開発力の枯渇が原因だ」といった言い方がされがちなのです。
しかし、内田先生らが「イノベーション研究会」で調査・研究・議論を進めた結果、問題の本質はそこにはないことがわかりました。
《世の中に存在しなかった画期的な発明やサービスは、企業におけるイノベーションの必要条件ではないということである。それよりも新しい製品・サービスを消費者や企業の日々の活動や行動の中に浸透させることこそがイノベーションの本質である。
我々はこれを行動変容と呼ぶが、これこそが企業がイノベーションを起こすためのカギとなる。そのことを皆さんに知ってもらいたいという想いが本書執筆の動機となっている》(「序章 イノベーションを問う」)
つまり、日本人の多くが「画期的な発明やサービスを生み出すこと」をイノベーションのゴールと捉えてきたのに対し、本書はそれによって世の人々を「行動変容」させることをゴールと捉えるのです。ここには、イノベーション観の大転換があります。
本書におけるイノベーションの定義は、「これまでにない価値の創造により、顧客の行動が変わること」です。
「価値の創造」は、技術革新や発明による場合もあれば、そうではない場合もあります。そして、たとえ画期的な発明・技術革新であっても、それが行動変容に結びつかなければイノベーションではない――そのように捉えるのです。
行動変容の前段階が「態度変容」で、「特定の対象・状況に対して多くの人々が共有する概念・価値観・基準を変えること」を指します。
イノベーションが起きるときには、まず「態度変容」が起き、それが進むと「行動変容」となって、人々の習慣自体が大きく変わります。そこまでに至って初めてイノベーションと呼び得るのです。
そして、《企業が価値創造をしながらも、顧客に態度変容が起こらなかった事例のほうが圧倒的に多い》と、本書は指摘します。
たとえば、アメリカで2000年に生まれた「セグウェイ」という電動立ち乗り二輪車がありました。スティーヴ・ジョブズやビル・ゲイツも絶賛したといわれる革新的乗り物でしたが、広く普及しないまま、2020年にひっそりと生産終了しました。
《セグウェイは偉大な発明(インベンション)だったが、世の中を変えるイノベーションにはなり得なかった》のです。
「油揚げをさらったトンビ」がイノベーターになる
逆に、「技術的に新しさはなくともイノベーションと呼べる商品、サービスは存在する」と、本書は言います。
たとえば、コロナ禍以後、オンライン会議ツールとして最も広く普及したのは「Zoom」です。しかし、オンライン会議ツールには「Skype」という先行者があり、Zoomは発明とは言えません。また、Skypeに比べて格段に優れた機能があったわけでもありません。
にもかかわらず、コロナ後に勝者となったのはZoomであり、Skypeは20~21年にかけて25%以上もシェアを落としました。
オンライン会議を日常的なものにする「行動変容」を短期間で引き起こしたのは、Skype ではなくZoomだったのです。その意味で、Zoomはまぎれもないイノベーションでした(なぜZoomが勝ったのかについては、本書に解説があります)。
同様に、発明したのは別の企業だったのに、行動変容を起こしてイノベーションの勝者となったのは後発企業だったという事例が、本書にはたくさん紹介されています。
たとえば、電子書籍リーダーの「Kindle」には、ソニーの「LIBRIe」(リブリエ)という先行例がありました。
Kindleは、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスがLIBRIeに衝撃を受けて開発を始めたものでした。しかし、結果的に行動変容を起こして生き残ったのはKindleだったのです(LIBRIeは2007年に生産終了)。
この例一つとっても、「近年の日本にイノベーションが生まれないのは、技術力・発明力が低下したからだ」という言説は眉唾でしょう。日本企業にはまだ、世界に先駆けるだけの技術力・発明力があるのです。
ただ、日本企業には開発をゴールと捉え、その後の行動変容に重きを置かない傾向があり、それがイノベーションの阻害要因となっています。本書ではそのことが、次のように表現されています。
《新しい価値を生み出した先に、人々の意識を変え(態度変容)、それを行動として定着させるためには、単なる発明や新製品にはとどまらない仕掛け・仕組みが必要となる。日本企業が勘違いしていて、このプロセスを軽視あるいは無視しているのが日本でイノベーションが定着しない1つの理由と思われる》
さらに、昨今の日本にイノベーションが生まれにくい背景として、本書は次のような傾向を挙げます。
《自分のところで生まれたものでなければ価値がない、あるいは人のものを真似するのはけしからんといった価値観が日本企業にはある。(中略)なぜ日本にイノベーションが生まれにくいのかと考えると、はじめから最後まで自分で成し遂げるのが一番よくて、途中で人の手を借りるのは次善の策である、さらには人の成果を横取りするのは下策であるといった考えがあるからではないだろうか》
しかしいまや、すべてを自社でまかなうのは困難な時代です。
じっさい、アップルなどは製品の製造を完全にアウトソーシングしています。日本企業が極端な「自前主義」を放棄することも、イノベーション力アップのためには不可欠だと、本書は提言しています。
そして、《人の成果を横取りするのは下策》といった古い価値観を捨て、他企業が開発した商品・サービス・技術の弱点を補ったり、効果的な仕組みを考えたりして行動変容を起こすことに、もっと積極的になるべきだと本書は訴えます。
《トンビに油揚げをさらわれるという格言があるが、油揚げをさらったものがイノベーターである》
ある商品やサービスを発明した者がイノベーターなのではなく、それを普及させて行動変容を引き起こした者こそがイノベーターなのです。「優れたイノベーターは0→1か? 横取りか?」という本書の副題は、そのことを示しています。
イノベーションの事例集として貴重な一書
以上のような斬新なイノベーション観を、著者たちはくわしいメカニズムに腑分けして解説しています。
《本書では、イノベーションを引き起こす源泉である、社会構造、心理変化、技術革新を「イノベーションのドライバー」、そしてその組み合わせを「イノベーションのトライアングル」と定義する》
そして、その定義に基づくイノベーションの創出プロセスを以下の4つに分け、それらをまとめて「イノベーションストリーム」と呼んでいます。
《ステップ1 トライアングルによりドライバーを捉える
ステップ2 ドライバーを梃子に新しい価値を創造する
ステップ3 顧客の態度が変わる
ステップ4 顧客の行動が変わる》
そのうえで、「イノベーションのトライアングル」と「イノベーションストリーム」の各要素について、1つずつ詳細に解説していくのです。
それらの解説の中では、具体的な企業のイノベーション事例が逐一挙げられていきます。頭の中だけで考えた机上の空論は、ただの一つもありません。
よく知られた企業の事例を通じて解説されることで、読者は「なるほど、そういうことか」と、著者たちのイノベーション理論がすんなり理解できるのです。
本書はイノベーション理論として画期的なものですが、同時に、イノベーションの成功(失敗)事例集としても高い価値を持ちます。
2年に及んだという「イノベーション研究会」で集められ、詳細に検討されたイノベーション事例は、1000件近くに上ったといいます。
そうした豊富な事例から導き出された、企業がイノベーションを起こすための要諦が、本書にはまとめられているのです。
自社の商品やサービスを通じてイノベーションを起こしたいのに、起こせない――そんな思いに悶々としている中小企業経営者にとっては、得難いヒント集になるでしょう。
内田和成編著/東洋経済新報社/2022年4月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






