『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第11回/『大人のいじめ』
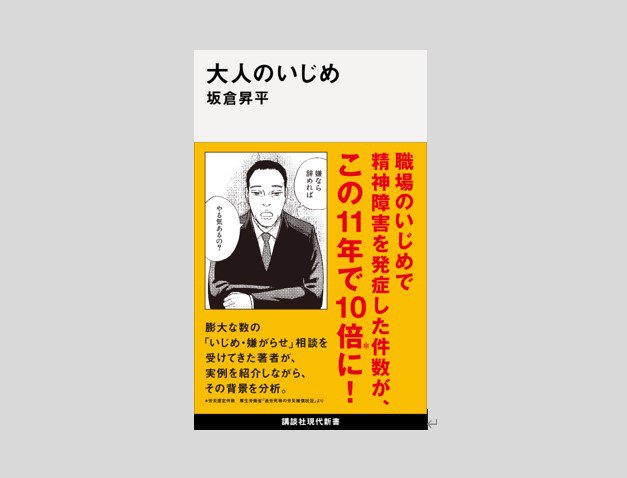
「職場いじめ」の衝撃的な実態を明かす
この連載では基本的に“読んで元気になれる本”を取り上げたいと思っていますが、今回は例外です。
むしろ、中小企業経営者が読むと、気持ちがどんより暗くなってしまうかもしれません。しかし、あえて取り上げます。本書の苦い読後感は“良薬の苦さ”であり、経営者が知っておくべきことが満載だからです。
『大人のいじめ』というタイトルですが、内容は「職場のいじめ」の概説書です。職場以外で起きる「大人のいじめ」は、本書では扱っていません。
著者は労働問題に取り組むNPO法人「POSSE」の理事であり、ハラスメント対策の専門家。年間約5000件もの労働相談に関わっているそうです。
豊富な経験・知識を踏まえ、本書では職場いじめの衝撃的な実態が明かされています。
厚生労働省の「個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、職場いじめに関する労働相談が、過去10年で激増しているそうです。
《2011年度までこの統計で長らく1位だったのは「解雇」だが、ここ10年以上は減少傾向にあり、入れ替わるように「いじめ・嫌がらせ」が大幅に増加した。「いじめ・嫌がらせ」は2011年度に4万5939件だったが、2012年度には約5万件と「解雇」を抜いて1位になり、2013年度は「解雇」を引き離して約6万件、その後も増加を続けて、9年連続トップとなっている。件数も、10年間で2倍近くに跳ね上がった》
そうした時代の変化を受けて書かれたのが、本書であるわけです。
全7章立てで、そのうちの4章(第2章から第5章)までは、著者たちが実際に受けたいじめ相談の事例紹介に充てられています。
また、第1章も《最新の統計や報道された事例を見ながら、近年の職場いじめの特徴を抽出する》内容です。
つまり、本書は何よりもまず、近年の職場いじめの事例集なのです。
その具体的内容にはここでは触れませんが、言葉の暴力、肉体的暴力など、信じられないほどひどい事例が多数登場します。
《業務による精神障害の最たるものとして、「過労自死」「過労自殺」という言葉がよく使われてきたが、いまやその大半は「ハラスメント自死」「職場いじめ自死」という表現の方が当たっているのではないだろうか》
……とあるとおり、被害者の自死につながるほど深刻なケースも多いのです。
“いじめを生む構造”にまで迫る
本書は職場いじめの具体例紹介が内容の過半を占めますが、単なる事例の羅列には終わっていません。
著者は、いじめの類型をくわしく腑分け・分析したうえで、背後にある“いじめを生む構造”にまで迫っているのです。
職場いじめは、パワハラ、セクハラなどの言葉がなかった昔からあったでしょう。ただ、近年になって明らかに増加・深刻化しているのです。
それはなぜか? 著者は《近年見られる職場いじめには、これまでとは異なる傾向がある》として、3つの特徴を挙げています。
① 過酷な労働環境――いじめのある職場は、ない職場に比べ、長時間労働の割合が2倍以上だという調査結果が紹介されます。
② 職場全体の加害者化――「職場いじめ」と聞いて、経営者や上司によるパワハラを連想する人は多いでしょうが、いまでは約半数が同僚によるいじめだそうです。
③ 会社による「いじめの放置」――被害に遭った従業員からハラスメント相談を受けても、無視する会社が約5割にのぼるそうです。
そうした傾向の背景に、《近年の日本の産業構造の変化と日本企業の労務管理の変容がある》と、著者は指摘します。
《サービス業を中心に、基幹的な業務が単純化・画一化・マニュアル化され、非正規雇用にも任されるようになった。低賃金にもかかわらず、責任や業務量は膨大になっていった。
こうした余裕の失われた職場で、職場いじめは加速した。過酷な労働は、ストレスの「はけ口」を求める。そのうえで、「生産性」が低く、「効率」の悪い労働者が、「職場に迷惑をかける」存在として、「いじめても良い」「人として扱わなくても許される」対象となったのである》
脳科学者の中野信子さんがいじめ問題を論じた、『ヒトは「いじめ」をやめられない』(小学館新書)という著作があります。
同書で中野さんは、人間の集団に「いじめ」が生まれるのは、脳内ホルモンの働きなどから必然的なことだと指摘しています。
向社会性(「反社会性」の対義語)を司る「愛情ホルモン」である「オキシトシン」や、「安心ホルモン」と呼ばれる「セロトニン」が、じつはいじめを生み出すメカニズムに深く関わっているというのです。
それらの脳内ホルモンは、集団内に「絆」意識を育むプラス面を持つ一方、集団を守るために異質な分子を排除する攻撃性につながってしまうマイナス面もあるのです。
いじめは脳のメカニズムが必然的に生み出すものなのだから、ゼロにすることはできない。だから、ゼロを目指すのではなく、できるだけ回避する方策を考えたほうがよい……と、中野さんは言います。
この『大人のいじめ』を読んで、その主張を思い出しました。職場いじめの急増にも、労働環境の悪化などが生み出した必然という側面があります。昔に比べて人々の人間性が劣化したわけではないのです。
経営者は本書を読んで防止策を
最後の第7章では、《職場のいじめ、ハラスメントをなくしていくには、どうしたら良いのだろうか》と、「ハラスメント対策」の今後が展望されています。
暗澹たる気分になるそれまでの章と比べ、希望の光が感じられ、読者もホッとするでしょう。
そして、巻末には「付録」として、著者の豊富な経験を踏まえた《職場いじめに悩む人への実践的アドバイス》が掲載されています。
「付録」と言いつつ、長文の充実した内容であり、当事者には大変有益なアドバイス集です。実際に職場いじめを経験した人は、本文を読むと被害がフラッシュバックしてつらいかもしれませんから、「付録」だけ読んでもよいでしょう。
本書に登場するようなひどい職場いじめは、『理念と経営』読者諸氏の会社にはないと信じます。
ただ、中小企業経営者は、このようないじめが起こり得ることを想定して、ふだんから防止策を講じておくべきでしょう。
本書には、そのためのヒントもちりばめられています。たとえば――。
《ハラスメントの加害者にならないよう管理職に研修を実施する企業はそれなりにあっても、被害を受けやすい一般の従業員(非正規雇用を含む) に対して、何がハラスメントにあたるのか、自分にどのような権利があるのかを教える企業はほとんど聞かない》
これなどは、中小企業経営者にとっても耳の痛い指摘ではないでしょうか。
一般社員の側に立って書かれた本ではありますが、経営者も「職場いじめ」防止のために必読の一冊です。
坂倉昇平著/講談社現代新書/2021年11月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






