『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第9回/『マインドセット――「やればできる!」の研究』
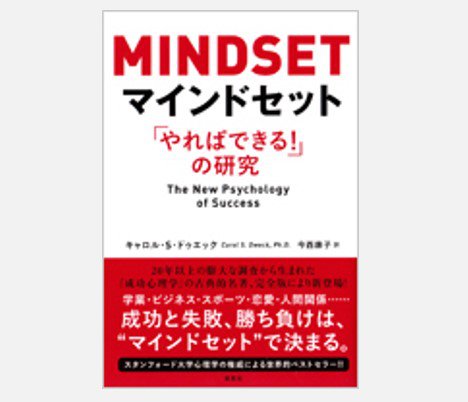
人材育成で肝に銘じるべきこと
著者のキャロル・S・ドゥエックは、米スタンフォード大学の心理学教授で、「パーソナリティ、社会心理学、発達心理学の分野における世界的な権威」です。
タイトルの「マインドセット(mindset)」とは、心のあり方、思考様式のこと。
著者によれば、「自分の性格だと思っているものの多くが、じつはこの心のあり方(=mindset)の産物」なのだそうです。
この「マインドセット」こそ、著者が長年研究テーマに据えてきたもの。そして、その研究の結果、マインドセットが人生を決定づける要因であることがわかってきたのです。
《あなたがもし可能性を発揮できずにいるとしたら、その原因の多くは〝マインドセット〟にあると言ってよい》
本書は、「マインドセット」についての著者の研究を、一般向けに咀嚼して紹介したものです。悪いマインドセットをよいマインドセットに変え、能力を開花させていくためにはどうすればよいかが、くわしく解説されています。
自分を変えるきっかけにもなり得る本ですが、何より、子育てや教育、ひいては人材育成全般で肝に銘じるべきことが書かれた一冊です。
社員を成長させるホメ方とは?
著者は本書で、2つの代表的マインドセットを対比させて論を進めていきます。
自分の能力は固定的で変わらないと信じている「硬直マインドセット=fixed mindset」と、自分の能力は努力しだいで伸ばすことができると信じている「しなやかマインドセット=growth mindset」です。
たとえば、子どもがどちらのマインドセットを持つかによって、学習意欲や成績には大きな差が生じます。「しなやかマインドセット」の持ち主のほうが、頑張って勉強に取り組み、成績も上がっていきやすいのです。
《しなやかなマインドセットの根底にあるのは、「人は変われる」という信念》だからこそ、変わろうとする意欲につながるのでしょう。
そして、2つのマインドセットは、成人後の人生も大きく左右していきます。
「硬直マインドセット」の人は、失敗したときにそれ以上の努力をしようとはなかなか思えません。そして、自分に対する他人の評価をいつも気にしています。
逆に、「しなやかマインドセット」の人は、失敗したときにも粘り強く努力を続けることができ、他人の評価よりも自分の能力を伸ばすことに関心を向けます。
そのようなマインドセットの違いは、年月を重ねるほど、あらゆる面で能力差となって現れます。それが、幸・不幸を大きく分かつのです。
著者によれば、マインドセットは努力によって変えられます。つまり、誰もが「しなやかマインドセット」を身につけ、よりよく生きられるようになるというのです。
本書には、「しなやかマインドセット」になるためのコツもさまざま紹介されています。ただし、次の一節が示すとおり、それはたやすいことではないようです。
《人のマインドセットは、小手先のテクニックで変えられるようなものではない。マインドセットが変化するということは、ものごとの見方が根底から変化することなのだ》
著者が教育分野で長年研究してきた人だけに、本書でも教育における「しなやかマインドセット」の大切さについて、かなりの紙数が割かれています。
とくに、親や教育者の接し方しだいで子どものマインドセットが変わるという話は、たいへん示唆的です。
よく「子どもはホメて育てろ」といいますが、著者によれば、「硬直マインドセット」を助長する有害なホメ方もあるそうです。
たとえば、子どもの才能や頭のよさをホメると、むしろ努力・挑戦への意欲を削いでしまいます。“能力は持って生まれた固定的なものだ”というメッセージを、子どもに伝えてしまうからです。
《何百人もの子どもたちを対象に、7回にわたる実験を行った結果はきわめて明快だった。頭の良さをほめると、学習意欲が損なわれ、ひいては成績も低下したのである》
それは、企業における人材育成にも言えることでしょう。
ホメて育てる姿勢が悪いわけではありませんが、ホメるなら、社員の才能や頭のよさではなく、努力や成長ぶりをこそホメるべきなのです。
そのためには、経営者や上司が社員をよく見守り、努力や成長に気付かなくてはいけません。
マインドセットと社風の密接な関係
本書の第5章は、「ビジネス――マインドセットとリーダーシップ」と銘打たれています。企業経営とマインドセットの関係について論じられた章なのです。
中小企業経営者には、本書の中でもとくに熟読していただきたい章です。
章の冒頭では、2001年に起きた米エンロン社の経営破綻が取り上げられています。全米有数のエネルギー企業で、エリート揃いのエンロンが粉飾決算を機に破綻した事件は、「エンロンショック」とも呼ばれました。
著者は、エンロンを破綻に導いたのは「才能崇拝の企業文化」であり、社内全体に蔓延した「硬直マインドセット」であったといいます。
《エンロンは、才能を盲信したがために、致命的な誤りを犯してしまったのである。才能崇拝の企業文化がつくられて、社員たちは並外れた才能の持ち主であるかのような振りをせざるをえなくなった。つまり、硬直したマインドセットに陥るはめになったのである。そのあとはもうおわかりだろう。私たちの研究から示されたように、硬直マインドセットの人は自分の欠点を認めないし、改めようともしない》
硬直マインドセットは個人をスポイルしますが、それが一つの企業文化にまで広がると、社員全員をスポイルしていくというのです。
著者は、経営者のマインドセットが企業文化にも反映されていくと指摘します。
硬直マインドセットの持ち主が経営者になれば、企業全体も硬直マインドセットに染め上げられ、やがて業績にも悪影響が生じます。
逆に、しなやかマインドセットの持ち主が経営者になれば、企業文化もしなやかマインドセットに沿ったものになり、業績も上がっていく、と……。
著者は、米国の大企業から“硬直マインドセットの悪しき経営者”と、“しなやかマインドセットのよい経営者”の実例を挙げ、両者を比較していきます。
とくに目を引くのは、名経営者として称賛されることも多いリー・アイアコッカ(フォード社元社長、クライスラー社元会長)が、悪しきリーダーの典型として厳しく批判されている点です。
《アイアコッカは硬直マインドセットの世界に生きていた。たしかに入社当初は自動車ビジネスを心から愛し、画期的なアイデアにあふれていたのだが、そのうちに、人よりも優れ ていることを証明したいという欲求がまさってきて、ついに、楽しむ気持ちを殺し、創造性の息の根を止めてしまうまでになる。時とともにますますその傾向は強まり、競争相手の挑戦を受けて立とうとはせずに、非難、言い訳、批判者やライバルの抑え付けといった硬直マインドセットの武器を振り回すようになっていった》
この章は、一般の経営書にはない斬新な切り口から、経営者の持つべき心構えを論じた内容であり、読み応えがあります。
人材育成とリーダーシップについて、心理学のたしかな研究成果を踏まえて論じた、ユニークな一冊です。
キャロル・S・ドゥエック著、今西康子訳/草思社/2016年1月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






