『理念と経営』WEB記事
企業事例研究1
2022年3月号
お客様の困り事にこそ、商機がある
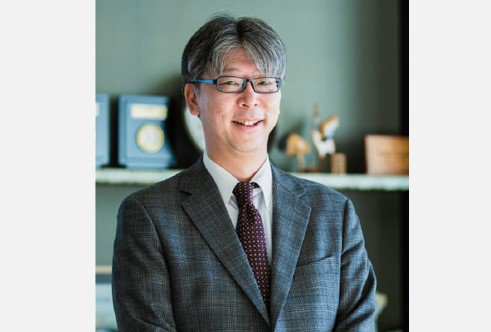
株式会社ニッコー 代表取締役 佐藤一雄 氏
自らもエンジニアである、株式会社ニッコー(北海道釧路市)の佐藤一雄社長は、加工機械のオーダーメードを展開するニッチ戦略で、独自のポジションを築いた。その源泉には、創業者の父から受け継いできた地域貢献の志と、変化をいとわないチャレンジ精神がある。
「地場産業の発展」に役立つ機械を作る
太平洋に面する北海道東部の都市・釧路市は、かつて日本有数の漁業基地だった。70年後半から80年代にかけて、サケやスケソウダラ、サバ、マイワシなどの漁で沸き日本一の水揚げを誇った。
ニッコーは、そんな漁の活況が続く1977(昭和52)年、東京の機械メーカーに勤めていた、現会長の佐藤厚さんが郷里の釧路に戻り創業した会社である。
自分も含めて3人。ビルの一室を事務所に借り、貸し倉庫を工場にスタートした。昇った日がますます輝きを増していくように、社名には「日興」という言葉が浮かんだ。しかし、「当時の流行りでカタカナにしたようです」と、二代目の佐藤一雄さんは言うのだ。
————「地場産業の発展に役立つ機械を作りたい」という思いが会長の創業の志だったそうですね。
佐藤 父が釧路に戻ってきた当時は水産加工場がたくさんあったんです。その働く現場を見ると、労働集約的で大変な仕事だった。なんとか楽に仕事ができるようなお手伝いができないかという気持ちだったと聞いています。
————それで水産加工に特化した機械を作り始められたわけですね。
佐藤 サケの加工機械から始めたようです。当時は釧路にもサケがたくさん水揚げされていて、そのサケの頭を落とし内蔵を取り出すという一次加工の機械を作ったのです。この作業の効率化を図ろうと、機械の開発を始めました。
————サケの加工機械は今もニッコーの柱の一つだそうですね。
佐藤 はい。現場のお客様の話を聞き、その時その時の課題を解決するために改善を繰り返していって、いまではサケだけで18種類ほどの機械があります。なかでもサケを切り身にしていく機械は当社のロングセラー製品です。
————ホタテの貝柱を取り出す機械でも、知られていますね。
佐藤 97(平成9)年に完成した世界初のホタテ貝の自動生剥き機は、特許も取得している世界では当社だけの製品です。
————ホタテに着目されたのは?
佐藤 当社の創業した年に、200海里(370km)の経済水域が設定されました。
————それぞれの国の沿岸から200海里の中には外国船は勝手に入って漁をしてはいけないという国際協定ですね。
佐藤 この協定は、さかんに遠洋漁業を行っていた日本の水産業に大きな影響を与えるようになりました。年を経るごとに漁獲量が減っていき、事業の安定には養殖にも目を向けていこうということでホタテ関連に参入したのです。
————世界初の技術ということですが、一番苦労されたのは?
佐藤 私はまだ入社していなかったのですが、いかにして生の状態でホタテ貝の殻を開けるかという技術開発に苦労したと聞いています。無理矢理開けてしまうと、貝柱の繊維が殻についてしまってきれいな形の貝柱が取れないんです。いろいろ試行錯誤して、殻に蒸気を当てる方法を編みだしたのです。
————効率は上がりましたか?
佐藤 それまで人がヘラを貝の口に突っ込んで手作業で開けていたのですが、能力でいくとこの機械は一台で11人分に相当します。
顧客との「雑談」からニーズを引き出す
————入社は2001(同13)年だと聞いています。
佐藤 そうです。28歳の時でした。私は、地元の釧路工業高等専門学校(釧路高専)を卒業して、東京で大手ロボットメーカーに勤めていました。その会社が企業グループ内で統合されることになり、いい機会だと戻ってきたのです。小さい時からずっと父に会社を継げと言われてきたものですから……。入社後は一年ほど本社にいて、関東進出のため東京営業所の立ち上げを任されました。
————東京では、水産加工会社を回られたのですか?
佐藤 実は、私がまだ前の会社に勤めていた頃に、アメリカに食品産業向けのロボットを作っているメーカーがあるということを知って、それを父に話したんです。水産業自体の見通しが暗くなってきた時期で、新しい市場を求めていたのだと思います。父はすぐに「それだ。それをやっていこう」と決断しました。そのメーカーと提携し、すでに食品加工全体を見据えるようになっていました。だから水産だけでなく畜産や農作物など食品加工の会社全般です。2、300社くらいでしょうか。けっこう回りましたね。
————先方の反応はいかがでした?
佐藤 いや大変でした。北海道の会社で、しかも釧路です。機械メーカーというイメージはありませんよね。営業に伺っても「何で北海道の会社さんが……」という感じでした。“本当に大丈夫?”と思われている様子が伝わってくるんです。なんとかそれを駆逐したいと、とにかく先方の会社を訪ねては雑談を重ねていきました。
————雑談ですか?
佐藤 ええ。お客様と雑談しながら「こういうことで困っているんだよね」という話を引き出して、その困り事を解決するための具体的な提案を考えて持っていくわけです。
取材・文 中之町新
写真提供 株式会社ニッコー
本記事は、月刊『理念と経営』2022年3月号「企業事例研究1」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






