『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第5回/『上流思考――「問題が起こる前」に解決する新しい問題解決の思考法』
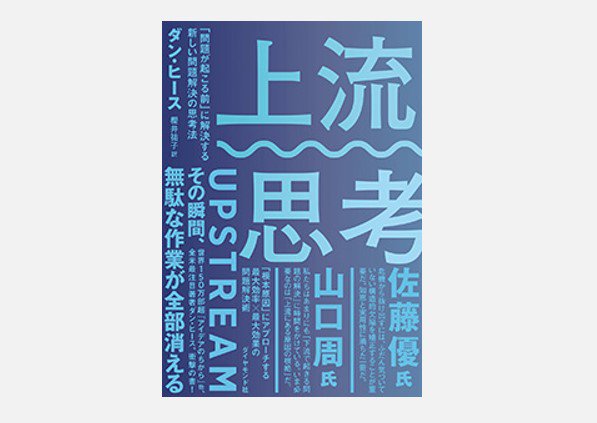
問題を根源から解決するための本
まず、タイトルの印象による誤解を解いておきましょう。
これは、いわゆる「上流階級」(アッパークラス)になるための本ではありません。「大富豪ならではの思考法を身につければ、あなたもお金持ちになれます!」とうそぶくような、鼻持ちならない本ではないのです。
本書の「上流思考」(原題は“UPSTRREAM”=「上流」)とは、物事を「川上」から、つまり根本原因に目を向けて考えることを指します。
医療でいえば、治療よりも予防を重視するのが「上流思考」です。
そもそも、治療を「川下」に喩え、予防を「川上」に喩えるのは、予防を重視する「社会疫学」の世界で始まったことなのです。
社会疫学研究の第一人者イチロー・カワチ(ハーバード公衆衛生大学院教授)氏は、著書『命の格差は止められるか――ハーバード日本人教授の、世界が注目する授業』(小学館101新書)の中で、次のように書いています。
《社会疫学は、川の中でも、特に上流から問題の解決に取り組みます。我々の仕事は、上流で問題解決を図り、人が川に落ちるのを未然に防ぐのです》
本書にも、「一つの予防は百の治療に勝る」という、医学の世界で語り継がれてきた言葉が紹介されています。問題に事後的に対処するのではなく、未然に防ごうとするアプローチとそのための思考法が、「上流思考」なのです。
本書はそれを、医療のみならず、社会問題の解決、企業の問題解決、犯罪防止など、あらゆる問題に敷衍していきます。
「問題が起こる前」に解決するためには、何が必要なのか? どんな点に気をつければできるのかを、くわしく解説した本なのです。
膨大な取材による、上流介入の事例集
著者のダン・ヒースは、兄のチップ・ヒースとの共著で、『アイデアのちから』『決定力!』『スイッチ!』といったベストセラーを世に送り出してきました。それらの著書は世界でトータル300万部以上を売り上げ、33言語に翻訳されています。ビジネス書分野の人気著者であるヒース兄弟(「ハース兄弟」と表記されることも)の片割れが、今回は兄の力を借りず、一人で書いたのが本書です。
著者は、本書のために300件以上ものインタビューを行いました。ビジネス界、教育界、スポーツ界、医療業界などで、上流にアプローチすることで問題解決に成功した事例を集め、当事者たちに直接話を聞いたのです。
実際の事例を通して、上流への介入がなぜ難しいか、根本的な問題解決を妨げる要因には何があるのかが、解説されていきます。
企業においても、トラブルが起きてから対処するより、トラブルを未然に防ぐ方法を見いだしたほうが、メリットも大きいことはいうまでもありません。ではなぜ、それが難しいのか? 一つには、予防による効果は目に見えにくく、評価されにくいという問題があります。
機械の深刻なトラブルに徹夜で対処し、何とか納期に間に合わせた社員は、ヒーローとなって皆に称賛されます。一方、日々の地道なメンテナンスに努め、機械トラブルを未然に防いだ社員の功績は、目に見えないため、称賛されることもほとんどありません。
《「何かが起こらなかった」ということをどうやって証明するのか?》、《上流活動の成果はもどかしいほどわかりにくい》のです。
だからこそ、多くの組織では、リソースの多くを起きた問題への対処に厚く配分し、予防には十分なリソースが割かれません。
では、そうしたリソース配分を改善するためには、どうしたらよいか? 本書にはたとえばそうしたことが解説されているのです。
企業改革のヒントも満載
本書に登場するさまざまな分野の事例は、少し視点を変えれば、どれも企業における問題解決のヒントになります。とくに、ビジネス分野の事例には、中小企業が社内改革にそのまま応用できそうなものも多いのです。
本書に紹介された事例を一つ挙げておきましょう。それは、世界最大級のビジネス特化型SNS「リンクトイン(LinkedIn)」の例です。
リンクトインが販売する、企業の人材発掘と採用を助けるツールは、サブスクリプション方式で提供されています。これはとてもよく売れるものの、一方では解約率(サービスを更新しない顧客の割合)も高かったのです。
そこで、リンクトインでは解約を防ぐため、毎年の更新時期になると、解約可能性が高いと思われる顧客のサポートに力を入れていました。
しかしあるとき、営業部長が「解約しそうな顧客をもっと早く特定できないだろうか?」と考えたのです。まさに上流へのアプローチといえます。
データ分析の結果、申し込み後30日以内にツールを使い始めた顧客は、そのままツールを使い続ける確率が4倍も高いことがわかりました。
そこで、従来は顧客を「死守する」ために使われていた人手や資金を、顧客に使い方を教え、ツールに慣れてもらうことに配分するようにしたのです。
たとえば、「手ほどき担当者」を設け、彼らが顧客にツールの使い方を電話でくわしく教えることにしました。
その結果、解約率は2年と経たずに半減し、そのことが年間数千万ドルの利益につながったのでした。
これは、「解決すべき問題の早期警報を得るにはどうするか」を考えた上流介入の例といえます。
本書に登場する多彩な事例のほんの一端であり、ほかにも企業改革のヒントになる事例が満載の一冊です。
ダン・ヒース著、櫻井祐子訳/ダイヤモンド社/2021年12月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






