『理念と経営』WEB記事
編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」
第3回/『もし幕末に広報がいたら――「大政奉還」のプレスリリース書いてみた』
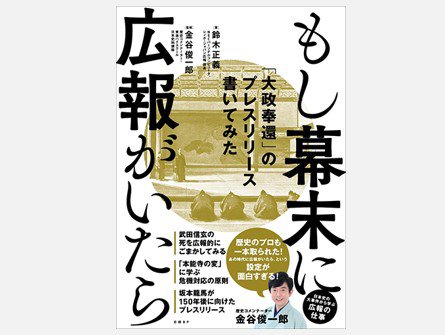
「日本史パロディ」の形を借りた広報入門
わりと堅い本が続いたので、今回は少しエンタメ寄りの本を取り上げます。昨年(2021年)暮れに発売され、大きな話題になっている一冊です。
これは、いまや一つのジャンルとして確立されている「日本史パロディ」の本。“歴史上のさまざまな大事件の現場に、現代社会のメディアやサービスなどがもしあったら、どうなっていたか?”という、「IF(もしも)」を楽しむ知的な遊びです。
ジャンルの先駆者の一人、人気ツイッタラーのスエヒロ (@numrock)さんは、ツイッター上で多種多様な日本史パロディの画像をアップし続け、すでに何冊もの本にまとめています。
そのうちの一冊『インスタ映えする戦国時代』(大和書房)は、戦国時代の有名エピソードの数々を、ネット関連ネタに置き換えていくパロディ集です。「上杉謙信から送られた塩のAmazonレビューを書く武田信玄」、「天正遣欧少年使節がYouTuberだったら」などというパロディが、次々と登場するのです。
一昨年(2020年)にはNHKが、“もしも明智光秀がスマホを持っていたら?”という設定のSF時代劇『光秀のスマホ』を放送し、「ギャラクシー賞」にも輝きました。同ドラマにもスエヒロさんが関わっています。
本書も、そうした「日本史パロディ」ブームの流れを汲む一冊。“歴史上の大事件の現場に現代企業のような広報がいたら、どんなプレスリリースを出したか?”を空想していく本なのです。
ただし、単なるお遊びではなく、広報入門としても十分に活用可能な深い内容になっています。
それもそのはず、著者の鈴木正義氏はスティーブ・ジョブズ時代のアップルで広報を務め、いまはNECパーソナルコンピュータとレノボ・ジャパンで広報部門を率いる、第一線の現役広報マンなのです。
広報の何たるかを知り尽くした著者が、日本史を広報的視点で捉え直した内容であり、歴史エンタメであると同時に企業向けの実用書にもなる一冊。
「歴史コメンテーター」として活躍する金谷俊一郎氏(東進ハイスクール日本史講師)が監修を務めており、内容もしっかりしています。
“プレスリリースのお手本集”にもなる
そもそも、現役広報マンの著者が、なぜ日本史パロディの本を出したのでしょう? そのいきさつは「まえがき」で明かされています。
著者はWEBメディア「日経クロストレンド」で広報の仕事を解説するコラムを連載していますが、「実際の広報の事例を示しながら書くこと」は「意外と難しい」と気付きました。当事者企業にとってネガティブな事例である場合もあり、取引先などに不愉快な思いをさせかねないからです。
そこで一計を案じ、本書のタイトルになった「もし幕末に広報がいたら 大政奉還のプレスリリース書いてみた」というコラムを連載の一回として書いたところ、大好評。それが本書誕生のきっかけになったのでした。
つまり、「はじめに日本史パロディありき」ではなく、波風立てずに広報の仕事を解説する(=当事者は墓の中なので、抗議などこない)手段として、日本史をネタにしたわけです。その意味で、本書が「広報入門としても役に立つ」のは当然でしょう。元々それが目的なのですから。
本書のタイトルはアイキャッチであり、幕末に限った内容ではありません。古代から明治時代までを射程に入れ、42の歴史的大事件が取り上げられています。
それらを題材として、「リスクマネジメント」「制度改革」「マーケティング」「広報テクニック」「リーダーシップ」という5つのテーマに沿って、“広報のプロなら、この大事件をどう広報するか?”が解説されていくのです。
42の大事件に合わせ、1ページないし2ページの「プレスリリース」が作られています。そして、なぜそのような内容のプレスリリースにしたのかを、著者が解説していくという構成です。
現役広報マンが著者だけに、42のプレスリリースはどれも、大変もっともらしく作られています。
例を挙げてみましょう。
松下村塾についてのプレスリリースは、進学塾の新規塾生募集のようなテイスト。見出しには、《志士輩出数全国1位の「吉田メソッド」で松陰先生が尊皇攘夷を直接指導!》といった言葉が躍ります。
また、《広報発の話題づくり》の例として、《今年の甲冑ベストドレッサー賞に真田幸村さん》などというプレスリリースが作られたりします。
さらに、紀貫之を取り上げた項では、貫之が『土佐日記』を女性になりすまして書いたことが“『古今和歌集』の選者ともあろう者が、読者をだますとはケシカラン!”とネットで炎上し(笑)、古今和歌集編集部が対応のためにプレスリリースを発表する、という設定になっています。
そのように遊び心あふれる内容ですが、各プレスリリースについての著者の解説は、どれも見事なものです。
たとえば、「本能寺の変」を取り上げた項では、焼失してしまった本能寺側が事後の危機対応としてプレスリリースを発表する、という設定で、「危機対応の5大原則」が解説されます。
「5大原則」とは、①謝罪、②事実関係、③原因・経緯、④影響、⑤対応・再発防止です。それらをプレスリリースに盛り込むことが大切だと、著者は言うのです。
《この要素がそろっていないと、必要以上に広報対応が長引いてしまい、企業側(今回のケースでは本能寺)の対応が批判を受けることにもなりかねません》(32ページ)
これはあらゆる中小企業においても、危機対応のいろはとして肝に銘じておくべき言葉でしょう。
色々なプレスリリースが網羅されているので、中小企業は本書を、「こういう場合にはこんなプレスリリースを出せばよい」という“お手本集”として活用することもできます。
広報を学ぶ、敷居の低い入り口
中小企業経営者には、歴史好きの人が多いですね。その大きな理由は、戦国武将などの人生が、経営者が持つべきリーダーシップの手本となるからでしょう。
しかし、本書を読むと、歴史に学べるのはリーダーシップだけではないことがよくわかります。効果的な情報発信、危機対応、レピュテーション・マネジメント(企業や経営者の評判管理)なども、歴史から学べるのです。
立派な広報部を持つ大企業とは違い、中小企業には独立した広報セクションがないケースも多く、どう広報したらよいかがわからないという経営者も多いでしょう。そんなとき、本書は広報を学ぶための敷居の低い入り口になってくれるでしょう。
社長にとって学びになるのはもちろん、広報を担当させる新人の教育にも、十分使える一冊です。
鈴木正義著、金谷俊一郎監修/日経BP/2021年12月刊
文/前原政之
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






