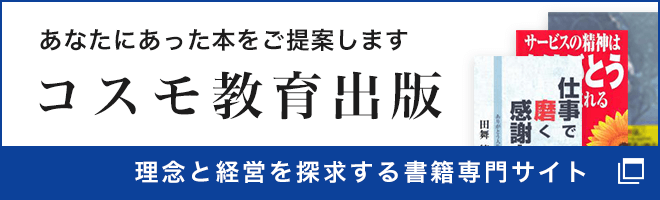『理念と経営』WEB記事
巻頭対談
2021年8月号
いまこそ経営に 「共感する力」を取り戻せ!

一橋大学名誉教授 野中郁次郎 氏 × ジャーナリスト 勝見 明 氏
かつて世界から称賛された「日本的経営」。次々にイノベーションを生み出した背景には「共感する力」があったと指摘する両氏は、それを「共感経営」と位置づけた。その輝きが失われつつあるいま、求められる日本企業の在り方とは何か。
日本企業から共感力を奪った
「三つの過剰」の問題
―野中先生の知識創造理論をベースに、「共感」の大切さを訴えられたのが、お二人の共著『共感経営』でした。なぜ経営に「共感する力」が不可欠なのかを、改めて語っていただければと思います。
勝見 昔は経営資源といえば、「ヒト・モノ・カネ」の3つでした。しかしいまや「知識経営」の時代であり、知識こそが競争力や価値、イノベーションの源泉になります。野中先生は、その知識が創造されるプロセスを「SECI(セキ)モデル」で理論化されました。
野中 「SECIモデル」は、「形式知」(言葉や文章で明示できる客観的・理性的・社会的な知)と「暗黙知」(言葉や文章で表現するのが難しい、主観的・個人的・感性的・暗黙的な知)の相互作用からイノベーションが生まれるとするモデルですが、その相互作用を生むためには共感が不可欠なのです。
勝見 「暗黙知」を共有するには共感がないといけないですからね。そうした共感が新しい価値やイノベーションを生む原動力になった経営を、私たちは「共感経営」と定義しました。「共感経営」がなぜいま求められているかといえば、日本企業から「共感」が失われつつあるからです。そのことが、かつて世界に賞賛された「日本的経営」が輝きを失った背景にあります。
野中 ええ。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われた1980年代まで、成功した日本企業の多くは「共感経営」でした。
勝見 80年代の日本企業は、高品質・高機能の新製品を、短いリードタイムでどんどん世に出していました。「なぜそんなことができるのか?」と不思議に思ったハーバード・ビジネス・スクールが野中先生に日本企業の分析を依頼し、野中先生は『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌に英語で論文を寄稿されました(1986年/竹内弘高氏と共同執筆)。
野中 その論文では「共感経営」という言葉は使っていなくて、ラグビーになぞらえた「スクラム」という言葉で表現していました。当時の画期的商品の多くは、私が「スクラム」と名付けた新製品開発手法で作られていたのです。
勝見 前工程と後工程のチームが前後を飛び越え、さらに左右の横の連係をしながら、一丸となってゴールに突き進み、製品開発する手法が「スクラム」です。個々のチームは自律しているけれど、全員が共振・共感・共鳴しながらスピーディーに開発を進めていくやり方ですね。
野中 ええ。それは最初に理論ありきではなくて、顧客の無理難題を解決するために一生懸命やっていくうちに、自然に生まれてきた手法だったのです。
勝見 そして、野中先生の論文を参考に、ソフトウェア開発手法としての「アジャイル・スクラム」を九〇年代に生み出したのが、米国のジェフ・サザーランドでした。「アジャイル・スクラム」方式では、分析・設計・実装・テストという各工程の技術者が、部門横断的にチームを作ります。そして、価値の高い機能を順位づけして、「まずこの機能からやろう」と、スクラムを組むように順に開発していくのです。ソフトウェア開発という最先端分野で、じつは最も共感が重視されているのは興味深いことです。
野中 ジェフとは、2011(平成23)年に彼が来日したときに初めて会いました。そのときに彼は「あなたの論文が私の『アジャイル・スクラム』を生んだのです」と言って涙ぐんでいました。
勝見 それくらい、80年代までの日本企業は、画期的イノベーションを次々に生み出す「共感経営」をやっていたわけです。日本型経営こそが米国企業のお手本になっていた。ところが、90年代以降の日本企業は、逆に米国企業の経営手法に寄りすぎてしまいました。
野中 そこから生じたのが、「三つの過剰」と呼ばれる問題でした。「分析過剰」(オーバー・アナリシス)、「計画過剰」(オーバー・プランニング)、「法例遵守過剰」(オーバー・コンプライアンス)です。一言で言えば、アメリカ流の分析的経営に対する過剰適応であり、それが日本企業から活力を奪い去りました。日本企業が豊かに持っていた共感力が失われたのです。「失われた30年」とも言われる、90年代後半以来の日本企業の競争力低下の、背景の一つがそれです。
勝見 なぜそうなったかといえば、80年代までの日本企業の「共感経営」が理論化されていなかったからでしょうね。野中先生が言われたとおり、懸命にやっていたらいつの間にかそうなったという自然発生的な面がありましたから……。「共感経営」の素晴らしさが理論化できないままバブルが崩壊して、やみくもに理論を求めた結果、アメリカ流の分析的経営に過剰適応してしまったのでしょう。
相手の視点になりきる共感が
イノベーションを生む
野中 そうした状況の中でも、素晴らしいイノベーションを生み出している日本企業はいまも数多くあります。私と勝見さんはもう20年近く、日本企業のイノベーション事例を一緒に取材する連載を続けてきました。『共感経営』も、その連載から生まれた本の一つです。そういう企業には、共感がイノベーションの原動力になっているという共通項があります。
勝見 そうですね。我々の取材先から一例を挙あ げれば、京都の宇治市に「HILLTOP(ヒルトップ)」というアルミ試作加工メーカーがあります。元々は、自動車会社の孫請けとして部品を作っていた普通の町工場でしたが、事業改革を行い、多品種単品製作に舵かじを切りました。取引先からの試作品受注を中心にしたのです。新卒採用を本格的に開始したこの10年間で従業員数は二・五倍、売上高は五倍、取引先は九倍に拡大しました。利益率も20~25%と非常に高い(業界水準は3~8%)。そういう大成長を遂げた中小企業です。
野中 HILLTOPは、「二四時間無人加工の夢工場」というキャッチフレーズを掲げています。製品をつくる加工機が自動化されていて、社員は昼間にプログラムを組んで、加工機が夜間も無人で稼働するのです。「ヒルトップ・システム」と命名された、大変なイノベーションです。
勝見 はい。そのイノベーションの原動力となったのは、経営者の社員に対する共感でした。孫請けだったころ、社員は毎日油まみれで働き、同じ単純作業の繰り返しだった。「面白みのない仕事を社員に押しつけたくない」「知的でやりがいのある仕事をしよう」―そんな思いから「ヒルトップ・システム」をつくり上げていったのです。
野中 イノベーションは共感から始まり、「本質直観」につながり、それを踏み台にして「跳ぶ仮説」が生まれてきます。「ヒルトップ・システム」が生まれるまでのプロセスもしかりです。経営者が社員たちの気持ちになり、「毎日油まみれで単純作業の繰り返しではつらいだろう。何とかそこを変えてあげたい」と強く思う。その共感が出発点です。変えるためにはどうすればいいか……相手の視点に立ち、その文脈のなかに入り込んで、あれこれ思索するうちに、「もっと人間らしい知的な仕事をしよう。楽しくなければ仕事ではない」という考えに至ったのでしょう。それが「仕事とは楽しいものであり、社員たちは知識労働者である」という「本質直観」です。そこから下請け脱却までは、多くの経営者が考えるでしょう。しかし、「加工工程を全自動化して、社員はプログラムを組むだけにしよう」とまで考えるには、大きな発想の飛躍があります。それが私の言う「跳ぶ仮説」です。その仮説を実現するために、試行錯誤の末に「ヒルトップ・システム」が生み出されたわけです。
勝見 「共感からイノベーションが生まれる」ことを示す見事な実例だと思います。
野中 そこで指摘しておきたいのは、「共感(Empathy)」と「同感(Sympathy)」は似て非なるものだということです。共感は相手の視点になりきることですが、同感は第三者の視点から判断・分析した上で相手に同意することです。言い換えれば、同感は意識的感情で、共感は無意識的感情なのです。人間の脳内には無意識のうちに相手に共感する「ミラーニューロン」がありますが、共感はまさにミラーニューロンが発火する無意識の感情と言えます。そして、「共感経営」というときの共感は、相手を外側から分析して生まれる同感も含みますが、まず起点になるのは相手になりきったときにこそ生まれる共感なのです。現象学では「相互主観性」と呼びます。
勝見 本田宗一郎(本田技研工業創業者)に、「人を動かすことのできる人は、他人の気持ちになることができる人である」という名言があります。まさに「共感」ですね。経営者にはそうした共感力が不可欠なのでしょう。
野中 それは、経営者の社員に対する共感、顧客に対する共感、取引先に対する共感、果てはモノや機械に対する共感など、さまざまな形を取ります。何であれ、相手の視点になりきるような共感から出発しないと、イノベーションには結びつかないのです。
勝見 野中先生は、「イノベーションは、徹底的な対話による知的コンバットがなければ生まれない」とよく言われます。「コンバット(Combat)」は「戦い・一騎打ち」という意味ですね。「共感」というと、「あなたの気持ち、わかるよ」と優しく寄り添うようなイメージがありますが、我々の言う「共感経営」はけっしてそのような静的・受動的なものではなく、共感した上で本音をぶつけ合う激しく能動的な営みなのですね。
野中 ええ。そこが誤解を招きやすい点です。相手の気持ちになる共感が出発点であっても、それが単に上司や客の顔色をうかがう「忖度」になってしまったら、イノベーションは生まれません。
構成 前原政之
撮影 中村ノブオ
本記事は、月刊『理念と経営』2021年8月号「巻頭対談」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
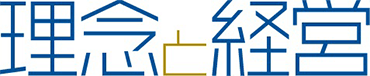


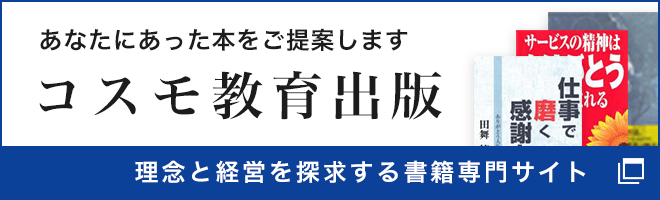





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)