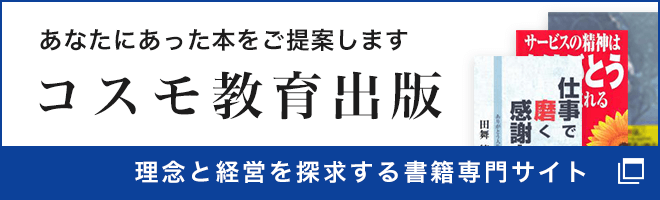『理念と経営』WEB記事
巻頭対談
2021年3月号
「企業は社会のために何ができるのか?」 あなたはこの問いに答えられますか

歴史家・作家 加来耕三 氏 × エッセイスト 鮫島純子 氏
渋沢栄一と言えば「日本資本主義の父」と呼ばれることが多いが、ご令孫・鮫島純子氏は「それは結果のこと」と断言する。加来耕三氏との語らいで、史実に基づく渋沢像を通して見えてきたのは、渋沢が生涯貫いた「皆が幸せと感じられる社会を創りたい想い」である。
どこへ行っても聞かしていただいた
亡き祖父への感謝の言葉
加来 今年はNHKの大河ドラマ『青天を衝け』の主人公になるなど、渋沢栄一が再び脚光を浴びていますね。
鮫島 はい。孫としてはありがたいことです。私も昨年来、祖父の関係で取材を受ける機会が増えました。孫の生き残りはほかに2人くらいいますけど、彼らはまだ赤ちゃんでしたから、いま生きている孫で、祖父と直接会話などしたのは私だけだと思います。ですので、語り部としての使命感を感じて取材をお受けしております。
加来 私の作家としてのデビュー作は『真説 上野彰義隊』ですが、これはタイトルの通り、「上野戦争」を戦った彰義隊の歩みをたどった作品です。慶応四(1868)年の5月15日(旧暦)に、たった1日で終わってしまった戦争ですが、その彰義隊を作った人物の1人が、渋沢栄一のいとこに当たる渋沢成一郎です。つまり、私のデビュー作の主人公の1人なのです。
鮫島 それは、それは……。渋沢家とご縁がおありなのですね。
加来 当時、その作品の取材で彰義隊に関係のある人々の集いに参加しましたところ、たまたま渋沢華子さん(渋沢栄一の孫。小説家としても活躍)も来られていて、お話をさせてもらいました。まだ私が20代のころです。
鮫島 華子は私のいとこで、かなり前に亡くなりましたけど……。そうですか、そんなに昔からご縁が。
加来 はい。ですから、今日はお会いできるのをとても楽しみにしておりました。
鮫島 加来先生は合気道もなさるんですよね? 合気道の開祖として知られる植芝盛平先生は、わが家とは近しいんです。海軍の竹下勇大将は主人の伯父ですから。
加来 そうでしたか。竹下大将は開祖・植芝盛平翁を見いだして、合気道普及に大きく貢献した人ですね。
鮫島 植芝吉祥丸先生(盛平の三男で後継者。1999年逝去)とも、何度かお目にかかったことがあります。
加来 吉祥丸道主(宗家)は、私の合気道の師でした。いやあ、ほんとうにいろいろご縁がありますね。
さて、今日の対談は、「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一の生涯から、本誌の読者である中小企業経営者や社員の皆さんが学ぶべきことを語るというテーマです。
鮫島 私は『理念と経営』とご縁ができてから、毎月読ませていただいています。さまざまな会社の記事を読むたびに、「ああ、祖父が理想とした経営の精神を、そのまま受け継いで広めてくださっている」と思って、胸が熱くなります。
ただ、私は祖父が亡くなったときにはまだ9歳でした。祖父が日本の近代化に貢献したとか、「日本資本主義の父」であるとか、そんな考えで見ていたわけではありません。私にとっては一人の優しいおじいちゃまだったのです。伺ってご挨拶すると、決まってニコッと笑って、榮太樓の「梅ぼ志飴」を食籠の中から1粒手に取って、私の口の中に入れてくれました。
加来 優しいお顔が目に浮かぶようです。
鮫島 「どうやらうちのおじいちゃまは、普通の人とは違うらしい」とやっと気づき始めたのは、亡くなる直前です。祖父の病状が毎日、新聞記事になったりしたものですから。
また、私が中学生くらいのときに、ある場所で三浦環さん(日本で初めて国際的な名声を得たオペラ歌手)とご一緒した際、「私はおじいさまのおかげでドイツに留学できました。私が今日あるのは渋沢さんのおかげです。足を向けて寝られません」と言われたことが印象的でした。
大人になってからも、どこへ行っても「あなたのおじいさまにはこんなことでお世話になりました」とよく聞かされました。私は祖父の優しさを、接した皆さんの言葉を通じて教えられたのです。
わずか1年半の渡欧で
資本主義の本質をつかむ
加来 渋沢栄一は、幕末に一橋慶喜(のちの第15代将軍徳川慶喜)の家臣となり、慶喜の異母弟・徳川昭武に随行してフランスをはじめとした欧州に約1年半滞在しました。
鮫島 はい。27歳から28歳にかけてのことですね。幕臣としてはまだ新米の若造で、しかも農家の倅で元は武士ではなかった祖父を抜擢してくださったのは、慶喜公の慧眼だったと思います。
加来 私は、この渡欧の中にこそ、渋沢栄一の天才性を感じます。というのも、それまで外国文化に直接、触れる機会がなかったにもかかわらず、栄一はあまりに多くのことを、このとき学び取ってきたからです。
彼は、たった一度の短期間の渡欧で、資本主義の本質を見抜きました。そして、その仕組みを日本に持ち込むためには何が必要か、完全に理解していたのです。そこがすごい。いったいどうしてそんなことが可能だったのか、私にはそれが謎でした。
渡欧の主な目的は、パリで開かれた万国博覧会(1867年)の視察と昭武の留学でした。一方の万博は、フランスがこれを機に一流国の仲間入りをしたと言ってよい、歴史的なものでした。日本からも多くの人が視察に行っています。しかし、その中で資本主義のエッセンスを正しく学び取れたのは、栄一ただ一人だったと思います。他の人たちは、「すごいなあ」と驚くだけで終わっていたのです。
鮫島 一橋家からの他の随員の方々は、「昭武様に何かあったら大変だ」と、そちらにばかり目が行っていたのでしょうね。それに対して、祖父は経理などの実務を担当したのがよかったのかもしれません。
加来 会計係と書記官を兼ねたような役回りだったのですね。栄一は、一行が当初泊まったグランド・ホテルでは滞在費用が嵩むということで、安い住宅を探して、そこに移る手配をしました。このあたりも彼らしいところです。というのも、普通、武士はそんな倹約など考えないものだからです。倹約どころか、お金に関わること自体、武士らしくないと考えられていたのですから。
鮫島 そうなのですか。
加来 ええ。例えば武家の子どもが夏祭りに遊びに行くと、何か買うときには巾着ごと商人に手渡すのです。商人は「いくらいただきました」と巾着を返す。それほど〝金には触ることすら武士らしくない〟という考え方が一般的でした。
それに対して、栄一は豪農の家に生まれてお金の扱いも学び、一橋家に仕えてからは家政改革にも携わり、財政を立て直しました。だからこそ、生まれながらの武士にはできないことができたのです。そのころから、経営の才が発揮されていたわけです。
鮫島 渡欧に際しても、他の随員が武士の眼で視察していたのに対して、祖父はすでに経営者目線で見ていたのかもしれませんね。
加来 それが大きいと思います。
また、もう1つ驚かされるのは、西欧文明に対する順応性の高さです。例えば、行きの船で毎日バターとパン、ハムやコーヒーの食事を出されても、栄一は初めて口にしたのに「バターはとてもおいしい。コーヒーは胸が爽やかになる」と抵抗なく味わっています。そのような順応性も、ただ者ではありません。ずっと鎖国していた日本にあって、彼は何にでも好奇心を持つ、いわば〝天性の世界市民〟だったのです。だからこそ、1年半の渡欧で多くを学び、帰国後に近代国家建設に手腕を発揮できたのだと思います。
鮫島 祖父は、中国がアヘンでやられて植民地化されたことや、東南アジアの国々も欧米列強に植民地化された例を見て、「日本が同じ轍を踏んだら大変だ」と強く憂うれえていました。その思いこそが学びの原動力だったのでしょうね。
学ぶべきは、「企業利益を
社会に還元する」姿勢
加来 渋沢栄一といえばすぐに「日本資本主義の父」といわれ、そこばかりが強調されますが、一方で彼は日本における「社会福祉の父」でもありました。
約500もの企業の設立に関わった栄一ですが、一方では約600もの教育機関・社会公共事業の支援に尽力したのです。そこを見過ごして、「資本主義の父」としての側面ばかりを見てしまうと、渋沢栄一の本質を見誤ると思います。
鮫島 まったく同感です。私も講演に呼ばれますと、プロフィール紹介に「日本資本主義の父・渋沢栄一の孫」ということが決まって書いてあるんです。でも、「資本主義の父」だけで終わらないでほしい、といつも思います。
加来 渋沢栄一の代名詞とも言える「論語と算盤」自体が、「資本主義の父」と「社会福祉の父」という両側面を示しています。論語が象徴するのは公共性の追求であり、算盤が象徴するのは利益の追求です。栄一にとって、企業を起こして経済を活性化させ、利益を上げることと、その利益を社会に還元していくことはセットであり、車の両輪なんですね。2つがごく自然な形で共存している。それこそが、栄一の提唱した「道徳経済合一説」の意味するところなのです。
企業が利益を追求するのはいいけれど、その先に公共性を重んじる視座がなければ、本当の意味での経営とは言えない……というのが栄一の考え方でした。
撮影 中村ノブオ
本記事は、月刊『理念と経営』2021年3月号「巻頭対談」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
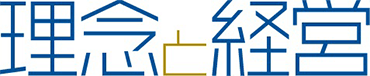


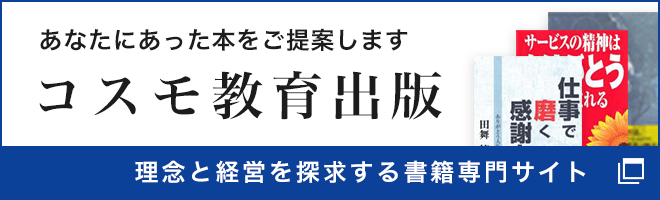





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)