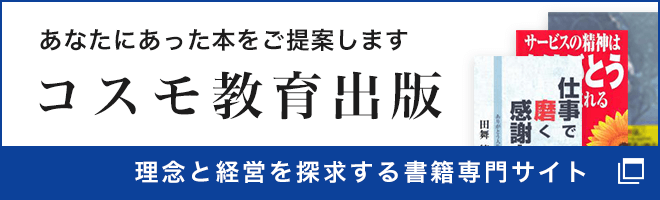『理念と経営』WEB記事
巻頭対談
2020年5月号
時勢が悪いときこそトップの「志」が試される
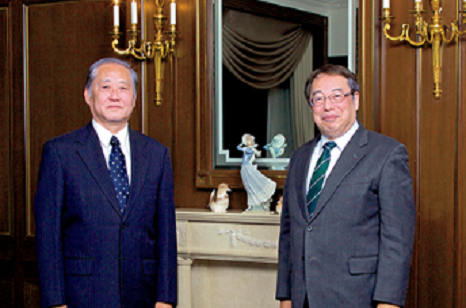
皇學館大学教職アドバイザー 川口雅昭 × 歴史家・作家 加来耕三
幕末の危機感のなかで突き動かされるように学び、行動した志士たち。同じく大きな時代の転換期のなかで、今なぜ多くの日本人は危機意識をもち得ないのか。歴史家で作家の加来耕三氏と吉田松陰の研究者である川口雅昭氏が語る、日本人の志の行方――。
日本人は相変わらず「稚心(ちしん)」を
去ることができていない
加来―聞くところによりますと、次の改訂で高校の日本史の教科書から、吉田松陰の名前が消えるそうですね。
川口―そうなんです。山口県の松陰先生ファンは大騒ぎですよ。
加来―その理由は、日本史に影響を与えなかったと言うわけのようで、上杉謙信、武田信玄も消えるらしいですね。こうなるのは、根の部分を見ずに、現象しか見ていないからでしょう。見ているのは「明治維新になった」という結論だけで、そこに至るプロセスには目を向けていません。先生が研究されている松陰も、同じく維新の先覚者で、私が魅力を感じている福井藩の橋本左内も、安政の大獄で罪に問われ、若くして刑死するわけです。結果に参画していない、と言われればそうかもしれませんが、本来はそうした志半ばで倒れた者の精神にこそ、学ばなければいけないはずです。
川口―まったく同感です。私は吉田松陰の研究を続けていますが、松陰は「経」と「史」とその両方を学ばなければならない、と言っています。「経」というのは人間永遠の道、すなわち「こうあらねばならない」という人の在り方です。「史」は観念ではなく史実と言いますか、「こういう生き方をしてきた」などという具体的な事実です。松陰は、この2つを学べと語っているのです。
加来―まさに、正しい歴史の学び方ですね。今の日本人は皆、歴史の「答え」しか知りません。「1868年は慶応4年で明治元年である」とだけ、知っている。どれほどの志ある人々が、どんな思いで維新を成し遂げようとしたか、を知ろうとはしません。
これはスマホでも同じです。調べたいことがあったとき、スマホは検索をかければすぐに答えを教えてくれます。人は答え、つまり結論を聞くとわかった気になるのです。
川口―その通りですね。物事を深く考えなくなります。
加来―そうなんです。本当に考えない。橋本左内は15歳のときに、 自分を律するために、人としてのあるべき姿を示した『啓発録』を著しています。その第一に「稚心(ちしん)を去れ」と言っているのです。「稚心(おさなごころ)とは幼い心、子どもじみた心のことである」と。日本人は相変わらず、「稚心を去る」ことができていない、と思います。幼いままです。結局、今日の問題は、そこに根があるように思われます。
川口―先生がおっしゃったように、誰もが幼いままであるということは、私も実感しています。常々感じるのは、みんな「ごっこ」をやって生きているということです。父親は父親ごっこ、経営者は経営者ごっこ、教師は教師ごっこというように、みんな本物になっていないように思います。本物になっていないから、感動を与えられない。学生を見ていても同じで、本気で生きているな、と感じられる若者が少なくなったという気がしています。
加来―日本人は平成の30年を経て、大きく変わりました。以前の日本人とは違う、と思います。何が違うかというと、志がなくなりました。志を抱く人間はいつの時代もいるのですが、今はそれが小さい。加えて、危機意識がまったくありません。未来に目を向けず、考えているのは今日明日のことだけです。
私が興味深いと思うのは、関東大震災が起こる直前の雑誌を見ると、今と一緒なのです。本を読まない、コミュニケーションが取れないなど、日本人が躍動的でなくなってきた、との記事が載っているのです。世界恐慌の前でもありましたが、何の危機意識もありません。
川口―その危機意識のなさは、確かに今と通じるものがありますね。
加来―明治維新のそもそものスタートは、欧米列強の植民地化への危機感でした。国家の独立の尊厳を、どう守るかという問題意識と言ってもいいでしょう。きっかけは、清国のアヘン戦争の敗戦です。アヘン戦争を戦った清国の林則徐が、友人の魏源に敗戦後のレポートを書いてくれるように託すのですが、それを読んだ清国の人間はいませんでした。隣国の李朝朝鮮も無視です。懸命に読んだのは、日本の島津斉彬や鍋島閑叟(直正)などの大名、幕府の少壮官僚たちでした。真剣に学び、強い危機感をもったわけです。
川口―松陰という青年も、そうした危機意識をもった一人です。松陰が考えたのは、王政復古と、国家の独立をどう守るか、の2つでした。彼は死ぬまで「侵略が進んでいる」という言い方をしているんです。
加来―植民地化を防ごうと考えると、どうしてもそうした結論にならざるを得ません。国民というものをつくって、その一人ひとりが国を守るという気概をもたない限り駄目だ、という結論です。それをどう実現するかということで、吉田松陰も、橋本左内も、試行錯誤しながら必死に動き回ったわけです。
川口―松陰は徹底的に文科系の人間ですが、左内は理科系の人間です。確か左内は医者でしたね。
加来―はい。今でこそ社会的なステータスは高いですが、当時の医者は武士ではなく、お坊さんと同じ身分の分類に入ります。左内は、自分は医者にしかなれないと思っていました。しかし彼は決意します、医者が治す病気もいろいろある。自分は日本国を治そう、と。
川口―「小医は病を医(いや)し、中医は人を医し、大医は国を医す」という有名な言葉ですね。
加来―はい。そして左内は、突き動かされるように学ぶわけです。大坂の緒方洪庵の適塾(正しくは適々斎塾)にも行き、ドイツ語から英語、フランス語まで学んでいます。最終的には藩主の松平春嶽(諱は慶永)によって、藩士に取り立てられ、日本の国全体を治すという自身の志に挑みました。松陰も同じだと思いますが、彼も誰に言われたからということではなく、自ら率先して学んでいますね。
川口―はい。松陰は幼くして叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の元に養子に行きますが、父の杉百合之助の、家庭における教育がとても大きかったと思います。松陰は、その教育すべてを真剣に受け止めるのです。誰に頼まれたわけでもないのに、「我が国をどうすればいいのか」と考える。性格的には根っからの真面目人間です。しかし、その半面、行動的で、酒もいけるし、いざというときは段平(刀)を下げて飛んで行くようなタイプです。
加来―とても、熱い人だったのですね。
撮影 中村ノブオ
本記事は、月刊『理念と経営』2020年5月号「巻頭対談」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
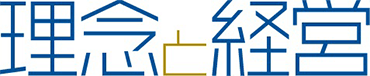


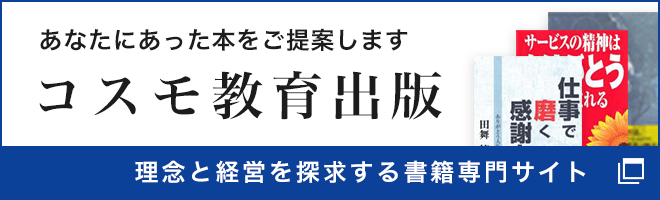





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)