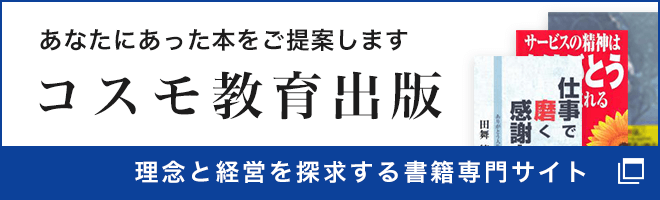『理念と経営』WEB記事
人とこの世界
2018年4月号
絶望の淵にも、かならず希望の灯はある

NPO法人「蜘蛛の糸」理事長 佐藤久男
死に向かおうとする人々の“最後のとりで”となって話を聞き続け、「秋田の自殺を半減させた男」と呼ばれる人がいる。自身も倒産で死を間近に感じた経験を持つからこそ信じる、「未来に希望を持つこと」の力――。
15歳から山登りを始めた。日本の山の3分の1は登っただろうか。山にはいつも1人で登る。思い通りにならない局面に出会うたび、多くのことを学び、人生の難局を乗り越える糧にした。
山頂に着いて下り始めると、よく二股の道に出合う。上りはかならず山頂に通じているが、下りは迷う。そんなとき、分岐点にどっかとあぐらをかき、1万分の1の地図を広げる。選択を違えば、2000キロも遠回りするかもしれない。1時間、2時間と動かず自然の声を聞き続ける。
すると、体の内側から何かが湧き上がり、「あっ」と思う瞬間が来る。それは決してひらめきではなく、何の確証もない。しかし、一歩踏み出せば、あとは絶対に振り返らない。とどまっても休んでもいいから諦めずに、自分の決めた道をただひたすら前に進む。
お父さん、自殺したら
承知しないからね
1943(昭和18)年、秋田県北部に生まれた佐藤久男さんは「秋田の自殺を半減させた男」といわれる。身長161センチの白髪頭。ずんぐりした体型から発せられる秋田弁が優しく、親しみを感じる。2002(平成14)年、NPO法人「蜘蛛の糸」を立ち上げ、主に経営者の自殺予防に取り組んできた。
誠実でひたむきな人柄だが、堅物ではない。さまざまな事情を抱える相手と真っすぐ向き合う強さがありながら、ユーモアを忘れず、無邪気に笑う。力のある瞳には、苦境のなかに幸せを見いだしてきた人生が垣間見えた。
倒産した経営者の相談を多く受ける佐藤さんも、以前は経営者だった。地元の高校を卒業後、秋田県の職員を経て不動産鑑定事務所の専務に転身。34歳で独立すると、住宅・不動産会社の経営者となった。社員は一緒に鑑定事務所を辞めた3人だけで、事務所も7坪しかなかった。
溢れるアイデアを具現化するため、寝ても覚めても会社の経営に没頭した。間もなく中古住宅市場で商機をつかむと、アパートの仲介や新築住宅も手掛けて年商10億円を超える企業へと成長させた。
やがて、バブル経済が崩壊。地価や住宅価格は下落したが、焦りはなかった。2度にわたる石油危機を乗り越えた経験と十分な内部留保がある。そのうち、景気が上向くだろうと考えた。しかし、景気は後退を続け、大手住宅メーカーとの競争も激化。売上高は坂道を転げ落ちていった。
会社は自己実現の最大の場であり、人生そのものだった。日に日に倒産の恐怖がのしかかり、抗うつ剤を飲みながら働いた。万策尽きた2000(同12)年9月半ば、子どもたちに倒産することを伝えた。重苦しい沈黙が漂うなか、長女の伸子さんが「お父さん、自殺したら承知しないからね。家族はお墓参りに行かないからね」と強い口調で言った。絶対に死んでほしくないという思いが伝わった。
小学校2年生のとき、佐藤さんは父親を亡くしている。経営者だった父親は、ある日、川の浅瀬で倒れているところを発見された。事業に失敗して自殺したのだと思ってきたが、はっきりとはわからない。享年48歳だった。
「僕は死ぬことが許されない人間です。父親のいない子どもの悲しみを身に染みて知っている。祖父に続いて私まで自殺すれば、子どもが挫折したとき『私も』となるかもしれない。自殺をDNAにしてはならないと思いました」
一生懸命頑張って、その結果が
“罪人”なのか……
2000年10月2日、会社は倒産。負債総額8億5000万円、債権者は86人に上った。すぐにテレビや新聞で報じられ、会社には債権者が押し寄せた。電気や水道が止まり、トイレの水も流せない。がらんとした事務所にストーブを持ち込み、登山用のウエアを着て、膨大な残務処理に臨んだ。
「自分宛ての封筒も弁護士の立ち会いがなくては開けられない。裁判所の書類のなかで、債権者は原告で自分は被告です。一生懸命頑張って、その結果が罪人かと情けなくなりました」
ようやく残務処理にめどが付いた翌年1月半ば、自宅を出て賃貸住宅に移ると、今度は夜な夜なフラッシュバックの恐怖に襲われた。決まって午前2時、突然ハッと目が覚めると、手足が震え、心臓がドクドクと鳴る。社長室に座る自分や社員の前であいさつする自分の姿が見える。一番つらかったのは、お盆で玄関に子どもたちが帰ってくる映像だった。
秋田の街は狭い。債権者や銀行員に会ったらどうしようとおびえ、家に閉じこもりがちになった。周囲にいるすべての人が倒産した自分に冷たい視線を送っているように感じて怖かった。
それでも、意識して毎日の散歩だけは続けていた。散歩道には葉が落ちた桜並木が続いている。人目を避け、夕方から散歩に出掛けたある日、何気なく見上げると、桜の枝に白い布切れがぶら下がり、てるてる坊主のように風に吹かれて揺れていた。よく見ると、顔も足もある。しばらくしてハッとした。「あれは俺が首を吊っている姿だ」。揺れていたのは、桜の木で自殺している自分の幻影だった。慌てて引き返しながら、「倒産した社長は死にたくて死ぬよりも、こうした衝動や幻覚に負けて死ぬのだな」と思った。
あるときは生きる力を感じ、あるときは死に引っ張られながら、時間がとれると自然のなかに出掛けた。そして、小さな幸せを探し、心のなかに貯めていった。雪が辺りを白く染めていく光景や、足元に咲いたタンポポの可憐さ。変わらない自然の営みが心を満たし、幸せを感じさせた。
取材・文 菅井理恵
撮影 宍戸清孝
本記事は、月刊『理念と経営』2018年4月号「人とこの世界」から抜粋したものです。
理念と経営にご興味がある方へ
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
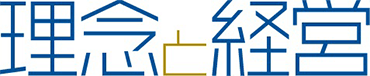


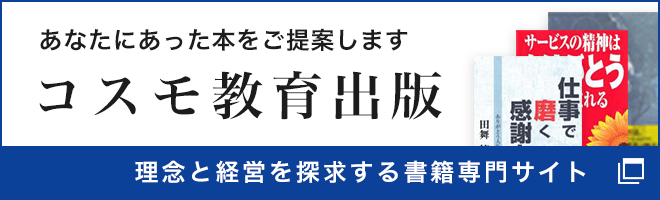





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)