企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
現場力
2025年11月号
才能は自分から見つけていくもの
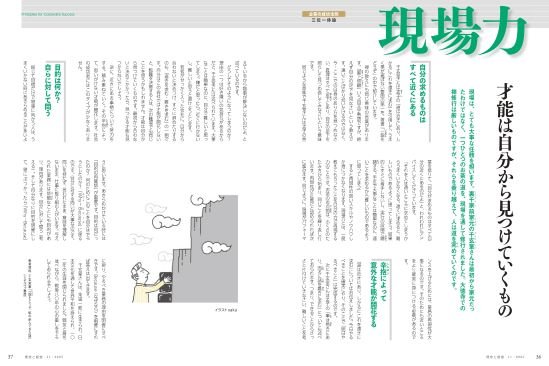
現場は、とても大事な任務を担います。裏千家前家元の千玄室さんは最初から家元だったわけではなく、一つひとつのお茶の道を、現場を通して修行されました。大徳寺での禅修行は厳しいものですが、それらを乗り越えて、人は道を究めていくのです。
自分の求めるものはすべて近くにある
千玄室さんは孟子の「道は近きにあり、しかるにこれを遠きに求む」を引用して、うまく事が運ばない要因の第一を、著書『一盌をどうぞ』の中で紹介しています。
禅の教えにも同じ意味の言葉があります。「脚下照顧」いう四文字熟語ですが、絶えず自分の足下を見なさいという教えです。遠いことばかり追いかけるのではなく、
今・ここでの自身のあり方を見つめなさい、真理はすべて足下にあり、自分の足下を照らして見つめ直してみなさいという意味です。
同じような意味で千玄室さんは孟子の言葉を借りて、「自分が求めるものはすべて自分の近くにあるのだよ」と、われわれにアドバイスしてくださっています。
「それを人は遠いところに求めてしまうからうまくいかなくなる。遠くに求めると、難しいものであるように思ってしまう。結果的にすぐに着手しないし、実行の段階で躊躇する。手近で大事なことは簡単なのに、遠いことを求めるから難しいものであるように思ってしまう」
すると再現性の弱いスキルやノウハウしか身につかなくなります。現場力とは、一度教えてもらったことを自分の力で再現する力のことです。お茶のお点前は、ふくさのたたみ方から始まり、同じことを繰り返し行います。
再現性が正確だと認められれば次に進みます。同じように、現場がパフォーマンスを上げるためには、業務の再現性が大事になるのです。そのためにも近いところをより確実に身につける必要があるのです。
辛抱によって意外な才能が開花する
「道は近きにあり、しかるにこれを遠きに求む」についてはお伝えしました。今日やるべきことを確実にやり、そのことで「明日やるべきこと」は完成するのです。
次に千玄室さんは孟子の「事は易きにあり、而るに諸を難きに求む」についても述べておられます。つまり、できることからさっさと片付けていきなさい、難しいことを考えているから物事が解決しないのだよ、と述べているのです。
どうしてそのようになってしまうのか? 理由の一つは好き嫌いの気持ちがあるからだと、千玄室さんは述べられています。大事なことは簡単なのに、自分で難しいと思ってしまう。嫌だと思ったら、近くに行かないし、難しいと思うと避けようとします。
若者がせっかく入った会社に、自分から合わないと決めつけ、すぐに辞めたりするのも、「遠きを求む・難きを求む」の一例です。自分はこの会社では才能が開花しないと、転職を決意する人は、次の職場でも同じことを思うかもしれません。
才能は自分から見つけていくものです。最初から合わないと決めてかかったら、見つかる才能も見つからないでしょう。
逆に、近きにある事柄について努力をする。積み重ねていく。その辛抱によって、思いがけない才能が開花します。社会の成功者にはこのタイプが少なくありません。
本記事は、月刊『理念と経営』2025年11月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






