企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
現場力
2025年8月号
後ろ向きな発想からは何も生まれない
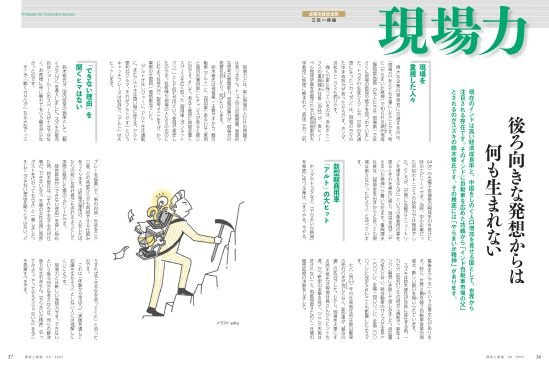
現在のインドは高い経済成長率と、中国をしのぐ人口増加を見せる国として、世界から注目される存在です。そのインドに自動車を広めた功績から「インド自動車市場の父」とされるのがスズキの鈴木修氏です。その根底には「やらまいか精神」があります。
現場を重視した人々
偉大な企業の経営者に共通するのは、「現場力」をとても大事にしたことです。特に「やらまいか精神」で知られる遠州地域(静岡県西部)の先人たちは、現場第一で気さくに現場の意見や様子を見つめていました。トヨタの生産システムや、世界の共通語になった「カイゼン」は、現場の方々のたゆまぬ努力があったからです。ホンダ、浜松ホトニクスも然りです。
強く印象に残っているのは、浜松ホトニクスの晝間輝夫社長(当時)が、後にノーベル物理学賞を受賞される小柴昌俊東京大学教授に無理に頼まれて、直径二五㌅(約64㎝)の光電子倍増管の開発を引き受けた時のエピソードです。当時、中小企業だった浜松ホトニクスの技術力では無謀でした。ところが、「世界に先駆けてニュートリノを捕まえるんだ」という小柴教授の夢を語るとそれを意気に感じ、現場全員が「やらまいか精神」で奮い立ちます。晝間輝夫社長は、「報奨金を出すからと言っても現場は燃えなかっただろう」と述べています。
新型軽商用車「アルト」の大ヒット
ホンダやトヨタなど、「やらまいか精神]を根底に持つ企業は、「すぐやる、今やる、最後までやる」という企業文化があります。特に、世界と覇を競う自動車産業の現場は、厳しい闘いを強いられています。
スズキは鈴木修氏が社長に就任する前、一九七六(昭和51)年の排ガス規制で、新型エンジン開発に失敗して苦しみました。排気量の拡大に伴い、軽自動車のサイズが全長三二〇〇㍉㍍、全幅一四〇〇㍉㍍、全高二〇〇〇㍉㍍に改定されたことも影響したようです。
七八(同53)年の社長就任時は軽自動車の売れ行きが芳しくなく、新型車が〝頼みの綱〟の状況でした。しかし、現場を大事にする鈴木修氏は現場社員さんからヒントを得、かつ新型の実車を見て、「ここで失敗は許されない」と、再度見直すために一年間の販売延期の決断をしました。
現場力とは、単に現場の人だけの問題ではありません。トップ自らの観察眼、発展的な思考の展開能力、情報収集力が、現場力の発揮を促したり、妨げたりします。
鈴木修氏は現場第一主義ですから、軽自動車「アルト」に、「商用車」あるいは「乗用と商用の兼用車」にチャンスがあると感じたのです。そして、あえて後部に荷物を置くスペースを広く取った「商用車(ボンネットバン)」として四七万円という安価で発売したのです。技術陣や現場の人たちの血のにじむような努力で、製造コストを下げ、かつ異例の全国同一価格販売でした。
「アルトきはレジャーに、アルトきは通勤に、またアルトきは買い物に使える、アルト便利なクルマ。それがアルトです」というキャッチフレーズは好評で、「アルト」は大ヒットします。
本記事は、月刊『理念と経営』2025年8月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






