企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
現場力
2025年3月号
最大の任務は「顧客の創造」です
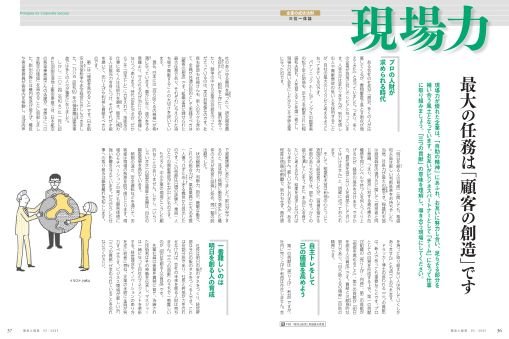
現場力が優れた企業は、「自助の精神」にあふれ、お互いに努力し合い、足らざる部分を補い合う風土となっています。お互いがビジネスパートナーとして「チーム」になって仕事に取り組みましょう。「三つの貢献」の意味を理解し、導き合う現場にしてください。
プロの人財が求められる時代
ある会社の社長が「最近、多くの人が応募してくるが、書類審査で落とす割合が増えてきた」と述べていました。つまり、多くの企業が採用に対してシビアになっています。人手不足は変わりませんが、努力を惜しむ人や貢献意欲の低い人を採用することが、自社の最大のリスクだと考えるようになってきているのです。
パナソニック ホールディングスの創業者の松下幸之助翁も、京セラを創業された稲盛和夫翁も、人を育てることを第一義とし、現場力の高い会社にしたからこそ世界企業になったのです。「明日を創る人の育成」に関しても、稲盛和夫翁は厳しい判断基準をお持ちでした。当然、社長力が最大の要です。稲盛和夫翁は経営幹部の選び方に関して「経営者と同じ意識、つまり、経営に対する責任感や危機感を同じレベルで持つ人を何人つくり上げるかが、経営の成否を分けます。ですから、責任感を持てない人を幹部にしておいてはいけません」と、明確に述べておられます。
そして、稲盛和夫翁は利他の心について造詣の深い経営者でしたが、「現場を預かる幹部のあり方次第では、部下のせっかくの能力を潰してしまう。また、本当に人を育てたいと考えるなら、結果を追求しなければなりません。厳しいかもしれませんが、ある程度は信賞必罰で、努力もせず、責任感を持って取り組まない人は外していくしかありません」とも述べておられます。
ドラッカー博士の言われる「三つの貢献」は、新人であっても重要なことです。プロとしての自覚を形成する上で、第一の貢献が組織の「売り上げ・利益」、第二の貢献が「価値を高めること」、第三の貢献が「明日を創る人の育成」です。貢献とは献身的な努力であり、「自ら助くるの精神」(自助の精神)です。
自主トレをして己の価値を高めよう
第一の貢献は「売り上げ・利益」ですが、社内に売り上げや利益は存在しません。会社のあらゆる費用を賄ったり、研究開発費を捻出したり、給料を上げたり、雇用を守ったり、競争の中から企業の存続を守ってくださっているのは、実はお客様なのです。社長も幹部も社員さんも、新人の方々も含めて、全員が共通の目的として実践すべきは「顧客の創造」です。組織全員に課せられた最大任務であり、それぞれに与えられた持ち場で貢献することの大切さを説いています。
現在、日本には「自ら助くるの精神」が希薄になっています。豊かになり、誰かを守る意識より、守られるのが当たり前の意識になりつつあります。時代の変化ですが、だからこそ「自主トレ」に力を入れて、技術系の仕事に就く人は技術力を磨き、販売に携わる人は販売力を身につけ、それぞれが才能を磨いて、売り上げや利益に貢献すべきなのです。
第二は「価値を高めること」です。日本航空は労使紛争や赤字経営に苦しんできました。一九八五(昭和60)年の御巣鷹山墜落事故では多くの人々が犠牲になりました。
しかし、二〇二四(令和6)年一月に起きた羽田空港地上衝突事故では、日本航空の客室乗務員さんの活躍が、世界中に「日本航空の価値」を高めることに貢献しました。脱出の際には機内放送が使えず、機長や客室乗務員が客室内を移動し、ほぼ肉声で避難誘導にあたりました。脱出が完了するのと、ほぼ同じ時間に衝突で発生した機体の火災が客室に延焼し始め、間一髪の脱出劇でした。
状況観察力、判断力、指示、機敏な動き、これらの総合力が、乗客乗員三七九名を誰一人傷つけずに炎上する機体から救出したのです。この奇跡は日頃の訓練と、乗員一人ひとりの貢献意欲が生み出したものです。
もちろん、中小企業の現場にこうした劇的なことはありません。しかし、「いらっしゃいませ」の誠実な態度と笑顔は、自社の顧客価値を高めています。
納期の速さ、安全運転などを通じて、お客様は現場の熱意を肌で感じとります。現場のモチベーションの高さも顧客価値に強い影響を与えています。だらだらした仕事への取り組みは顧客離れを起こします。
本記事は、月刊『理念と経営』2025年3月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






