企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
現場力
2024年8月号
一日勉強が遅れたら、日本の国が一日遅れる
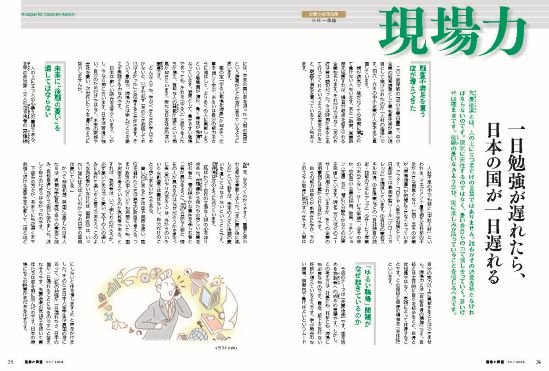
先憂後楽とは、人の上に立つ者だけの言葉ではありません。誰もがその決意を持たなければならないのです。現状に安住するのではなく、憂いを自らの力で消し去っていく。若い時代は種まきです。後顧の憂いなきよう学び、後に楽しみが待っていることを信じるべきです。
顧客不満足を買う店が増えてきた
二〇二四年版の『中小企業白書』で、中小企業の経営課題として最も優先度が高い項目として挙げられたのが「人材の確保」です。四六・六%の中小企業が人手不足に直面しています。
親が病気で、稼ぎたくても時間に縛られて働けない人もいます。あと一時間、営業時間を延長すれば、損益分岐点を超えられる企業もあります。それだけではなく「あのお店は昔は親切だった。今は時間が来ると出て行ってくれというような態度をされる」と、顧客不満足を買っているケースもあります。
人材不足の中でも特に「中核人材」といわれる、マネジメント層を担える幹部の不足が大きな問題となり、七四・五%の企業が「現場指導」が的確にできなくなっています。アフターコロナや人手不足対策として、日創研では動画学習ツール「グロースカレッジ」を提供しています。①自社の業務スキル取得、②製造業などの「自社独自の技術・技能のスキルアップ」、③サービス産業の「おもてなし・サービス手順」、④そのほか、中堅中小企業の採用、教育、リテンション(定着)など、幅広い分野でかなりの効果を発揮しています。現在二万人ほどのユーザーに活用されていますが、多くの企業の活用事例には驚かされるばかりです。
自らの能力は自らが前向きに学び、今以上のスキル取得に尽力すべきです。人間は自分の実力以上に貢献することはできません。現場力とは「自修自得の精神」です。自修とは主体的に自らを修めること。自得とは知識ではなく、実践によって体得することです。この自修と自得の精神を「主体性」といいます。
「ゆるい職場」問題がなぜ起きているのか
今回のテーマは「先憂後楽」です。国を治める為政者への戒めの言葉です。しかし、この考え方は、社長にも、幹部にも、現場にも必要なものです。最近、部下を叱れない幹部が増えているようです。学ぶ機会のない現場、時間内で働けばよいというムードには、本来の高い志を持った「人財の育成」という課題がどこか抜け落ちているように思います。
案の定「ゆるい職場化現象」が起きて、仕事を通して学ぶ、あるいは自分の能力をさらに伸ばして、より多くの人に貢献しようという価値観が薄れ、働く意味が希薄になっています。結果として、働きやすい職場であっても、それを「ゆるい」と感じる人たちが増え、有能な人の離職が進むという問題が起きています。新たな日本社会の深い憂慮です。
どんな人でも、学ぶべきときに学んでおかないと、いずれ必ず「あのとき勉強しておけばよかった」と反省するときがきます。そういう意味で、現場力とは学んだことを絶えず実践する力なのです。
日本は厳しい時代を迎えています。しかし、今なら間に合います。日本は苦境に強い。自分のためだけではなく、未来の家族や会社を憂い、次世代にツケを遺さぬように努力しませんか。
本記事は、月刊『理念と経営』2024年8月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






