企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
現場力
2020年3月号
明確なゴールを持てば不安や恐れは克服できる
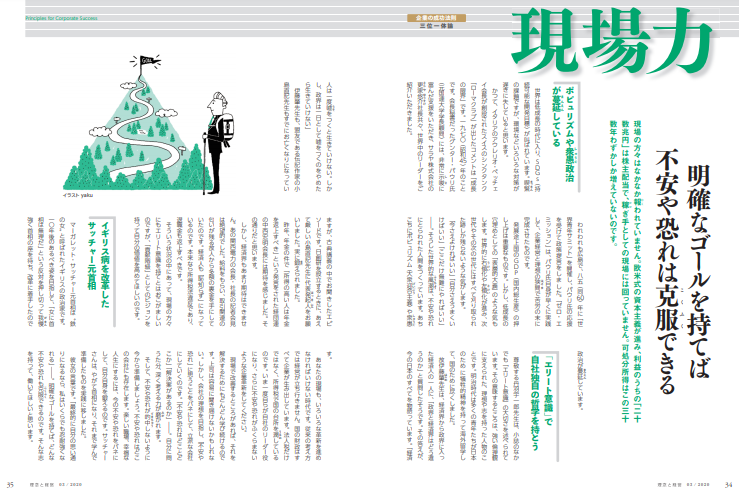
現場の方々はなかなか報われていません。欧米式の資本主義が進み、利益のうちの「二十数兆円」は株主配当で、稼ぎ手としての現場には回っていません。可処分所得はこの三十数年わずかしか増えていないのです。
ポピュリズムや衆愚政治が蔓延している
世界は低成長の時代に入り、SDGs(持続可能な開発目標)が叫ばれています。喫緊の課題ですが、環境などいろいろな対策が遅きに失していると思います。
かつて、イタリアのアウレリオ・ペッチェイ会長が創設されたスイスのシンクタンク「ローマクラブ」が出したコメントは「成長の限界」です。1970(昭和45)年のことです。会長秘書だったグンター・パウリ氏(元国連大学学長顧問)には、非常に示唆に富んだ支援をいただき、サラヤ株式会社の更家悠介社長共々、世界中のリーダーをご紹介いただきました。
われわれも広島で、85(同60)年に「世界青年サミット」を開催し、パウリ氏の応援を受けて政策提言をしました。「ゼロ・エミッション」は、パウリ氏自身が早くに実践して、企業経営と理想の狭間で苦労の末に完成させたものです。
発展途上国のGDP(国内総生産)の押し上げは重要なものです。しかし、低成長の穴埋めとしての「表層的大義」のような気もします。世界的に右傾化や左傾化が進み、次世代やその次の世代にはすべて刈り取られた跡しか残らないような気がします。
「今さえよければいい」「自分さえうまくいけばいい」「ここだけ無難にやればいい」―。そうした世界的な風潮は、不安や恐れにとらわれた人間をつくっています。あちこちにポピュリズム(大衆迎合主義)や衆愚政治が蔓延しています。
「エリート意識」で自社独自の哲学を持とう
尊敬する丹羽宇一郎先生は、小誌のなかでも「エリート意識」の大切さを述べられています。その意味するところは、強い倫理観に支えられた、理想や志を持った人物のことです。明治時代は多くの青年たちが日本のために犠牲的精神を持って海外留学して、国のために尽くしました。
故伊藤肇先生は、経済界から政界に入った経済人の一人に、「政界と経済界はどう違うのか」と質問したそうです。その答えが、今の日本のすべてを物語っています。「経済人は一度嘘をつくと生きていけない。しかし、政界は一日として嘘をつくのをやめたら生きていけない」
伊藤肇先生も、盟友である伝記作家の小島直記先生もすでにお亡くなりになっていますが、古典講義の中でお聞きしたエピソードです。日創研を設立するときに、あえて厳しい小島直記先生に代表発起人をお願いしました。実に鍛えられました。
昨年、年金の件で「所得の高い人は年金を返上すべき」という発言をされた経団連の中西宏明会長には期待を感じました。その通りだと思います。
しかし、経済界もあまり期待はできません。あの関西電力の会長・社長の記者会見は絶望的でした。給料をもらい、取引関連の匂いが残る故人から多額の裏金を手にしていたのです。経済人も「恥知らず」になっているのです。本来なら所得税法違反であり、退職金も返上すべきです。
そういう状況の中にあって、現場の方々にもエリート意識を持てとはおこがましいのですが、「貢献階級」としてのビジョンを持って自分の価値を高めてほしいのです。
本記事は、月刊『理念と経営』2020年3月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






